はじめに:「在留資格取得許可申請」ってどんな手続き?
日本で暮らす外国人の方や、外国人をサポートする方へ。「在留資格取得許可申請(ざいりゅうしかく しゅとく きょか しんせい)」という手続きについてご存知でしょうか?
これは、例えば日本で外国籍の赤ちゃんが生まれた場合や、もともと日本の国籍を持っていた人が日本にいながら日本の国籍をやめた(または失くした)場合など、特別な理由で、通常の入国の手続きをせずに日本にいることになった人が、そのまま60日以上日本にいたい場合に、ちゃんとした「日本にいるための資格(在留資格)」をもらうための、法律で決められた手続きのことです。[1]
普通、外国の人が日本に来る時は、来る前や来た時に「在留資格」が決まります。でも、この「取得申請」は、すでに日本にいる人が、後から在留資格をもらう、という少し特別なケースのための手続きなんです。
この記事では、2025年の最新情報をもとに、この「在留資格取得許可申請」について、どんな時に必要で、どんな書類がいるのか、いつまでに手続きしないといけないのか、などを分かりやすく解説していきます。正しい手続きを知っておくことは、安心して日本で暮らすためにとても大切です。
他の手続きとの違いは? 「取得」「変更」「更新」…似てるけど違う!
「在留資格」に関する手続きには、似たような名前のものがいくつかあります。でも、目的や対象になる人が違うので、間違えないようにしましょう。
- 在留資格「認定」証明書交付申請(COE申請): これは、外国にいる人を日本に呼ぶために、日本に来る前に日本の入管事務所にする申請です。[3] 今回説明する「取得申請」は、もう日本にいる人が対象です。
- 在留資格「変更」許可申請: これは、すでに何かの在留資格を持って日本にいる人が、活動内容を変える(例:留学生が会社員になる)ために、資格の種類を変える申請です。[3] 「取得申請」は、そもそも資格がない状態から新しくもらう手続きです。
- 在留期間「更新」許可申請: これは、今持っている在留資格の活動を続けるために、日本にいられる期間を延ばす申請です。[3]
- 査証(ビザ)申請: これは、基本的には外国にある日本の大使館などにする、入国前の手続きです。[3] 「取得申請」は日本国内の入管事務所にします。
このように、手続きの名前(「取得」「変更」「更新」「認定」)には、それぞれちゃんと意味があります。[1] 自分の状況に合った正しい手続きを選ぶことが、とても重要です。「取得申請」は、他とは違う特別な状況のための手続きだと覚えておきましょう。
この手続きが必要になるのは、主にどんな人?
「在留資格取得許可申請」が必要になるのは、主に次のような人たちです。
- 日本で生まれた外国籍の赤ちゃん: 日本で生まれても、お父さんやお母さんが外国人だと、赤ちゃんは日本の国籍をもらえません(日本のルールです[1])。その赤ちゃんが、生まれてから60日以上日本にいたい場合。[1]
- 日本の国籍をやめた・失くした人: もともと日本の国籍だった人が、日本に住んでいる間に国籍をやめたり失くしたりして、その後も外国籍の人として60日以上日本にいたい場合。[1]
どちらの場合も、ただ「日本にいたい」というだけでなく、「どんな活動をするための資格(例:家族として住む『家族滞在』、日本人と結婚した人の『日本人の配偶者等』など)が欲しいのか」を考えて、その資格をもらうための条件を満たしている必要があります。[1]
ポイント: 「取得申請」は、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんや、日本で国籍をやめた人などが、60日以上日本にいるために必要な特別な手続き。他の「変更」や「更新」とは違う!
申請の進め方:2025年の手続きガイド
大事な締め切り:「60日ルール」と「30日ルール」
この手続きには、とても大事な締め切りが2つあります。
- 60日間いてOK: 赤ちゃんが生まれた日や、国籍をやめた日から60日間は、特別な在留資格がなくても日本にいることが許されています。[1] いろいろな手続き(出生届を出す、自分の国に登録する、日本から出る準備をするなど)をするための時間ですね。
- 30日以内に申請!: でも、もし60日を超えて日本にいたいなら、理由ができた日(生まれた日など)から30日以内に、「在留資格ください」という申請をしなければいけません。[1]
「60日間いられるのに、申請は30日以内?」と不思議に思うかもしれません。これは、「60日以内に日本を出るなら申請しなくていいけど、長くいたいなら、早めに手続きを始めてね」という意味だと考えられます。[3] 30日の締め切りを過ぎてしまうと、60日を超えて日本にいることがルール違反(不法残留)になってしまう危険があるので、注意が必要です。[2] 理由ができたら、すぐに計画を立てて準備を始めることが大切です。
どんな書類が必要? 申請書と証明する紙
基本の提出書類
まず、どんな場合でも基本となる書類です。
- 在留資格取得許可申請書: 「資格ください」の申請用紙。欲しい資格の種類によって用紙が違います。[1] 入管のウェブサイトからダウンロードするか、窓口でもらえます。[1]
- 申請する理由を証明する書類: なぜこの申請をするのかを証明する公的な紙(生まれた証明や、国籍をやめた証明など)。[1]
- 欲しい資格の条件を満たしていることを証明する書類: どんな資格が欲しいかによって、必要な書類が大きく変わります。入管のウェブサイトでしっかり確認しましょう。[1]
大事なのは、ただ「生まれたから」という理由だけでなく、「欲しい資格(例えば『家族滞在』)の条件をちゃんと満たしていますよ」ということを証明する書類を揃えることです。
赤ちゃんが生まれた場合の必要書類(よくあるケース)
日本で外国籍の赤ちゃんが生まれた場合(例えば、お父さんもお母さんも永住者ではない場合など)に必要な書類の例です。これは一番よくあるケースですが、色々な場所から書類を集めて、締め切りまでに提出する必要があるので、特に注意しましょう。
- 生まれたことを証明する書類: 市役所や区役所などでもらう「出生届受理証明書」か「出生届記載事項証明書」。[5]
- 赤ちゃんのパスポート: 基本的には見せる必要があります。もし申請時にまだできていなければ、自分の国の大使館などで申請中であることを示す紙(受付票のコピーなど)か、「パスポートがまだない理由書」を出します。[5]
- 住民票の写し: 赤ちゃんを含めて、家族みんなが載っているもの。国籍や在留資格などの情報が省略されていないもの。発行から3ヶ月以内のものが必要です。[5]
- お父さん・お母さん(生活を支える人)の在留カードとパスポートのコピー:[5]
- 生活を支える人の仕事とお金の証明: 赤ちゃんを養っていけることを示すために、次のような書類が必要です。
- 会社に勤めている証明(在職証明書)[5]
- 住民税の証明書(課税証明書と納税証明書):最近のもので、収入と税金を払った状況がわかるもの。[5]
- もし親が留学生などの場合は、銀行の貯金残高証明書など。[7]
- 身元保証書: 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住許可」の申請をする時に必要です。[5] 普通は、お父さんかお母さんが保証人になります。
- 質問書: 場合によっては提出が必要なことも。[5] 結婚関係のビザでよく使われますが、赤ちゃんの申請でも念のため準備した方が良いと言われることもあります。[6]
これらの書類集めは、赤ちゃんが生まれてすぐの大変な時期に、役所、会社、大使館、入管など、色々な場所とやりとりしながら進めないといけないので、親にとっては結構な負担になることがあります。
▼赤ちゃんが生まれた時の必要書類チェックリスト▼
| 書類の名前 | どこでもらう? | ポイント |
|---|---|---|
| 在留資格取得許可申請書 | 入管ウェブサイト、入管窓口 | 欲しい資格の種類の用紙を使う[1] |
| 出生届受理証明書 or 出生届記載事項証明書 | 市区町村役場 | 出生届を出した後にもらう[5] |
| 子のパスポート or 旅券未取得理由書 | 自国の大使館・領事館 | 原本を見せるのが基本。なければ理由書など[5] |
| 住民票の写し | 市区町村役場 | 家族全員記載、情報省略なし、3ヶ月以内発行[5] |
| 親(扶養者)の在留カード・パスポートのコピー | – | 有効なもの[6] |
| 扶養者の職業証明(在職証明書など) | 勤務先など | 状況に応じて[5] |
| 扶養者の税金証明(課税・納税証明書) | 市区町村役場 | 最近の所得・納税状況がわかるもの、3ヶ月以内発行[5] |
| 身元保証書 | 入管ウェブサイト | 特定の資格(日本人配偶者等、永住者等)申請時に必要[5] |
| 質問書 | 入管ウェブサイト | 場合によって必要[5] |
注:これは一般的な例です。状況や欲しい資格によって他の書類が必要なこともあります。必ず最新情報を入管ウェブサイトで確認するか、専門家に相談してください。
このリストは、赤ちゃんが生まれた時に必要な書類をまとめたものです。役所への出生届(14日以内)[5]、大使館への登録・パスポート申請(かかる時間は国による)[5]、そして入管への取得申請(30日以内)[1]と、締め切りが続くので、このリストが準備の助けになれば幸いです。
日本の国籍をやめた・失くした場合の必要書類
日本の国籍をやめたり失くしたりした人が申請する場合は、主に次のような書類が必要です。
- 国籍が変わったことを証明する書類: 日本の役所(法務局など)が出した国籍をやめた証明や、戸籍謄本(日本の戸籍から名前が消えたことがわかるもの)、外国の国籍をもらった証明など。[2]
- 住民票の写し: 今どこに住んでいるかを示すもの。[17]
- 欲しい資格の条件を満たしていることを証明する書類: 上と同じく、欲しい資格の種類によって必要な書類が違います。[1]
このケースは赤ちゃんの場合より少ないですが、国籍が変わったことを証明する公的な書類をしっかり準備することが大切です。
欲しい資格によって必要な書類
どんな在留資格(例:「家族滞在」「日本人の配偶者等」「定住者」など)が欲しいかによって、追加で必要な書類が変わってきます。[1] 例えば、「家族滞在」なら親との関係を証明する書類、「日本人の配偶者等」なら日本人との結婚を証明する書類などです。自分がどの資格に当てはまるか考えて、必要な書類を漏れなく準備しましょう。
どこに出すの? 誰かにお願いできる?
- 出す人: 基本的には本人(16歳以上)か、親などの法定代理人です。[1] 赤ちゃんの場合は、普通は親が申請します。
- 代わりに出せる人(取次者): 特別な届け出や許可を受けた人なら、本人の代わりに申請できます。[1] 例えば、
- 本人が働いている会社や通っている学校の人
- 技能実習のお世話をする団体
- 外国人を助ける活動をしている団体[11]
- 届け出をした弁護士や行政書士[2]
- 本人が16歳未満だったり、病気などで役所に行けなかったりする場合の家族など(入管がOKした場合)[1]
- 出す場所: あなたが住んでいる場所を担当する地方の入管事務所(地方出入国在留管理局、支局、出張所)の窓口に出します。[1] 郵送では受け付けてくれません。[11] どこの事務所に行けばいいかは、入管のウェブサイトで確認できます。[1]
- オンライン申請: インターネットを使って申請することもできます。[11] 役所に行かなくていいし、24時間いつでも申請できて便利です。[17] ただし、本人がオンライン申請するにはマイナンバーカードが必要な場合があります。[22] また、オンラインで申請できる資格の種類が決まっているので、確認が必要です。[22]
オンライン申請は、国が進めている役所手続きのインターネット化[23]の一環です。これからますます便利になるかもしれませんが、新しいシステムに慣れる必要もありますね。
特別ルール:永住者の子供の永住申請
もし、お父さんもお母さんも永住者だったり、片方の親が永住者で特別な条件を満たしていたりする場合、日本で生まれた赤ちゃんは、普通の在留資格取得申請ではなく、生まれてから30日以内に、いきなり「永住許可申請」ができることがあります。[5]
これは特別な手続きで、必要な書類も少し違います。[5] 身元保証書なども必要です。[5]
ただし、必ず永住許可がもらえるわけではなく、親の状況などもチェックされます。[6] もし永住許可がダメでも、「定住者」という資格がもらえる可能性はあります。[6] 大事なのは、この特別な永住申請は生まれてから30日以内にしないといけないこと。この締め切りを過ぎると、普通の在留資格取得申請(多くは「永住者の配偶者等」)をすることになります。[6] これは、永住者の子供に特別なチャンスを与えつつも、締め切りはきっちり守ってね、というルールなんですね。
ポイント: 書類は欲しい資格に合わせて準備。提出は住んでいる所の入管へ。本人か親、または専門家などが申請できる。オンライン申請も可能。永住者の子供は30日以内なら直接永住申請できる特別ルールあり!
手数料・かかる時間・許可されたら?(2025年情報)
申請にお金はかかる?
この「在留資格取得許可申請」自体には、手数料はかかりません。[1] 許可された時も、お金(収入印紙)は必要ありません。
ただし、他の多くの在留資格の手続き(資格を変える、期間を延ばすなど)は、2025年4月1日から(またはそれ以前から)手数料が変わっています。[19] この取得申請は無料[1]ですが、将来家族が他の手続きをする時には新しい手数料がかかるので、知っておくと良いでしょう。
どれくらい時間がかかる?
審査にかかる時間は、公式には「理由ができた日(生まれた日など)から60日以内」とされています。[1] これは、申請が必要になる60日間の猶予期間に合わせています。場合によっては、申請したその日に手続きが終わる(即日処理)こともあります。[1]
他の手続き(例えば、COE申請は1~3ヶ月、変更・更新は2週間~1ヶ月など)[3]と比べると、この取得申請は比較的早く終わる可能性があるようです。特に、赤ちゃんが生まれて「家族滞在」を申請するような、よくある分かりやすいケースでは、早く終わることも期待できるかもしれません。
許可されたらどうなる?
申請がOKされると、「在留カード」がもらえます。[1] これは、日本に長くいる外国人の身分証明書で、在留資格の種類や期間などが書かれています。日本にいる間はいつも持っている必要があります。ちなみに、16歳未満の子供(赤ちゃんも)の在留カードには、顔写真は載りません。[16]
ポイント: 取得申請自体は無料!審査期間は60日以内、早い時はその日のうちに終わることも。許可されたら在留カードがもらえる。
2025年のルールや動きについて
2024年の法律改正の影響は?
2024年に、日本の出入国のルール(入管法)がいくつか改正されました。[19] これらが実際に使われ始めるのは2025年以降になるものもあります。[24]
主な変更点は、
- 将来的にマイナンバーカードと在留カードが1枚になる計画。[24]
- 技能実習に代わる新しい「育成就労」制度ができる。[19]
- 永住許可のルールを見直す動き(厳しくなる方向?)。[24]
これらの変更が、今回説明している「在留資格取得許可申請」の手続きに、2025年すぐに大きな影響を与えることは少ないかもしれません。関係する資格や手続きの種類が違うからです。
でも、法律の改正は、日本の入管ルール全体の方向性を示しています。例えば、永住許可を厳しくする[24]ような流れが、取得申請の際の親の生活力のチェックなどに、間接的に影響する可能性はゼロではありません。マイナンバーカードとの一体化も、将来は手続きのやり方を変えるでしょう。2025年時点では、これらの動きに注目しておくことが大切です。
他の手続きの手数料が変わったこと
前にも触れましたが(III.A)、在留資格を変えたり、期間を延ばしたりする他の多くの手続きでは、2025年4月1日(またはそれ以前)から手数料が変わっています。[19] この取得申請は無料のままですが、将来、家族が他の手続きをする時には新しい手数料がかかる、ということは覚えておくと良いでしょう。
他の新しい制度との関係は?
日本は今、すごく能力の高い外国人(J-Skip/J-Findなど)や、人手が足りない分野で働く外国人(特定技能)を受け入れるための新しい制度[19]を進めています。
これらの制度は、主に仕事や研究のためのものなので、赤ちゃんが生まれたり国籍が変わったりした時の「在留資格取得許可申請」(多くは家族関係の資格)とは、直接の関係はあまりありません。でも、もし申請する赤ちゃんの親が、こういう新しい資格を持っている場合は、その親の状況を証明するために、関連する書類が必要になるかもしれません。
ポイント: 2024年の法改正がすぐにこの申請に大きく影響することは少ないかも。でも、永住許可が厳しくなる流れや、マイナンバーカードとの一体化は将来影響する可能性あり。他の手続きの手数料は上がっている。
これも大事! 関連する手続き
「在留資格取得許可申請」をする前や、それと同時に、必ずやらなければいけない大事な手続きがあります。
赤ちゃんが生まれたら:①役所への出生届
- いつまで?: 生まれた日から14日以内。[5]
- どこへ?: 住んでいる所か、生まれた所の市区町村役場。[9]
- いるもの(例): 生まれた証明書(病院からもらう)、母子手帳、届け出る人の身分証明(在留カードなど)。[7]
- もらうもの: 届け出を出したら、「出生届受理証明書」や「出生届記載事項証明書」、そして赤ちゃんも入った家族全員の「住民票の写し」をもらっておきましょう。[5] これらは後の手続きで必要になります。
これは、日本で赤ちゃんが生まれたことを正式に記録する最初の、そしてとても大事な手続きです。14日以内という締め切りは必ず守りましょう。
赤ちゃんが生まれたら:②自分の国の大使館への届け出とパスポート申請
- 何のため?: 赤ちゃんのお父さん・お母さんの国に「生まれました」と届け出て、赤ちゃんの国籍をはっきりさせ、パスポートを作ってもらうためです。[1]
- やり方・いるもの: 国によって全然違うので、必ず自分の国の大使館や領事館に確認してください。[5] 日本の役所でもらった出生届の証明書が必要なことが多いです。[7]
- かかる時間: パスポートができるまで時間がかかることがあります(例:2週間くらい[6])。もし入管への申請締め切り(生まれてから30日)までにパスポートが間に合わなくても、大使館で申請中という証明書などがあれば大丈夫な場合があります。[5]
これは、赤ちゃんの国籍と、世界で使える身分証明書(パスポート)を作るために、絶対に必要です。
【要注意!手続きの連鎖と締め切り】
赤ちゃんが生まれた時のこの3つの手続き(①役所への出生届、②大使館への登録・パスポート申請、③入管への在留資格取得申請)は、それぞれ締め切りがあって、しかもつながっています。役所(14日以内)[5]でもらう書類は、大使館[5]と入管[5]の両方の手続きで必要です。そして、入管への申請自体にも30日以内[1]という厳しい締め切りがあります。大使館でのパスポート発行に時間がかかるかも[6]しれないことを考えると、本当に時間との勝負です。赤ちゃんが生まれてすぐのバタバタしている中で、役所、大使館、入管という3つの違う場所と、ほぼ同時に、手際よく手続きを進める必要があります。
日本の国籍をやめた・失くしたら:関係する届け出
日本の国籍をやめたり失くしたりした場合は、そのことを日本の役所(住んでいる所の法務局や、外国にいる場合は大使館など[10])に届け出る手続きが必要になることがあります。外国の国籍をもらった証明書や、日本の戸籍謄本(名前が消えたことがわかるもの)などが必要です。[17] これは、入管への申請とは別に、国籍が変わったことを法的に記録するための手続きです。
ポイント: 赤ちゃんが生まれたら、①14日以内に役所へ出生届、②その後すぐに大使館へ登録&パスポート申請、③そして30日以内に入管へ取得申請、という流れを頭に入れて、計画的に進めよう!
困ったときは? 情報収集と相談窓口
手続きが複雑で分からないことや、心配なことがあったら、頼れる情報源や相談窓口があります。
- 出入国在留管理庁(入管)のウェブサイト:(https://www.moj.go.jp/isa/)
これが一番正確で新しい情報源です。[18] 必要な書類のリスト[1]や、オンライン申請の方法[11]、全国の入管事務所の場所[1]、よくある質問[19]などが載っています。 - 外国人在留総合インフォメーションセンター:
電話で、入管の手続きに関する一般的な質問に、たくさんの国の言葉で答えてくれます。[18]
電話番号: 0570-013904 (海外などからは 03-5796-7112)
時間: 平日 8:30~17:15 - FRESC(フレスク):
東京の新宿にある、外国人のための総合相談センターです。入管、労働局、法律相談所などが集まっていて、色々な相談にまとめて対応してくれます。[19]
電話番号: 0570-011000 (海外などからは 03-5363-3013)
時間: 平日 9:00~17:00 - 専門家(弁護士・行政書士):
複雑な場合や、自分でやるのが大変な場合は、入管手続きの専門家である弁護士や行政書士に相談したり、手続きをお願いしたりするのも良い方法です。[1] 最新のルールに基づいたアドバイスや、書類作成の手伝い、入管とのやりとりなどを代行してくれて、許可の可能性を高めてくれることが期待できます。[14]
入管のウェブサイトや電話相談[20]、生活説明ビデオ[27]など、色々な言葉での情報提供もされていますが、やはり日本語の情報が一番詳しいことが多いです。分からないことは、これらの窓口や専門家をうまく活用しましょう。
ポイント: 困ったらまず入管のウェブサイト! 電話相談やFRESCも活用しよう。難しい場合は専門家にお願いするのも手。
まとめ:2025年、スムーズな申請のために
「在留資格取得許可申請」は、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんや、日本で国籍が変わった人などが、60日を超えて日本にいるために必要な、少し特別な、でもとても大事な手続きです。他の在留資格の手続き(変更や更新など)とは違うことをしっかり理解して、正しい手続きを選ぶことが大切です。
2025年にこの申請をスムーズに進めるためには、特に以下の点が重要になります。
- 締め切りは絶対守る!: 理由ができてから30日以内の申請期限は本当に大事です。すぐに準備を始めましょう。
- 書類は正確に、漏れなく: 申請する理由と、欲しい資格の条件を満たしていることを証明する書類を、間違いなく、足りないものがないように準備しましょう。特に赤ちゃんの場合は、チェックリスト(表1)などを参考に。
- 関連手続きとの連携(特に赤ちゃん): 役所への出生届(14日以内)、大使館への登録・パスポート申請、そして入管への取得申請(30日以内)。この3つの手続きを、時間との戦いの中でうまくつなげて進める必要があります。
- 2025年の動きを知っておく: 他の手続きでルールが変わったり、手数料が上がったりしていますが、この「取得申請」自体は無料のままであることなどを確認しておきましょう。
- 情報収集と相談を大切に: 入管のウェブサイトや相談窓口をフル活用し、分からないことは積極的に聞きましょう。複雑な場合は、早めに専門家に相談するのも良い方法です。
この手続きは、他とは違うルールや厳しい締め切りがあるので、前もってしっかり理解し、計画的に準備して、すぐに行動することが、2025年においてもスムーズに在留資格をもらうためのカギになります。
引用文献
[1] 在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理庁 他
[2] ビザ申請に関する手続き(4)在留資格取得許可申請 他
[3] 出入国在留管理局(入管)への申請・届出等の手続まとめ – ビザ申請オンライン 他
[4] 在留資格ってなに?ビザとの違いや取得方法、29種類まとめて解説! – Jinzai Plus
[5] 外国人の出産後|在留資格の申請などの必要な手続きや制度を解説 – メディフォン 他
[6] 赤ちゃんが生まれた時のビザの必要書類とお手続き 他
[7] 日本に住む外国籍家庭に赤ちゃんが生まれたときの大切な3つの手続き 他
[8] お子さんが生まれたり家族に変化があったときのビザ手続き
[9] 在留資格取得許可申請(外国人の子どもが生まれたとき) 他
[10] ビザ申請に関する手続き(4)在留資格取得許可申請
[11] 在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 – 法務省 他
[12] 在留資格をどこに申請するのか – 外国人雇用・就労VISAサポートセンター
[13] 2.3 在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ – ジェトロ
[14] 出入国在留管理庁(入管)とは?ビザ取得に関わる役割や注意点を解説 他
[15] ビザ(査証)|外務省 – Ministry of Foreign Affairs of Japan
[16] 在留資格取得許可申請書の書き方と記載例永住ビザ 他
[17] ビザ申請に関する手続き(4)在留資格取得許可申請 他
[18] 在留資格 | HAMAPO – はままつ多文化共生・国際交流ポータルサイト 他
[19] 出入国在留管理庁ホームページ – 法務省 他
[20] 外国人在留総合インフォメーションセンター等 | 出入国在留管理庁 他
[21] 出入国在留管理庁 | あなたの相談窓口ナビ – 政府広報オンライン
[22] 在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 他
[23] Visit Japan Web – デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション 他
[24] 令和6年入管法等改正法について | 出入国在留管理庁 他
[25] 在留手続等に関する手数料の改定 | 出入国在留管理庁 他
[26] 外国人(がいこくじん)在留(ざいりゅう)総合(そうごう)インフォメーションセンター
[27] 生活オリエンテーション動画(出入国在留管理庁作成)/Daily Life Orientation Video – 君津市
[28] 申請等取次研修会 – 公益財団法人入管協会
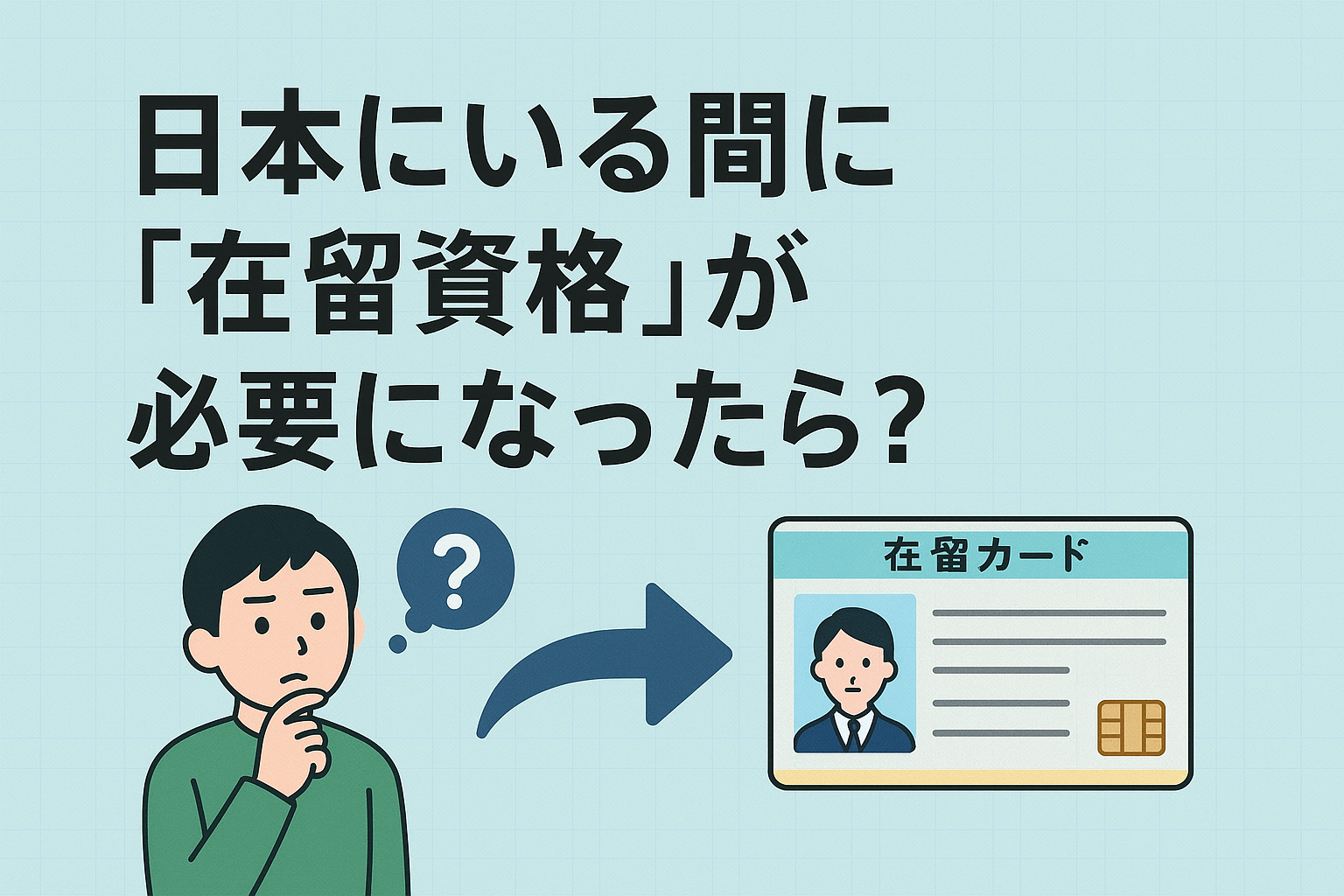

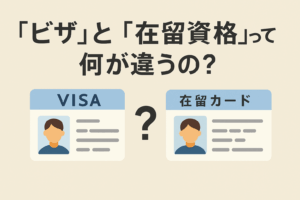
コメント