1. 概要
本報告書は、2025年に日本全国で施行される、義務的支援制度、定期的な面談の義務、行政機関への通報義務に関する主要な変更点と取り組みについて概説するものである。2025年は、労働者のワークライフバランス、外国人労働者の受け入れ体制、企業における倫理的な内部通報制度など、多岐にわたる分野で重要な法改正が予定されている。これらの変更は、企業の人事戦略、コンプライアンス体制、および従業員の福祉に大きな影響を与える可能性があり、企業はこれらの新たな義務を理解し、適切に対応する必要がある。本報告書では、これらの主要な変更点を詳細に分析し、企業が取るべき対応について考察する。
2. 2025年における義務的支援制度
2.1. 仕事と育児・介護の両立支援の強化(改正育児・介護休業法に基づく)
2025年には、改正育児・介護休業法に基づき、仕事と育児または介護の両立を支援するための義務的な措置が大幅に拡充される。これらの改正は、労働者の多様な働き方を支援し、育児や介護を理由とした離職を防ぐことを目的としている 1。
2.1.1. 育児休業等に関する措置の拡大
2025年4月と10月には、育児休業および関連する措置に関して、以下のような重要な変更が段階的に施行される。
- 子の看護等休暇の拡充: これまで「子の看護休暇」と呼ばれていたものが「子の看護等休暇」に名称変更され、対象となる子の年齢が小学校就学前から小学校3年生修了までに拡大される。また、休暇の取得理由に、子の病気やけがだけでなく、感染症に伴う学級閉鎖や、入園式・入学式・卒園式への参加も含まれるようになる 1。さらに、これまで労使協定により除外可能であった勤続6ヶ月未満の労働者も、原則としてこの休暇を取得できるようになる 2。この変更は、より多くの労働者が、より幅広い状況で育児に関する休暇を取得できるようにすることを意図している。
- 所定外労働の免除対象の拡大: 所定外労働(残業)の免除を申請できる労働者の範囲が、これまでの「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大される 1。これにより、より長い期間にわたり、育児中の労働者が残業を免除される可能性が高まり、仕事と家庭生活の両立を支援する。
- 育児のためのテレワーク導入の努力義務化: 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主は必要な措置を講じる努力義務を負うことになる 1。また、3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の導入が困難な場合、その代替措置としてテレワークを導入することも努力義務となる 1。これらの措置は、柔軟な働き方を促進し、育児と仕事の両立を支援する。
- 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置の義務化: 2025年10月1日より、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、以下のいずれか2つ以上を実施することが義務付けられる。労働者はこれらの措置の中から1つを選択して利用できる 1。
- 始業時刻・終業時刻の変更
- テレワーク(月10日以上)
- 短時間勤務制度
- 新たな休暇の付与(年間10日以上)
- 保育施設の設置・運営など この義務化は、いわゆる「小1の壁」に対応し、小学校入学前の子を持つ労働者の就労継続を支援する重要な措置である。
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化: 2025年10月1日より、事業主は、労働者またはその配偶者からの妊娠・出産の申し出時や、子が3歳になるまでの適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、その意向を踏まえた必要な配慮を行うことが義務付けられる 1。これは、労働者一人ひとりの状況に合わせた支援を提供することを目的としている。
2.1.2. 介護離職防止に向けた支援の強化
高齢化が進む日本において、介護離職は深刻な問題となっている。改正育児・介護休業法では、介護離職を防止するための措置も強化される。
- 介護離職防止のための雇用環境整備の義務化: 事業主は、介護休業や介護と仕事の両立支援制度に関する研修の実施、相談体制の整備、社内における利用事例の収集・提供、制度の利用促進に関する方針の周知など、雇用環境の整備を行うことが義務付けられる 2。これらの措置は、労働者が安心して介護と仕事を両立できる環境を整備することを目的としている。
- 介護に直面した労働者に対する個別の周知・意向確認等の義務化: 介護に直面した労働者から申し出があった場合、事業主は介護休業制度や介護両立支援制度の内容、申請先、介護休業給付金に関する事項などを個別に周知し、休業や支援制度の利用意向を確認することが義務付けられる 2。また、介護に直面する前の早い段階(40歳頃)の労働者に対しても、これらの情報提供を行うことが義務付けられる 4。これにより、労働者は早い段階から介護に関する情報を得て、準備や計画を立てやすくなる。
- 介護のためのテレワーク導入の努力義務化: 要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主は必要な措置を講じる努力義務を負う 2。
2.2. 特定技能外国人労働者に対する義務的支援
2025年には、特定技能外国人労働者の受け入れに関する制度においても、義務的支援が重要な柱となる。
- 事前ガイダンスの義務化: 特定技能外国人労働者が入国する前に、日本での仕事内容、労働条件、生活環境などに関する事前ガイダンスを提供することが義務付けられている 17。これにより、外国人労働者は日本での生活や仕事に対する期待と現実のギャップを埋め、不安を軽減することができる。
- 継続的な義務的支援: 受け入れ機関または登録支援機関は、特定技能外国人労働者に対して、生活オリエンテーション、日本語学習の支援、住居の確保、医療機関への同行、行政手続きの支援など、多岐にわたる継続的な支援を提供することが義務付けられている 17。これらの支援は、外国人労働者が日本社会に円滑に適応し、安定して就労できるようサポートすることを目的としている。
- 定期的な面談と行政機関への通報義務: 支援担当者は、特定技能外国人労働者と定期的に面談を実施し、労働状況や生活状況を確認する必要がある 18。もし面談を通じて労働関連法規の違反が確認された場合、支援担当者は労働基準監督署やその他の関係行政機関へその旨を通報する義務を負う 18。この義務は、外国人労働者の権利保護と適正な労働環境の確保を目的としている。
2.3. 高齢者および障害者の雇用促進
2025年には、高齢者や障害者の雇用を促進するための義務も強化される。
- 65歳までの雇用確保の完全義務化: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、これまで経過措置が設けられていた65歳までの雇用確保が、2025年4月1日より全ての企業において完全義務化される 4。企業は、定年年齢の引き上げ、定年制の廃止、または65歳までの継続雇用制度(再雇用または勤務延長)のいずれかの措置を講じる必要がある 21。これは、高齢者の就労意欲に応え、労働力不足を緩和することを目的としている。
- 障害者雇用除外率の引き下げ: 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、2025年4月1日より、障害者雇用除外率が10%引き下げられる 4。これにより、これまで障害者雇用義務が一部免除されていた業種の企業も、より多くの障害者を雇用することが求められるようになる。これは、障害者の社会参加と自立を促進することを目的としている。
3. 2025年における定期面談の義務
2025年には、従業員の状況把握や支援を目的とした定期的な面談が、いくつかの分野で義務付けられる。
3.1. 育児・介護休業に関する個別面談
改正育児・介護休業法に基づき、育児や介護に関する様々な段階で、事業主による労働者との個別面談が義務付けられる。
- 妊娠・出産、育児に関する意向聴取: 労働者またはその配偶者からの妊娠・出産の申し出時、および子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取することが義務付けられる 3。また、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して柔軟な働き方に関する措置を周知する際にも、個別の意向確認が義務付けられる 3。これらの面談は、労働者のニーズを把握し、適切な支援策を検討するために重要となる。
- 介護に関する意向確認: 介護に直面した労働者から申し出があった場合、事業主は介護休業や介護両立支援制度の利用意向を個別に確認することが義務付けられる 2。また、40歳頃の労働者に対して介護に関する情報を提供する際にも、個別の意向確認が推奨される。
3.2. 特定技能外国人労働者との定期面談
特定技能外国人労働者の受け入れにおいては、支援担当者による定期的な面談が義務付けられている 18。
- 3ヶ月に1回以上の面談: 支援責任者または支援担当者は、特定技能外国人労働者と、その監督を行う立場にある者の両方と、少なくとも3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施する必要がある 19。面談は、外国人労働者が十分に理解できる言語で行われ、必要に応じて生活オリエンテーションで説明した内容を再確認する 19。オンラインでの面談も許可されている 23。支援担当者は中立的な立場で面談を行い、外国人労働者が問題を話しやすい環境を確保する必要がある 19。
- 面談内容: 面談では、労働契約通りの待遇で働いているか、不当な扱いを受けていないか、生活や健康で困っていることはないか、出入国や労働法関係法令違反がないかなどを確認し、必要に応じて相談や問題解決の支援を行う 19。
3.3. 医師による面接指導
特定の条件下では、医師による面接指導が義務付けられる。
- 研究開発業務従事者: 時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超える研究開発業務従事者に対しては、本人の申し出の有無にかかわらず、医師による面接指導を行わなければならない 26。
- 高度プロフェッショナル制度対象労働者: 1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその時間について、1ヶ月あたり100時間を超える高度プロフェッショナル制度対象労働者に対しても、本人の申し出の有無にかかわらず、医師による面接指導を行わなければならない 26。健康管理時間の超過時間が1ヶ月あたり100時間を超えない高度プロフェッショナル制度対象労働者については、本人の申し出により面接指導を行うことが努力義務とされている 26。
4. 2025年における行政機関への通報義務
2025年には、特定の状況下で行政機関への通報が義務付けられる制度が強化される。
4.1. 特定技能外国人に関する通報義務
特定技能外国人労働者の受け入れにおいては、労働関連法規の違反が確認された場合、行政機関への通報が義務付けられている 18。支援担当者は、定期的な面談などを通じて違反行為を発見した場合、速やかに労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報しなければならない 18。違反行為には、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの違反、許可を得ていない就労、パスポートや在留カードの取り上げなどが含まれる 19。
4.2. 公益通報者保護法の改正による通報義務の強化
公益通報者保護法は、2025年に改正が予定されており、事業者による内部通報制度の整備義務や、通報者保護の強化が図られる 27。
- 内部通報体制整備義務違反に対する罰則: 常時使用する労働者数が300人を超える事業者には、内部公益通報に対応する業務従事者を指定する義務があるが、改正により、この義務に違反し、消費者庁の勧告に従わない場合には、命令や立ち入り検査、さらには刑事罰が科される可能性が盛り込まれている 27。
- 公益通報者の探索行為の禁止: 正当な理由なく、労働者等に公益通報者である旨を明らかにすることを要求する行為など、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止される 27。
- 公益通報を妨害する行為の禁止: 正当な理由なく、労働者等に公益通報をしないことを約束させるなどの公益通報を妨害する行為が禁止され、これに反する契約締結等の法律行為は無効となる 30。
- 不利益な取扱い(解雇・懲戒)に対する罰則の強化: 公益通報をしたことを理由として、労働者に対して解雇や懲戒を行った場合、事業者だけでなく、その決定に関与した者に対しても刑事罰が科される 27。法人には3000万円以下の罰金、個人には6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性がある 27。また、解雇・懲戒に関する立証責任が事業者に転換される 30。
- 公務員への保護の明確化: 公務員に対しても、公益通報を理由とする不利益処分が明確に禁止され、通報を理由とする免職や懲戒処分の決定に関与した公務員に対しても刑事罰が導入される方針である 27。
4.3. その他行政機関への報告・通報義務
- 労働安全衛生法関係の電子申請義務化: 2025年1月1日より、労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告、ストレスチェック結果等報告など、労働安全衛生法関係の各種手続きが電子申請義務化される 22。
- 医療機関の機能に関する報告: 2025年4月より、医療機関は、自院の「かかりつけ医機能」に関する医療体制を都道府県に報告することが義務付けられる 35。
5. 企業への影響と推奨事項
2025年に施行されるこれらの義務的支援制度、定期面談の義務、行政機関への通報義務の強化は、企業経営に多岐にわたる影響を与えると考えられる。企業はこれらの変更点を十分に理解し、適切な対応を講じる必要がある。
- 管理業務の増加: 改正育児・介護休業法や特定技能外国人に関する報告義務の変更、公益通報者保護法の改正などにより、企業における管理業務は増加する可能性が高い。特に、特定技能外国人に関する年次報告の詳細化や、公益通報に関する体制整備と運用は、新たな負担となることが予想される。
- 社内規程の見直しと従業員への周知徹底: 各法改正に対応するため、就業規則や関連規程の見直しが不可欠となる。また、改正内容や新たな制度について、従業員への周知徹底を図る必要がある。研修や説明会などを実施し、従業員の理解を深めることが重要となる。
- 費用負担の増加: 柔軟な働き方を支援するための制度導入や、従業員へのサポート体制の強化、内部通報制度の整備などには、費用が発生する可能性がある。特に、テレワーク環境の整備や保育施設の設置・運営などは、企業にとって新たな投資となる場合がある。
- 従業員の意識改革と企業文化の醸成: 法改正への対応だけでなく、従業員のワークライフバランスに対する意識改革や、倫理的な企業文化の醸成も重要となる。管理職層を含めた全従業員が、新たな制度の趣旨を理解し、協力体制を築くことが、制度の実効性を高める上で不可欠である。
- 正確な記録管理の重要性: 特に特定技能外国人に関する報告義務においては、労働時間、賃金、支援状況など、詳細な記録管理が求められる。また、公益通報に関する記録も適切に管理する必要がある。
- コンプライアンス体制の強化: 公益通報者保護法の改正により、企業は内部通報制度の適切な運用と通報者保護を徹底する必要がある。違反行為に対する罰則も強化されるため、コンプライアンス体制の一層の強化が求められる。
企業は、これらの影響を踏まえ、以下の推奨事項を参考に、早めの準備と対応を進めることが望ましい。
- 法改正内容の正確な理解と情報収集: 厚生労働省や関係省庁のウェブサイト、専門家による解説などを参考に、改正内容を正確に理解し、必要な情報を収集する。
- 社内プロジェクトチームの設置: 法改正への対応を円滑に進めるため、人事、法務、労務などの関連部署が連携したプロジェクトチームを設置し、役割分担と責任者を明確にする。
- 就業規則および関連規程の見直しと改定: 法改正の内容に合わせて、就業規則や育児・介護休業規程、公益通報規程などを速やかに見直し、必要な改定を行う。
- 従業員への説明会や研修の実施: 改正された制度の内容や利用方法について、従業員向けの説明会や研修を実施し、理解を深める。特に、管理職層には、新たな制度の趣旨や適切な対応について十分な研修を行う。
- 相談窓口の設置と周知: 育児、介護、外国人労働者の支援、公益通報など、それぞれのテーマに対応した相談窓口を設置し、従業員にその存在と利用方法を周知する。
- 柔軟な働き方を支援する環境整備: テレワークの導入や拡充、短時間勤務制度の柔軟な運用、育児や介護と両立しやすい勤務体系の導入など、柔軟な働き方を支援する環境整備を検討する。
- 記録管理体制の強化: 特定技能外国人に関する詳細な記録管理体制を構築するとともに、公益通報に関する記録も適切に管理するための仕組みを整備する。
- 内部通報制度の実効性向上: 公益通報窓口の設置だけでなく、通報者の保護、調査の透明性、是正措置の実施など、内部通報制度全体の実効性を高めるための取り組みを行う。
- 専門家への相談: 法改正の内容や自社における具体的な対応について不明な点がある場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談する。
- 定期的な見直しと改善: 法改正への対応は一度きりではなく、制度の運用状況や従業員のニーズを踏まえ、定期的に見直しと改善を行うことが重要である。
6. 結論
2025年は、日本における労働法制や社会政策が大きく変化する年となる。企業は、これらの新たな義務を遵守し、従業員が安心して働き続けられる環境を整備することで、持続的な成長と企業価値の向上につなげることができる。そのためには、法改正の内容を正確に理解し、組織全体で適切に対応していくことが不可欠である。
表1: 改正育児・介護休業法の主な改正点(2025年)
| 項目 | 現状 | 2025年4月からの変更点 | 2025年10月からの変更点 | 義務/努力義務 |
| 子の看護休暇 | 小学校就学前の子 | 対象年齢を小学校3年生修了までに拡大。取得理由に学級閉鎖、入園・入学式、卒園式を追加。勤続6ヶ月未満の労働者の除外規定を撤廃。名称を「子の看護等休暇」に変更。 | 変更なし | 義務 |
| 所定外労働の免除 | 3歳に満たない子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者に拡大 | 変更なし | 義務 |
| 育児のためのテレワーク | 努力義務 | 変更なし | 変更なし | 努力義務 |
| 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方 | 特になし | 特になし | 以下のいずれか2つ以上の措置を実施する義務:始業時刻・終業時刻の変更、テレワーク(月10日以上)、短時間勤務制度、新たな休暇の付与(年間10日以上)、保育施設の設置・運営など | 義務 |
| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 | 特になし | 特になし | 労働者またはその配偶者からの妊娠・出産の申し出時や、子が3歳になるまでの適切な時期に、個別の意向を聴取し、必要な配慮を行う義務 | 義務 |
| 介護離職防止のための雇用環境整備 | 特になし | 研修の実施、相談体制の整備、利用事例の収集・提供、制度利用促進方針の周知などを義務化 | 変更なし | 義務 |
| 介護に直面した労働者に対する個別の周知・意向確認等 | 特になし | 介護休業制度等の内容、申請先、給付金などを個別に周知し、利用意向を確認する義務。40歳頃の労働者への情報提供も義務化。 | 変更なし | 義務 |
| 介護のためのテレワーク | 努力義務 | 変更なし | 変更なし | 努力義務 |
表2: 特定技能外国人に関する報告義務の変更点(2025年)
| 項目 | 現状 | 2025年4月からの変更点 |
| 定期報告 | 四半期ごと(年4回) | 年1回に変更。最初の年次報告は2026年5月31日提出(対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日)。最後の四半期報告は2025年1月~3月分で、2025年4月15日提出。 |
| 報告様式 | 「受入れ状況・活動状況に係る届出」と「支援実施状況に係る届出」の2種類 | 「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」の1種類に統合。報告項目や添付書類も変更。 |
| 随時届出 | 特定の事由が発生した場合に随時 | 就労開始後1ヶ月を経過しても就労を開始していない場合や、雇用後に1ヶ月活動できない事情が生じた場合も対象に追加。支援計画の実施困難な事由が生じた場合(特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含む)の報告が新たに必要。 |
表3: 改正公益通報者保護法の主な改正点(2025年)
| 項目 | 現状 | 2025年の改正点(予定) |
| 内部通報体制整備義務 | 常時使用する労働者数が300人を超える事業者に義務 | 義務違反に対する消費者庁の立ち入り検査権、勧告に従わない場合の命令権を規定。命令に従わない場合に刑事罰を科す。 |
| 公益通報者の探索行為 | 明示的な規定なし | 正当な理由のない探索行為を禁止する規定を新設(罰則は設けられない予定)。 |
| 公益通報の妨害行為 | 明示的な規定なし | 公益通報をしないことを約束させるなどの妨害行為を禁止し、これに反する契約等を無効とする規定を新設。 |
| 不利益な取扱い(解雇・懲戒) | 禁止されている | 公益通報を理由とする解雇・懲戒を行った事業者および意思決定に関与した個人に刑事罰を科す。法人には3000万円以下の罰金、個人には6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。解雇・懲戒に関する立証責任を事業者に転換(内部通報後1年以内)。 |
| 公務員の保護 | 地方公務員法、国家公務員法等に規定 | 公益通報を理由とする不利益処分を明確に禁止し、通報を理由とする免職・懲戒処分の決定に関与した公務員に刑事罰を導入する方針。 |
| 中小企業(労働者数300人以下) | 努力義務 | 努力義務 |
引用文献
- 【2025年施行】育児介護休業法改正のポイントをわかりやすく解説 – パソナ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.pasona.co.jp/clients/service/column/women/2025ikujikaigokyugyohou/
- 2025年4月に育児介護休業法が改正 その内容と企業への影響をわかりやすく解説, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/bizon/childcare-and-caregiving.html
- 【2025年4月・10月施行】改正育児・介護休業法の実務対応を解説!(育児編) ~ 厚生労働省の『Q&A』をもとに, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.human-tech.co.jp/column/2623/
- 2025年の人事関連 法改正まとめ | リクオプ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://recop.jp/laboratory/recruit_topics15/
- 【2025年4・10月】育児・介護休業法の改正ポイント!対応すべきことをわかりやすく解説 – HQ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://hq-hq.co.jp/articles/240412_041
- 2025年施行の「育児介護休業法等改正」のポイントを分かりやすく解説 – POSITIVE – 人事給与, 4月 3, 2025にアクセス、 https://hr.dentsusoken.com/column/1398/
- 2025年育児・介護休業法改正:6つのキーワードで分かりやすく解説 – 社長の顧問, 4月 3, 2025にアクセス、 https://shacho-no-komon.net/column/ikujikaigokyugyohou-2025
- 【2025年4月施行】育児・介護休業法の改正内容を解説!準備内容も紹介, 4月 3, 2025にアクセス、 https://freeway-timerecorder.com/blog/view/226
- 【2025年4月施行】育児・介護休業法の改正ポイントをわかりやすく解説, 4月 3, 2025にアクセス、 https://xn--alg-li9dki71toh.com/column/childcare-caregiver-leave-law-amendment/
- 【2025年】育児・介護休業法の改正をわかりやすく!必要な企業の対応も – ハマふれんど, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.hamafriend.jp/column/knowledge/the-act-on-child-care-and-family-care-leave.html
- 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 – 厚生労働省, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 人事・労務に関わる2025年(令和7年)施行の重要法改正まとめ – テンプスタッフ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.tempstaff.co.jp/client/hr-knowledge/11221.html
- 2025年4月から義務化!介護離職防止の措置, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.espayroll.jp/news/20241261
- 2025年4月に何が変わる?働き方関連の法改正と必要な対応を解説 – リコー, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.ricoh.co.jp/magazines/workstyle/column/kaisei2504/
- 人事・研修関連の担当者必見 2025年法改正情報 – GRONIA plus, 4月 3, 2025にアクセス、 https://all-e-support.jp/news/2025/
- 厚生労働省発表!令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&Aをわかりやすく解説【社労士監修/解説】 – HQ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://hq-hq.co.jp/articles/241204_138
- 義務的支援 事前ガイダンスに関する専門レポート – 謙虚なブログ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://blog.kenkyo.ai/2025/04/01/%E7%BE%A9%E5%8B%99%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8F%B4-%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/
- 「登録支援機関」の役割とは?義務的支援の内容や監理団体との違いを外国人雇用労務士が解説, 4月 3, 2025にアクセス、 https://japannesia.com/howto/support-organization/
- 【2024年最新】特定技能の定期面談は対面必須に!登録支援機関が解説 | 株式会社Funtoco, 4月 3, 2025にアクセス、 https://funtoco-inc.com/tokuteiginouteikimendan/
- 2025年の労務に関する主な法改正について – 一般社団法人中小企業労働保険協会, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.mks.or.jp/20250131/
- 【社労士監修】定年65歳の義務化はいつから?2025年の制度改正と企業の対応策 – エデンレッド, 4月 3, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/workstyle-reform/178/
- 【保存版】2025年の法改正一覧!今から準備すべき実務チェックリスト – 労務SEARCH, 4月 3, 2025にアクセス、 https://romsearch.officestation.jp/news/49129
- 【2025年4月改正】特定技能の定期報告が年1回に変更!新制度のポイントを解説 – noborder, 4月 3, 2025にアクセス、 https://noborder.cloud/nortification/column0034.html
- 【特定技能】特定技能外国人との定期面談とは?行う時期や報告書の作成方法まで解説!, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.smilevisa.jp/owned-media/tokuteiginou_teikimendan/
- 2025年4月開始!特定技能の定期届出が年1回に!?制度変更のポイントを解説! – YouTube, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=IaxsjgnBeXc
- 「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます – 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 – 厚生労働省, 4月 3, 2025にアクセス、 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001458531.pdf
- 政府が公益通報者保護法の改正案の骨子を示しました(2025年3月号 …, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/koueki/column/20253.html
- 新井消費者庁長官記者会見要旨(2025年1月9日(木)), 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.caa.go.jp/notice/statement/arai/040803.html
- 「改正公益通報者保護法」の施行に伴い人事労務担当者がとるべき“対策”とは。主な改正ポイントと具体的な対応策を解説 – HRプロ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2822
- 2025年は危機管理上の重要法案が審議される年!今からでも準備を!~通報者保護、情報セキュリティ、ハラスメント防止(カスハラ、就活等セクハラ)に関する重要ポイントを解説~ | 株式会社エス・ピー・ネットワーク, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.sp-network.co.jp/column-report/column/spneye/candr20115.html
- 公益通報者保護法と制度の概要 – 消費者庁, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview
- 公益通報者保護法 改正案を閣議決定 内部通報者への不利益な扱いに刑事罰(2025年3月4日), 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=x5zJe2Gieaw
- 公益通報者保護法の制度見直しの方向性 – RM NAVI, 4月 3, 2025にアクセス、 https://rm-navi.com/search/item/2044
- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号) – 東京弁護士会, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/koueki/column/post_25.html
- 2025年4月開始予定!かかりつけ医機能報告制度の目的とは, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.cb-p.co.jp/column/18590/
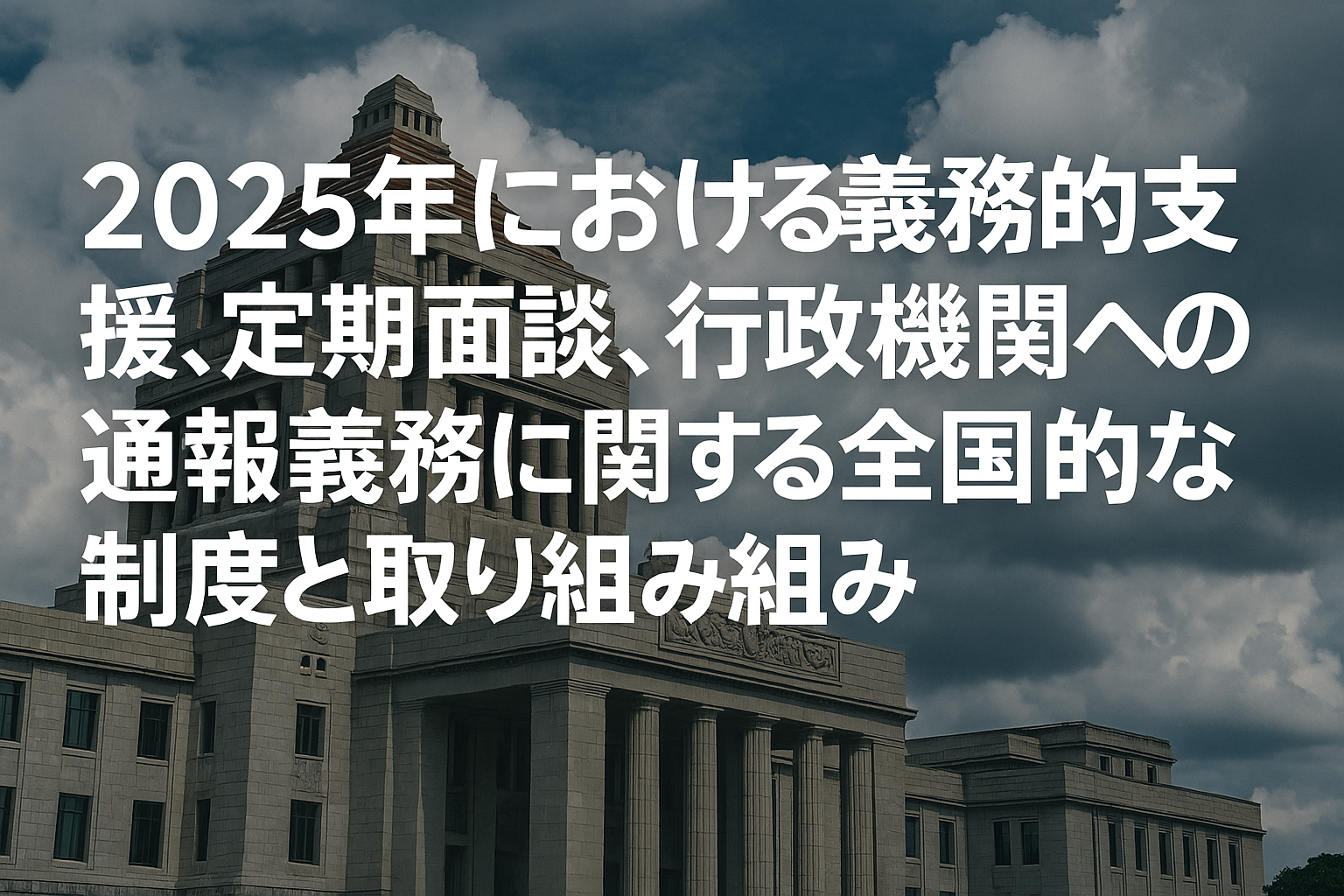




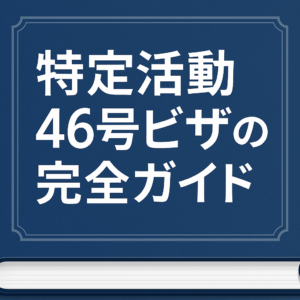
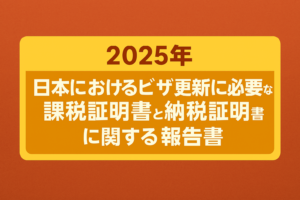

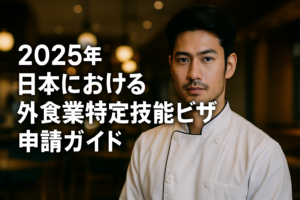

コメント