I. 概要
本報告書は、2025年に日本全国で実施される、日本人と日本に居住する外国人との交流促進を目的とした義務的な支援プログラムについて、その現状を分析したものである。調査の結果、外国人との交流促進を義務とする支援の主要な推進力は、特定技能外国人(以下、SSW)の在留資格に紐づく支援策であることが明らかになった。本報告書では、これらの義務的支援の根拠となる法制度、国および地方自治体による具体的な取り組み、非政府組織(NGO)や財団による貢献、そして2025年に予定される交流機会の具体例について詳述する。
II. はじめに
近年、日本における外国人居住者の数は増加傾向にあり、多文化共生社会の実現に向けた取り組みが重要性を増している。外国人居住者の社会統合を促進する上で、日本人との積極的な交流は不可欠な要素である。本報告書は、2025年において全国的に展開される、この日本人と外国人との交流を促進するための義務的な支援プログラムに焦点を当て、その詳細な内容、実施主体、および特徴を明らかにすることを目的とする。本報告書の分析範囲は、法律や政策によって義務付けられた支援策、特に特定の在留資格(例えばSSW)に関連するものを中心とする。本報告書は、提供された調査資料を詳細に検討し、関連情報を抽出、分析、および統合することによって作成された。
III. 交流促進を義務付ける法的および政策的枠組み
日本における外国人居住者の社会統合を支援する法的および政策的枠組みにおいて、日本人との交流促進は重要な要素として位置づけられている。特に、特定の在留資格を持つ外国人に対する支援策においては、交流促進が義務として明記されている。
特定技能外国人(SSW)ビザの重要な役割
提供された資料1から、SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する支援において、「日本人との交流促進」が義務的支援項目の一つとして明確に定められていることがわかる。
法務省の告示1によれば、SSW(i)の在留資格で雇用される外国人に対しては、受け入れ機関が労働、日常生活、社会統合のための支援計画を作成し、これに基づいた支援を提供することが義務付けられている。この支援計画には、10項目の義務的支援が含まれており、その一つに「日本人との交流促進」が挙げられている。このことは、日本政府が、特定の分野で労働する外国人にとって、日本人との社会的な繋がりを持つことが、円滑な日本での生活と社会参加に不可欠であると考えていることを示唆している。
受け入れ機関がこの義務的支援を自ら実施するだけでなく、登録支援機関に委託することも可能である1。この委託という仕組みは、必ずしも受け入れ機関が交流促進のための専門知識やリソースを持っているとは限らない現状を踏まえ、より専門的な機関による支援提供を可能にすることで、義務的支援の質の確保を図るものであると考えられる。
民間企業である株式会社キャリアリンクファクトリーのブログ記事2や、日本での生活情報を発信するJapannesiaのウェブサイト3においても、SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する義務的支援として「日本人との交流促進」が挙げられており、この義務が広く認識されていることが裏付けられる。キャリアリンクファクトリーの記事2では、具体的な支援内容として、地方公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流イベントに関する情報提供や参加手続きの補助、そして特定技能外国人が日本文化を理解するための地域行事への同行と必要に応じた案内などが例示されている。これらの具体例は、「日本人との交流促進」という抽象的な義務が、実際の支援現場においてどのような活動として展開されるべきかを示唆している。
また、2025年における登録支援機関の義務的支援に関するブログ記事4においても、「日本人との交流促進」が引き続き重要な支援項目として挙げられていることから、この義務は2025年においてもその重要性を維持し、継続的に実施されることが確認できる。
これらの情報から、SSW(i)ビザは、外国人との交流促進を義務付ける主要な法的根拠であり、その対象となる外国人労働者の社会統合を促進するための重要な政策的ツールであると言える。
IV. 国によるイニシアチブとガイドライン
日本政府は、外国人との交流促進を義務付ける法的枠組みに基づき、具体的なイニシアチブとガイドラインを提示している。特に、法務省出入国在留管理庁は、SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する支援において中心的な役割を果たしている。
出入国在留管理庁の役割
前述の通り1、出入国在留管理庁が定める「特定技能の運用に関する方針」およびその補足資料において、SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する10項目の義務的支援の一つとして「日本人との交流促進」が明記されている。このことは、国が特定の在留資格を持つ外国人に対して、社会的な繋がりを築く機会を提供することを強く求めていることを示している。
国による義務的交流支援は、主にSSW(i)の在留資格を持つ外国人労働者を対象としている1。これは、労働力不足が深刻な特定の産業分野における外国人労働者の受け入れを円滑に進め、彼らが日本社会に定着することを目的とした、政府の明確な政策的意図を示していると考えられる。
国のガイドラインは、交流促進を義務付けているものの、その具体的な実施方法については、受け入れ機関や登録支援機関の裁量に委ねられている部分が大きい1。これは、外国人労働者の背景や地域社会の状況が多様であることを考慮し、画一的なプログラムではなく、それぞれの状況に応じた柔軟な対応を可能にするためと考えられる。
間接的な交流支援としての言語および就労環境整備
株式会社マイナビグローバルが運営する外国人雇用支援サイトの情報5によれば、国は外国人雇用事業所に対して、日本語研修の開催や日本語学校への就学、就業環境の多言語化などを支援する補助金を提供している。これらの支援策は、直接的に日本人との交流を促進するものではないものの、外国人居住者の日本語能力の向上や、より快適な就労環境の整備を通じて、結果的に日本人とのコミュニケーションを円滑にし、交流を促進する間接的な効果が期待できる。日本語能力の向上は、外国人居住者が地域社会や職場で日本人と積極的に関わるための基礎となる。また、多言語化された就労環境は、外国人労働者の不安を軽減し、心理的な障壁を下げることで、日本人との自然なコミュニケーションを促す可能性がある。
V. 地方自治体による交流促進の取り組みと補助金
地方自治体も、地域に居住する外国人との交流を促進するために、独自のプログラムや補助金制度を設けている。これらの取り組みは、地域の特性や課題に合わせて、よりきめ細やかな支援を提供することを目的としている。
地方自治体の積極的な役割
株式会社マイナビグローバルが運営する外国人雇用支援サイトに掲載された2025年3月28日更新の記事5は、全国の地方自治体が外国人雇用の支援として様々な補助金や助成金を提供していることを示している。これらの多くは、外国人労働者の生活支援や定着支援を目的としており、その一環として日本人との交流を促進する活動も含まれていると考えられる。地方自治体による多様な支援策の存在は、外国人労働者が地域社会の一員として受け入れられ、共に生活していくことの重要性が、地域レベルでも広く認識されていることを示唆している。
義務的交流支援を間接的に支援する財政的インセンティブ
青森県五戸町や宮城県栗原市などの例5に見られるように、外国人介護人材の受け入れ支援や、外国人労働者を初めて雇用する事業者への支援策として、地域住民との交流会への参加支援や、交流イベントの開催費用への補助などが提供されている場合がある。これらの補助金は、受け入れ機関や事業者が義務的交流支援を実施する際の経済的な負担を軽減し、より積極的に交流機会を提供することを促す効果が期待できる。
石川県能登町5では、外国人労働者と地域住民との交流を促進することを目的とした補助金が提供されており、これは地方自治体が地域レベルでの異文化交流を積極的に推進しようとする具体的な事例と言える。
多文化共生に向けた地域主導の取り組み
神戸市が東灘区南部で実施する外国人との共生に向けた基盤づくり事業の公募6では、地域住民向けの学習会や多文化交流の場の開催、地域または外国人による共生に向けた活動の支援などが盛り込まれている。これは、地方自治体が主体となり、地域住民と外国人が共に学び、交流する機会を創出することで、相互理解を深め、共生社会の実現を目指す積極的な取り組みであると言える。
VI. 非政府組織(NGO)および財団による交流促進への貢献
NGOや財団も、多文化共生社会の実現に向けて、外国人との交流を促進する重要な役割を担っている。これらの組織は、政府や自治体の支援策を補完し、より柔軟で多様な活動を展開している。
政府主導の義務的支援を補完するNGOと財団の役割
一般財団法人ゆうちょ財団7は、多文化共生の推進に寄与する活動を行う民間団体に対して助成金を提供している。これらの助成金は、必ずしも義務的なプログラムではないものの、地域社会における外国人との交流を促進するNPOなどの活動を経済的に支援することで、結果的に義務的支援の効果を高めることに貢献していると考えられる。ゆうちょ財団による多文化共生推進活動への助成は、地域社会における異文化理解を深め、外国人住民と地域住民の間の相互交流を促進する様々な活動を支援しており、政府の義務的支援策を地域レベルで補完する重要な役割を果たしていると言える。
公益財団法人かめのり財団8も、多文化共生地域ネットワーク支援事業として、外国人住民が抱える課題の解決や、地域社会での相互理解に資する事業に対して助成を行っている。特に、保健や教育といった生活に密着した分野での外国人支援や、地域社会での相互理解を深める事業を優先的に支援しており、これらの活動は、外国人住民が地域社会に円滑に統合され、日本人住民との良好な関係を築く上で重要な基盤となる。
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)と公益財団法人中島記念国際交流財団11は、共同で留学生地域交流事業に対する助成を行っている。この事業は、外国人留学生と地域住民(留学生以外の外国人を含む)との相互理解を促進し、地域における国際交流を推進することを目的としている。大学や地方公共団体、NPO法人などが実施する、国際理解教育、留学生の生活支援体制整備、地域住民との交流促進、多様なネットワーク形成などを目的とした事業が助成対象となっており、これらの活動は、地域社会における国際交流の活性化に大きく貢献すると期待される。特に、外国人留学生は、地域社会との交流を通じて日本文化への理解を深め、地域住民は留学生との交流を通じて国際的な視野を広げることができるため、双方にとって有益な機会となる。
国際交流の担い手としての外国人留学生の活用
JASSOと中島記念国際交流財団による留学生地域交流事業11は、外国人留学生を地域社会との交流の 촉매剤(触媒)として活用する点で注目される。留学生は、自身の文化や言語を地域住民に紹介するだけでなく、地域社会の文化や習慣を学ぶことで、相互理解を深めることができる。このプログラムは、大学、地方公共団体、NPOなど、多様な主体による申請を可能としており、地域の実情に合わせた様々な交流事業の展開が期待される。
VII. 義務的交流支援の実践例
SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する義務的交流支援は、受け入れ機関や登録支援機関によって様々な形で実践されていると考えられる。以下に、その具体的な例を挙げる。
地域のお祭りへの参加促進
法務省のガイドライン1や民間企業のウェブサイト2で示唆されているように、受け入れ機関は、外国人労働者に対して地域の祭りに関する情報を提供し、参加に必要な手続きを支援したり、場合によっては祭りに同行して文化的な背景などを説明したりすることが考えられる。地域のお祭りは、日本の伝統文化に触れる良い機会であると同時に、地域住民との間で自然なコミュニケーションが生まれる場となり得る。祭りの準備や当日の活動を通じて、外国人労働者は地域社会の一員としての意識を高め、地域住民は外国人労働者との交流を通じて異文化への理解を深めることが期待される。
自治会活動への参加奨励
法務省のガイドライン1では、地域住民との交流の場として自治会活動が挙げられている。受け入れ機関は、外国人労働者に対して自治会の活動内容や連絡先などの情報を提供したり、自治会への紹介を行ったりすることが考えられる。自治会活動への参加は、地域に根ざした日常生活における日本人との交流を促進し、外国人労働者の地域社会への統合を深める上で重要な役割を果たすと考えられる。自治会は、地域住民の生活に密着した様々な活動を行っており、外国人労働者がこれらの活動に参加することで、地域住民との間でより深い人間関係を築くことができる。
地域イベントに関する情報提供と参加支援
キャリアリンクファクトリーの記事2では、地方公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流イベントに関する情報提供や参加手続きの補助が、義務的支援の内容として挙げられている。これは、外国人労働者が地域社会で開催される様々なイベントに参加するためのハードルを下げ、日本人との交流を促進することを目的としている。イベントの内容は、文化交流、スポーツ、趣味活動など多岐にわたることが考えられ、外国人労働者は自身の興味や関心に合わせてイベントを選択し、参加することで、地域住民との共通の話題を見つけやすく、交流を深めることができる。
VIII. 2025年における地域交流の機会
2025年には、日本各地で日本人と外国人との交流を促進する様々なイベントや取り組みが予定されている。これらの機会は、SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する義務的交流支援の実践の場となるとともに、より広範な外国人居住者と地域社会との繋がりを強化する上で重要な役割を果たすと考えられる。
大規模な国際交流イベント
株式会社YOLO JAPANが2025年1月12日に大阪で開催する「YOLO JAPAN FESTIVAL 2025」12は、日本で働く外国人を対象とした大規模な交流イベントであり、様々な文化体験やパフォーマンス、ワークショップなどを通じて、参加者間の交流を促進する。このような大規模なイベントは、多くの外国人居住者と日本人が集まる機会を提供し、異文化理解と相互交流を促進する上で貴重な場となる。
東京都豊島区の池袋西口公園では、2025年3月14日から16日にかけて「2025東京国際交流フェスティバル『華の春』in池袋」13が開催される予定である。このフェスティバルは、多文化共生をテーマに、様々な国や地域の文化、グルメ、伝統芸能、音楽パフォーマンスを紹介し、外国人と日本人の相互理解と友好を深めることを目的としている。地域に根ざした国際交流フェスティバルは、地域住民と外国人居住者が気軽に交流できる機会を提供し、多文化共生社会の実現に向けた意識を高める上で重要な役割を果たす。
多様な文化交流イベント
イベント情報サイトParty Animals JP14によると、2025年4月には池袋ベトナムフェスティバルやサルサストリートなど、特定の文化に焦点を当てたイベントが予定されている。これらのイベントは、特定の文化に関心を持つ日本人と外国人との間の交流を深める良い機会となる。
国際交流イベント情報サイトこくちーずプロ15にも、2025年4月を中心に、様々な国際交流イベントや交流会が掲載されており、地域やテーマごとに多様な交流の機会が提供されていることがわかる。これらの情報は、受け入れ機関や登録支援機関が、外国人労働者の興味や関心に合わせて交流機会を提供する上で役立つと考えられる。
地域に根ざした交流促進の試み
浜松市で開催される「2025まちむらリレーション市民交流会議」17は、都市部と中山間地域の交流を促進するイベントであるが、地域に居住する外国人も参加することで、地域住民との交流を深める機会となり得る。
大阪観光大学のプロジェクト18は、大阪府南部において、外国人留学生と地域住民との交流を促進することを目的としており、地域社会への国際的な視点の導入と、地域住民の国際交流への参加を促進する効果が期待される。
環瀬戸内海地域交流促進協議会19は、瀬戸内地域における経済、生活、文化の発展を目指し、様々な分野での交流を促進しており、外国人居住者も地域交流の輪に加わることで、地域社会への理解を深め、地域住民との繋がりを強化することが期待される。
日本行政学会20が2025年に開催するワークショップの中には、ダイバーシティの推進や関係人口の創出・拡大をテーマとしたものがあり、これらは地方自治体の職員を対象としているが、外国人住民とのより良い関係構築や地域社会への統合を促進するための知識や視点を提供し、結果的に地域における多文化共生を推進する基盤となると考えられる。
過去の支援事例21からは、地域に根ざした支援団体が、外国人コミュニティのニーズに応じた活動を通じて、長年にわたり交流促進に貢献してきたことがわかる。これらの団体の経験やノウハウは、今後の交流促進策を検討する上で貴重な示唆を与えると考えられる。
IX. 義務的交流支援プログラムの比較分析
2025年における義務的交流支援プログラムの中心は、SSW(i)の在留資格を持つ外国人に対する支援であり、その主な特徴を以下の表にまとめる。
表1:2025年における特定技能外国人(i)ビザ保持者に対する義務的交流支援
| 特徴 | 説明 | 根拠資料 | 実施主体 | 対象地域 | 対象者 |
| 法的根拠 | 出入国在留管理庁の「特定技能の運用に関する方針」において、「日本人との交流促進」が10項目の義務的支援の一つとして定められている。 | 1, B1 | 受け入れ機関(雇用主)、登録支援機関 | 全国 | 特定技能外国人(i)ビザ保持者 |
| 支援内容 | 地方公共団体やボランティア団体が主催する地域住民との交流イベントに関する情報提供、参加手続きの補助、日本文化理解のための地域行事への同行と必要に応じた案内など。 | 2 | 受け入れ機関、登録支援機関 | 全国 | 特定技能外国人(i)ビザ保持者 |
| 具体的な活動例 | 地域のお祭りに関する情報提供と参加支援(情報提供、交通手段の手配など)、自治会活動に関する情報提供と参加奨励、地域イベントに関する情報提供と参加支援(イベント情報の翻訳、文化的な背景の説明など)。 | 1 | 受け入れ機関、登録支援機関 | 全国 | 特定技能外国人(i)ビザ保持者 |
| 実施責任 | 原則として受け入れ機関(雇用主)が責任を負う。ただし、受け入れ機関は、支援計画全体(交流促進を含む)を政府が定める基準を満たす登録支援機関に委託することができる。 | B1 | 受け入れ機関、登録支援機関 | 全国 | 特定技能外国人(i)ビザ保持者 |
| 実施状況の確認とペナルティ | 受け入れ機関は、外国人労働者およびその監督者との定期的な面談(3ヶ月に1回以上)を実施し、労働基準法等の違反行為について行政機関への通報義務を負う。義務的支援が適切に実施されていない場合、受け入れ機関に対して指導や改善命令が出される可能性があり、悪質な場合には特定技能外国人の受け入れが認められなくなるなどのペナルティが科される場合がある2。 | 2 | 出入国在留管理庁 | 全国 | 特定技能外国人(i)ビザ保持者を受け入れる機関 |
この表から、2025年における義務的交流支援は、主にSSW(i)の在留資格を持つ外国人労働者を対象としており、その実施責任は雇用主である受け入れ機関にあるものの、登録支援機関への委託も可能であることがわかる。支援の内容は、地域社会との接点を持ち、日本文化への理解を深めるための情報提供や参加支援が中心となっている。
X. 結論
本報告書の分析結果から、2025年において日本における外国人との交流促進を目的とした義務的支援は、主に特定技能外国人(i)の在留資格を持つ労働者を対象として、国の政策として明確に位置づけられていることが明らかになった。国によるガイドラインは、受け入れ機関や登録支援機関に対して、地域社会との交流機会の提供や日本文化への理解を促す活動を義務付けている。また、地方自治体やNGO、財団も、独自の取り組みや補助金を通じて、この義務的支援を補完し、より広範な外国人居住者と地域社会との繋がりを強化する上で重要な役割を果たしている。2025年には、全国各地で多様な国際交流イベントが予定されており、これらは外国人居住者と地域住民が交流を深めるための貴重な機会を提供するものと期待される。
XI. 提言
政策立案者に向けて
- 特定技能外国人(i)以外の在留資格を持つ外国人に対しても、社会統合を促進するために、交流支援の義務化または推奨を検討すべきである。
- 受け入れ機関および登録支援機関向けに、より具体的で効果的な交流促進のための戦略やベストプラクティスに関する詳細なガイドラインを開発し、提供することを検討すべきである。
- 国は、地方自治体やNGOなどが実施する、地域レベルでの多様な交流促進イニシアチブに対する資金援助やサポートを強化すべきである。
実施機関(受け入れ機関および登録支援機関)に向けて
- 外国人労働者の多様な興味、文化的背景、および日本語能力に対応できるよう、幅広い交流機会を積極的に特定し、提供すべきである。
- 地域社会の団体、自治会、文化団体などとの連携を強化し、より本質的で有意義な交流体験を創出するべきである。
- 外国人労働者が交流活動に自信を持って参加できるよう、包括的な日本語学習支援と文化オリエンテーションプログラムを提供すべきである。
外国人居住者に向けて
- 雇用主や支援機関から提供される交流機会に積極的に参加し、地域社会との繋がりを築くための新たな機会を探求するべきである。
- 日本語学習リソースを積極的に活用し、日本人とのコミュニケーション能力を向上させるべきである。
- 日本の文化を体験し、異なる背景を持つ人々との関係を築くことに積極的に取り組むべきである。
引用文献
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html
- 特定技能外国人の受け入れに必要な義務的支援と実施方法や要件を …, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.careerlinkfactory.co.jp/blog/specific-skills-compulsory-support/
- 「登録支援機関」の役割とは?義務的支援の内容や監理団体との違いを外国人雇用労務士が解説, 4月 3, 2025にアクセス、 https://japannesia.com/howto/support-organization/
- 2025年における登録支援機関の義務的支援と任意的支援に関する全国調査報告書, 4月 3, 2025にアクセス、 https://blog.kenkyo.ai/2025/04/01/2025%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%A8%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%9A%84/
- 【2025年3月28日更新】外国人雇用の助成金・補助金を活用しよう!自治体ごとに一覧で紹介, 4月 3, 2025にアクセス、 https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/469
- 2025年度東灘区における外国人との共生促進に関する業務【事業者募集】 – 神戸市, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.city.kobe.lg.jp/a78534/chiikikyousei/tsunagarisokushin.html
- 2025年度多文化共生推進活動・NGO海外援助活動助成募集 – 国際協力NGOセンター JANIC, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.janic.org/information_post/2025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%A4%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E5%85%B1%E7%94%9F%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%83%BBngo%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%8A%A9%E6%88%90%E5%8B%9F/
- 【受付終了】2025年度 多文化共生地域ネットワーク支援事業 事業助成 – かめのり財団, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.kamenori.jp/grant2024/
- 多文化共生地域ネットワーク支援事業 2025年度事業助成 オンライン説明会 – 助成財団センター, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.jfc.or.jp/grant/mnews250106-002/
- 2025年度 多文化共生地域ネットワーク支援事業助成 – 助成財団センター, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.jfc.or.jp/subsidy/grants241210-001-2/
- 公益財団法人中島記念国際交流財団助成による2025年度留学生地域交流事業の募集について | JASSO, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryujigyou/boshu2025.html
- 【入場無料】日本全国で働く外国人のための交流イベント『YOLO JAPAN FESTIVAL 2025』 1/12(日)開催! – PR TIMES, 4月 3, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000015950.html
- 2025東京国際交流フェスティバル「華の春」in池袋|3月14日(金)〜16日(日)池袋西口公園で開催!異文化が彩る3日間の祭典 | 池袋イベント&フェス情報, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.ikebukuropark.info/tokyo-international-festival-2025/
- パーティアニマルズ 〜 国際交流 イベント情報館 〜, 4月 3, 2025にアクセス、 https://partyanimalsjp.com/
- 外国人交流イベント特集 – こくちーずプロ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.kokuchpro.com/feature/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%BA%A4%E6%B5%81/
- 国際交流イベント特集 – こくちーずプロ, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.kokuchpro.com/feature/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81/
- 2025まちむらリレーション市民交流会議 – 浜松市, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminkyodo/event/machimura-rireisyon.html
- 多文化共生を目指した地域交流プロジェクト – TEAM EXPO 2025 – 大阪・関西万博, 4月 3, 2025にアクセス、 https://team.expo2025.or.jp/ja/challenge/C10233
- TOKUSHIMA FUTURE EXPO 2025 – 環瀬戸内海地域交流促進協議会, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.kanseto.jp/article/b_to07/index.html
- 海外研修 – 研修のご案内 | JIAM 全国市町村国際文化研修所, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.jiam.jp/workshop/list.html?y=2025
- 『若者がつくるこれからの多文化共生』かめのりフォーラム2025ゲストスピーチ 一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事 田村太郎氏, 4月 3, 2025にアクセス、 https://www.kamenori.jp/guestspeech2025/





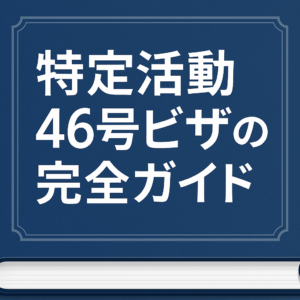
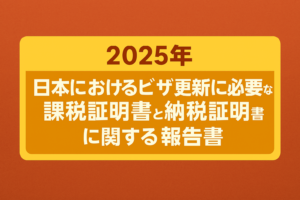

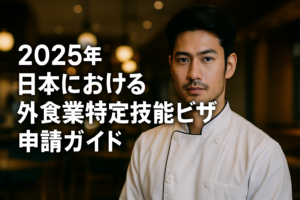
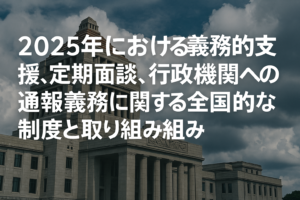
コメント