はじめに:2025年、日本で「自分で考えて動ける人」が超重要になるワケ
今の日本は、子供が少なくなって働く人が減ったり(少子高齢化)、世界とどんどん繋がったり(グローバル化)、新しい技術がものすごいスピードで出てきたり(技術革新)と、色々な変化が一気に起こっています。[1] こういう変化は、会社のやり方や国の仕組みにも大きな影響を与えています。
特に「2025年の崖」って聞いたことありますか?これは、デジタル化(DX)が遅れると、日本の経済が大きなピンチになるかも、という話です。それから、団塊の世代というたくさんの人が75歳以上になって、病院やお世話(医療・介護)がすごく必要になる「2025年問題」も迫っています。[2] こういう状況で、今までの働き方や人の育て方だけでは、もう追いつかなくなってきているんです。[1]
じゃあどうすればいいの? そのカギを握るのが、「自分で考えて動ける人(自律型人材)」を育てて、活躍してもらうことです。
「自分で考えて動ける人」は、ただ言われたことをやるだけじゃなくて、自分で「どうすればいいかな?」と考えて、新しいことを始めたり、仕事をもっとうまくできるようにしたり、変化に対応したりできる人のことです。2025年という変わり目の年に、こういう人がたくさんいることが、会社にとっても、日本全体にとっても、成長していくために絶対に必要なことなんです。[3, 4]
つまり、これからは、ただ働ける人がいればいい、というわけじゃなくて、「どんな風に働けるか」という仕事の「質」がすごく大事になってきます。言われたことだけやる人から、自分で問題を見つけて、解決方法を考えて、新しいことをどんどん進められる人へ。働く人が減っている[1]のも問題だけど、それ以上に、AIとかデジタル化[2]で簡単な仕事は機械がやってくれるようになって、もっと頭を使う仕事が増えているから、「自分で考えて動ける人」がますます重要になっているんです。
「2025年問題」は、今までの働き方や人の扱い方を根本から見直すきっかけになっていて、結果的に「自分で考えて動ける人」への期待をどんどん高めています。デジタル化が遅れるとヤバい![2]という危機感が、会社に「変わらなきゃ!」と思わせているんですね。新しい技術をうまく使うには、変化に対応して、自分で新しいことをどんどん学んで使える人が必要です。これって、まさに「自分で考えて動ける人」の特徴なんです。
ポイント: 日本は今、大変革の時代! 2025年に向けて、言われたことだけじゃなく、「自分で考えて動ける人」が会社や日本の未来を明るくするカギになる!
「自分で考えて動ける人」って、具体的にどんな人?
「自分で考えて動ける人(自律型人材)」って、一体どんな人のことを言うんでしょうか?
「自律」って「自分で自分をコントロールできる」こと
「自分で考えて動ける人」とは、上司や周りの人に「こうして」と言われるのを待つんじゃなくて、自分で考えて、判断して、会社やチームの目標を達成するために、自分から進んで行動できる人のことです。[7]
大事なのは、「自律(じりつ)」と「自立(じりつ)」の違い。音が同じでややこしいけど、意味が違います。「自立」は、ただ一人で仕事ができる、っていう意味。でも「自律」は、もっと深く、自分で自分をコントロールして(自己規律)、目標に向かって行動する、という意味なんです。会社全体の目標を達成するために、自分も責任を持つ、という気持ちも含まれています。[7]
色々な人が定義しているけど、みんな「自分から進んでやる気持ち(主体性)」を大事にしているのは同じです。[6]
主な特徴はこれ!
「自分で考えて動ける人」には、こんな特徴があります。
- 自分から動ける力(主体性): 会社の目標を理解した上で、「自分は何をすべきか」を自分で考えて、自分の意思で行動して、その結果に責任を持つこと。[6]
- 強い責任感: 自分で考えて行動するから、その行動には責任が伴います。いつでも上司に判断を求めるんじゃなくて、自分の行動と結果にちゃんと向き合って、もし失敗しても、それを受け止めてどうすればいいか考える力。[6]
- ずっと学び続ける気持ち(継続的な学習と成長マインドセット): もっと成長したい!という気持ちがあって、いつも新しい知識やスキルを身につけて、変化に対応し続けようとすること。[3]
- 自分の強みを活かす(自分らしさを仕事に活かす): 自分の得意なことや強みをよく知っていて、それを仕事や自分の将来設計にうまく使う力。[6]
2025年に特に必要なスキルは?
2025年、こんなスキルを持っていると、「自分で考えて動ける人」として活躍できます。
- 問題を解決する力・ちゃんと考える力(問題解決能力・批判的思考力): 複雑な状況を分析して、本当の問題点を見つけて、うまく解決する方法を考えて実行する力。[6] 実際、将来は「問題を見つける力」「未来を予測する力」「新しいことを生み出す力」がもっと大事になると言われています。[9]
- デジタルを使いこなす力・新しい技術に対応する力(デジタルリテラシー・技術適応力): パソコンやスマホ、色々なアプリをうまく使って、新しい技術もどんどん取り入れて、会社のデジタル化に貢献する力。[5]
- 話す力・協力する力(コミュニケーション能力・協調性): 色々な考えを持つチームの人たちや関係者と、うまく意思疎通して、みんなで協力して成果を出す力。[1]
- 自分を管理する力・目標に向かう力(自己管理能力・目標志向): 自分の時間や仕事の進み具合をちゃんと管理して、決めた目標を達成するために計画的に行動する力。[3]
【「自立」より「自律」が大事なワケ】
会社が求める人物像が変わってきているんです。昔は「言われたことをちゃんとできる人(自立した人)」が求められていたけど、今は「会社全体のことを考えて、そのために自分で判断して貢献できる人(自律した人)」が求められるようになってきました。変化が激しい時代だからこそ、一人ひとりがもっと広い視野で会社に貢献することが期待されているんですね。[6]
【特定の知識より「学び続ける力」】
2025年に必要なスキルを見ると、特定の専門知識よりも、「新しいことを学ぶ力」や「変化に対応する力」、「問題を解決する力」といった、どんな仕事にも通じる基本的な力が重視されているのが分かります。新しい技術はどんどん出てくる[5]から、特定の知識だけだと古くなっちゃう。だから、むしろ新しいことを自分で学び続けて、知らない状況にも対応できる力の方が、長く価値を生み出すためには大事なんです。「自分で考えて動ける人」の定義に「学び続けること」[3]が必ず入っているのも、こういう理由からです。
ポイント: 「自分で考えて動ける人」は、指示待ちじゃなく、自分で考えて責任を持って行動し、学び続ける人。問題解決力やデジタル対応力、コミュニケーション力も必須!
なぜ日本は「自分で考えて動ける人」がこんなに必要なの?(2025年に注目!)
日本がこれから成長していくために、「自分で考えて動ける人」がなぜこんなにも重要なのか、その理由を見ていきましょう。
- 働く人が減っている!(人口動態の変化と労働力人口の縮小): 日本は子供が少なくてお年寄りが増えているから、働く世代の人がどんどん減っています。[1] 例えば、看護師さんだけでも2025年には約200万人が必要と言われていて、多くの大事な仕事で人手不足が心配されています。[11] こういう状況だと、一人ひとりがもっと多くの価値を生み出さないといけません。だから、自分で考えて行動して、もっと効率よく、新しいことを生み出せる「自分で考えて動ける人」が、会社の生き残りのカギになるんです。
- AIとかデジタル化で仕事が変わる!(技術的破壊と仕事の性質の変化): AIやロボット、デジタル化(DX)といった新しい技術が、仕事のやり方や内容を根本から変えようとしています。[5] 今まで人がやっていた単純作業は機械がやってくれるようになる一方で、複雑な問題を解決したり、新しいアイデアを考えたり、計画を立てたりするような、まさに「自分で考えて動ける人」が得意とする、もっと頭を使う仕事が大事になってきています。経済産業省が心配している「2025年の崖」[2]は、デジタル化が遅れると日本の経済がヤバいよ、という警告。この変化を自分から進めて、対応できる人が急いで必要とされているんです。会社の人たちも、6割が「デジタル化でうちのビジネスは変わる!」と思っていて、AIが2025年までに大きな変化を起こす一番の原因だと考えているみたいです。[13] 日本でも、事務や工場などの仕事が減って、専門的な仕事や、人に対するサービス業などが増える「仕事の二極化」が起きているようです。[5]
- 会社の雇い方が変わる!(雇用モデルの進化と専門的・自律的役割の台頭): 「会社に入ったら一生安泰」とか「年を取れば給料が上がる」みたいな、昔ながらの日本の会社の仕組みは、もう限界が見えています。[1] 会社はもっと柔軟で、成果を重視する、専門的なスキルを持った人を大事にする「ジョブ型雇用」という雇い方を考え始めています。[12] こういう変化は、自分の将来設計を自分で考えて、専門的なスキルを磨いて、もっと自由に仕事に取り組める人に有利に働きます。[7]
- 「2025年問題」を乗り越えるには新しいアイデアが必要!(イノベーションへの緊急性): デジタル化の遅れだけじゃなく、お年寄りが増えて病院やお世話が大変になる[11]など、色々な問題が重なる「2025年問題」。これを解決するには、今までのやり方にとらわれない新しいアイデア(イノベーション)が絶対に必要です。「自分で考えて動ける人」は、自分から問題を見つけて解決する力や、枠にとらわれない発想力で、こういう難しい社会や経済の問題に対する新しい答えを生み出す力になると期待されています。「自分で新しい働き方や生き方を見つけられる人を育てることがすごく期待される」[1]という言葉は、この期待の大きさを表しています。
これらの理由は、お互いに関係しあって、「自分で考えて動ける人」への期待をどんどん大きくしています。人が減る→技術で解決しようとする→新しい技術を使いこなせる、変化に対応できる「自分で考えて動ける人」が必要になる→そういう人を引きつけて活かすために、会社は新しい雇い方(ジョブ型とか)を考える→新しい雇い方は「自分で考えて動ける人」が前提なので、ますますそういう人が必要になる…という、ぐるぐる回るサイクルになっているんです。
【会社の文化も変わらないと!】
「自分で考えて動ける人」が活躍するためには、会社の文化も変わる必要があります。自分で考えて行動する[6]っていうのは、昔ながらの「上司の言うことは絶対!」みたいな文化とは合いません。「自分で考えて動ける人」を育てて、その力を最大限に活かすためには、失敗を恐れずにチャレンジできて、社員が自分で考えて行動する権限があって、お互いを信頼できるような、もっとオープンで、社員一人ひとりの力を信じる文化に変えていく必要があるんです。[3] 上司とか役職とか関係なく、みんなが役割に基づいて動くような、フラットな組織も注目されています。[7] これは、単に研修をやるだけじゃなくて、会社の根本的なあり方を変える必要がある、ということですね。
【みんなが「自分で考えて動ける人」になれる?】
「仕事の二極化」[5]という話がありましたが、これは「自分で考えて動ける人(高いスキルを持つ人)」はますます必要とされるけど、変化に対応できない人は仕事が減っちゃうかも、という心配も含まれています。だから、会社が人を育てるだけでなく、社会全体でみんなが新しいことを学べる機会(リスキリング)[18]を作ったり、仕事がなくなった時のサポートをしっかりしたりすることも大事になってきます。これは、会社だけの問題じゃなくて、社会全体の問題なんですね。
ポイント: 働く人が減り、仕事内容も変わり、会社の仕組みも変わる大変革の時代だからこそ、「自分で考えて動ける人」が日本の未来を救うヒーローになる!そのためには会社の文化も変わる必要がある。
どうすれば「自分で考えて動ける人」になれる? 育てられる?
会社ができること:人を育てる環境づくり
- チャレンジできる文化を作る: 社員が自分から行動して、新しいことに挑戦して、もし失敗しても怒られるんじゃなくてそこから学べる、そんな安心できる雰囲気(心理的安全性)を作ることがめちゃくちゃ大事。[3] みんなが自由に意見を言えて、色々な考えを尊重する風土づくりも大切。そして、勉強を一回やって終わりじゃなくて、毎日の仕事の中でずっと学び続けることを応援する文化を作ることも重要です。[6]
- 会社の仕組みを変える: 仕事の役割や責任、必要なスキルをはっきりさせて、社員が自分で「何を勉強すればいいか」計画を立てやすくする「ジョブ型雇用」を進めるのがおすすめ。[12] それから、会社の中で色々な仕事を経験できるチャンスを作ったり、自分で希望する部署に行ける制度(社内公募)を作ったりするのも、自分で将来を考える力を育てるのに役立ちます。[14] 特に、デジタルスキルとか、将来必要になる力を身につけるための研修(リスキリング、アップスキリング)にお金をかけることは絶対に必要。[14]
- 一人ひとりの成長を応援する: 社員が「自分はこうなりたい」と自分で考えて、そのために努力する「キャリア自律」を応援することが、今の会社には求められています。[6] 上司と部下が定期的に1対1で話す時間(1on1ミーティング)を作って、将来の目標や、今困っていること、これから何を勉強したいかなどを話し合うのは、すごく良い方法です。[3] それ以外にも、インターネットで学べるeラーニング、みんなで学ぶワークショップ、会社の外の研修、会社の中の大学みたいなものなど、色々な学ぶ機会を用意して、実際にやってみる経験を積ませることも、「自分で考えて動ける人」を育てるのに役立ちます。[6]
▼日本の会社はどうしてる? 具体的な例▼
| 会社名(例) | どんな取り組みをしてる? | 何を目指してる? | 成果は?(分かっているもの) |
|---|---|---|---|
| 旭化成 | 新しいことを学ぶ支援「CLAP」、デジタル技術の資格、自分で部署を選べる制度、自分で勉強するのを応援する制度など。 | 社員が自分で将来を考えて成長するのを助ける、デジタルに強い人を育てる。 | デジタル専門家:2024年度末2,500人目標。自分で部署を選んで移った人:累計約500人。[22] |
| ソニーグループ | ベテラン社員が新しいことに挑戦するのを応援、会社の中の大学「ソニーユニバーシティ」など。 | ベテラン社員のやる気を引き出す、将来のリーダーを育てる、社員が自分で将来を考えるのを助ける。 | ソニーユニバーシティ参加者:累計約1,400人。[14] |
| 富士通 | 新しいアイデアを生み出すプログラム、世界で活躍できるエンジニアの資格、新しいことを学ぶ研修、自分で部署を選べる制度など。 | 社員の成長を助ける、自分で将来を考えるのを助ける、デジタルに強い人を育てる。 | 自分で部署を選んで移った人:3年で累計約7,200人。[23] |
| KDDI | 仕事の役割をはっきりさせる制度、会社の中のデジタル大学「KDDI DX University」、月1回の1on1、半年に1回の将来相談、自分で部署を選べる制度など。 | 自分で将来を考えるのを促す、デジタルに強い人を育てる。 | KDDI DX Universityはいつも満員になる人気。[20] |
| 大日本印刷(DNP) | 新入社員研修(自分で考えて行動する力を育てる、みんなで話し合う、実際にやってみる)。 | 新入社員が指示待ちじゃなく、自分で考えて行動できるようにする。 | 研修後のアンケートで満足度が高い。[31] |
| AGC | 管理職向けデジタル研修、データ分析家育成、工場の人向けデータ活用研修など、色々なレベルのデジタル人材育成。 | 社員みんなでデジタル化を進める、デジタルも仕事もできる「二刀流」人材を育てる。 | 2025年までにスゴ腕データ分析家100人目標。[23] |
| カインズ | 「DIY HR®」という考え方で、自分で将来を選んだり学んだりするのを応援する仕組み、自分で部署を選べる制度、学ぶためのプラットフォームなど。 | 自分で考えて動ける組織に変える、社員が自分で将来や学びを考えるのを助ける。 | – [26] |
| JTBグループ | 会社の中の大学「JTBユニバーシティ」(色々な学び方とたくさんの内容)。 | 旅行業界の発展に貢献する「自分で考えて新しいことを創り出せる社員」を育てる。 | – [26] |
| ソフトバンクグループ | 社員みんながAIの基礎を学べるeラーニング「AI Campus」、自分で手を挙げて参加する社内大学講座。 | AIを使えるようにする、デジタル専門家を育てる、自分で将来を考えるのを助ける。 | – [14] |
| 日本ガイシ | デジタル人材育成プログラム「NGK Data Science Academy」(会社の中で留学するみたいな制度)、レベル別のデジタル人材育成。 | デジタル人材、データ活用人材を育てる。 | 2030年までにデータ活用できる人1000人(国内社員の2割)、そのうちDXリーダー110人目標。[14] |
| オリンパス | 役職ごとの研修は原則やめて(2022年度~)、自分で手を挙げてスキルを身につける研修に変わった。 | 社員が自分から進んで学ぶのを促す、自分で学ぶ機会を提供する。 | – [20] |
国や学校ができること
- 国ができること:新しいことを学ぶのを応援する政策: 国は、新しい仕事のニーズに合わせて、働く人みんなが新しいスキルを身につけられるように(リスキリング、アップスキリング)、研修プログラムを作ったり、お金の面で助けたり、仕事を変わりやすくするためのサポートをしたりしています。[5, 12, 32]
- 学校ができること:自分で考える力の基礎を育てる: 小学校から大学までの学校は、自分で考える力、問題を解決する力、新しいことを思いつく力といった、自分で考えて動くための基本的な力を育てることに、もっと力を入れる必要があります。[1] そして、一生学び続ける気持ちを小さい頃から育てることも大事です。
一人ひとりができること:自分で成長する気持ちを持つ
- 「成長できる!」と信じる気持ち(成長マインドセット): 自分の能力は努力すればもっと伸びる!と信じること。[8] 新しいことに挑戦したり、失敗から学んだり、他の人の成功から刺激を受けたりする姿勢が大事。
- 自分の将来は自分で決める!(主体性と個人的な責任): 自分の将来設計に自分で責任を持って、会社からの指示を待つんじゃなくて、自分から進んでスキルアップの機会を探して行動することが求められます。[3]
- 自分を知って計画を立てる: 今までどんな仕事をしてきたか振り返って自分のスキルを整理したり、将来どうなりたいか目標を立てて計画したりすることが、自分で将来を考える意識を持つために役立ちます。[19]
【みんなで協力しないと!】
「自分で考えて動ける人」が育つかどうかは、会社(育てる環境を作る)、国・学校(応援する政策や基礎教育)、そして一人ひとり(自分から頑張る気持ち)の3者が協力して、それぞれの役割をちゃんと果たすかにかかっています。どれか一つが欠けても、うまくいかないかもしれません。
【「自分の将来は自分で決める」って大変?】
「キャリア自律」を大事にする、というのは、昔ながらの「会社にお任せ」という日本の働き方から大きく変わることを意味します。これは、一人ひとりが、自分を客観的に見て、目標を立てて、人と繋がる、といった新しいスキルと、自分の将来に対する大きな責任とチャンスを持つことになる、ということです。多くの日本人にとっては、意識を大きく変える必要があるかもしれません。
【「ジョブ型雇用」は会社にとってもチャレンジ】
「ジョブ型雇用」という、仕事の役割をはっきりさせる雇い方は、個人の「自分で考えて動く力」を助ける一方で、会社には「どんなスキルが必要で、どんな成果を期待するか」をもっと分かりやすく示すことを求めます。これは、今までの日本の会社のやり方に慣れている組織にとっては、仕事内容を分析したり、決めたり、伝えたりする面で、大きな変化と努力が必要なチャレンジになります。
ポイント: 会社はチャレンジできる文化と学ぶ機会を作り、国や学校はそれを応援し、一人ひとりは「成長するぞ!」という気持ちで自分から学ぶことが大事。みんなで協力して「自分で考えて動ける人」を育てよう!
「自分で考えて動ける人」を育てるのは難しい? 注意点と対策
「自分で考えて動ける人」を育てるのは、良いことばかりではありません。時間もお金もかかるし、ちょっとした落とし穴もあります。
- 時間もお金もかかるし、簡単じゃない: 「自分で考えて動ける人」を育てるのは、すぐにはできません。長い目で見て、ずっとお金や時間をかけていく必要があります。[7] 研修したり、相談に乗ったり、良い環境を整えたりするには、それなりにお金も時間もかかります。それに、人によって成長のスピードも違うから、みんな同じやり方ではうまくいかない、という難しさもあります。[33]
- 育てた人が辞めちゃうかも?(離職リスク): すごいスキルと「自分で考えて動ける力」を身につけた社員は、もし今の会社で「もっと成長できないな」「自由にやらせてもらえないな」と感じたら、もっと魅力的な他の会社に移ったり、自分で会社を作っちゃったりするかもしれません。[34]
- チームがバラバラになるかも?(チームの混乱): 自分ですごく考えて動ける人が、自分の判断ややり方ばかりを優先しすぎると、チームの中での情報共有やコミュニケーションがうまくいかなくなって、協力する雰囲気が壊れちゃうことも。[7] 自分だけが良ければいい、みたいになっちゃう可能性も。[36]
- みんなが変化に対応できるわけじゃない(個人の適応性): 社員みんなが、自分で考えてどんどんやる働き方にすぐに慣れるわけではありません。中には、もっと具体的に指示してほしい人や、ずっと頑張り続けるのが難しい人もいるでしょう。[34]
- 「やりがい」でタダ働きさせないで!(倫理的配慮と「やりがい搾取」): 「自分で考えて動ける人」は、やる気があって自分からどんどんやるけど、会社がそれを悪用して、「やりがいがあるから」と言って、不当に長い時間働かせたり、安い給料で済ませたりする「やりがい搾取」は絶対ダメ![37] 十分なサポートや正当な評価なしに、個人に責任だけを押し付けることにならないように、会社は気をつけないといけません。[36]
▼主な課題とどうすればいいか?▼
| 課題 | 説明 | どうすればいいか?(対策例) |
|---|---|---|
| 育成の時間とコスト | 長い目で見て、ずっとお金と時間をかける必要あり。人によって成長も違う。 | 会社として「人を育てるぞ!」と本気で決める。目先の利益だけでなく長い目で見る。色々な学び方を用意する。一人ひとりに合った育て方を考える。 |
| 育てた人が辞めちゃうリスク | スキルアップした人が、もっと良い条件の会社に行っちゃうかも。 | 魅力的な給料。やりがいのある仕事や成長できるチャンスを与える。会社の中でも色々な仕事に挑戦できるようにする。社員が会社を好きになるようにする。 |
| チーム運営への支障 | 自分で考えて動ける人が増えすぎると、チームがまとまらなくなるかも。 | コミュニケーションのルールをはっきり決める。チームワークを大事にする。協力することの大切さを伝える。情報共有しやすくする。 |
| 変化についていけない人が出るかも | みんなが自分でどんどんやる働き方に慣れるわけじゃない。 | 色々なキャリアの道を用意する(出世だけが全てじゃない)。「自分で将来を考えるって大事だよ」と丁寧に話し合う。一人ひとりの考えを尊重する。必要なサポートをする。 |
| 「やりがい搾取」(倫理的な問題) | 「やりがい」を言い訳に、タダ働きさせたり、責任だけ押し付けたりするリスク。 | 給料や評価のルールをはっきりさせる。法律を守る。働きすぎを防ぐ。仕事とプライベートのバランスを応援する。経営者や管理職の意識を変える。相談できる窓口を作る。 |
| 管理職が分かってない | 上司が「自分で考えて動ける人」の大切さを理解せず、昔ながらの指示命令ばかりだと、育つものも育たない。 | 上司向けの研修(部下のやる気を引き出す方法、相談に乗る方法、将来を応援する方法など)。「部下を育てること」も上司の評価に入れる。お手本になる上司を示す。 |
【会社選びも重要に?】
「自分で考えて動ける人」を育てることは、良い人材を引きつける魅力になる一方で、ちゃんと育ててくれない会社からは人が離れていってしまう原因にもなります。これは、会社の間での人材獲得競争を激しくして、進んでいる会社とそうでない会社との差を広げるかもしれません。「自分で考えて動ける人」は成長や挑戦、自由を求める[6]ので、会社がそういうものを提供できないと、せっかく育てた人も簡単に出て行ってしまうでしょう。[34]
【「やりがい」と「搾取」は紙一重?】
「やりがい搾取」の問題は、「やる気」や「目標」をどう引き出して育てるか、そしてそれを不当な働かせ方に利用しないように、どうバランスを取るか、という会社にとってすごく大事な課題です。「自分で考えて動ける人」は、強い目標や達成感で頑張ることが多い[3]けど、「やりがい搾取」はまさにその気持ちを悪用する行為[37]です。だから、会社は社員の頑張りをちゃんと評価して、給料や福利厚生をしっかりする仕組みを作らないといけません。
【変化についていけないのは個人のせいだけじゃないかも】
一部の社員が「自分で考えて動くなんて無理…」と感じるのは、必ずしもその人だけの問題じゃなくて、会社のサポートが足りなかったり、周りの目を気にして目立つことを嫌う会社の文化が残っていたりするせいかもしれません。「自分で考えて動く力」を育てるには、上司のサポート、はっきりした目標、そして安心できる雰囲気が必要不可欠[3]で、これらが足りないと、やる気のある人でも力を発揮できません。
ポイント: 「自分で考えて動ける人」を育てるのは時間もお金もかかるし、育てた人が辞めちゃうリスクも。チームワークが乱れたり、変化についていけない人が出たり、「やりがい搾取」にならないように注意も必要。会社は長期的な視点と、人を大切にする仕組みづくりがカギ!
2025年の新入社員はどう? 新しい世代を「自分で考えて動ける人」に!
2025年に入ってくる新入社員(多くはZ世代と呼ばれる若い人たち)は、どんな特徴があるんでしょうか? そして、彼らを「自分で考えて動ける人」として育てるには、どうすればいいのでしょうか?
- 2025年の新入社員の特徴(「新紙幣タイプ」とも):
- デジタルネイティブで、情報を集めたり分析したりするのが得意。[10]
- 「何のために働くのか」という目的意識が強い傾向。[10]
- 新しい技術や色々な考え方を受け入れる柔軟性がある。[10]
- 一方で、失敗を恐れたり、はっきりした答えを求めたりする面も。[10]
- 新しい世代を「自分で考えて動ける人」に育てるには?:
- 彼らの特徴に合わせたやり方が必要です。はっきりした目標や役割を与えるのは大事だけど、同時に彼らが自分から進んで考えて行動するチャンスを与えることが求められます。[10]
- 得意なデジタルスキルを活かしつつ、実際にやってみる経験や、失敗しても大丈夫な環境で色々試してみる機会を意識して作ってあげることが、成長を助けます。[10]
- こまめに、そして具体的に良いところを褒めたり、アドバイスをしたりすること。彼らのアイデアを尊重する、協力的なチームの雰囲気を作ることも大事です。[10]
- 働き始めた早い段階から、彼らが自分で将来を考えて成長していけるように応援し、彼らの「何のために働くか」という気持ちや「成長したい」という意欲に応えることが、やる気を引き出すことにつながります。[10]
【新しい世代を育てる難しさ?】
「新紙幣タイプ」と言われる2025年の新入社員は、デジタルに強い[10]という良い面がある一方で、失敗を怖がったり、はっきりした答えを求めたりする傾向[10]も持っています。これは、「自分で考えて動ける人」を育てる上で、ちょっとした課題になるかもしれません。なぜなら、本当に「自分で考えて動ける」ようになるには、先の見えない中で判断したり、失敗から学んだり、曖昧な状況にも対応したりする力が必要だからです。彼らの新しいことを生み出す力を活かしつつ、どうやって打たれ強さや、曖昧な状況にもめげない力を育てるかがカギになります。ただデジタルスキルを使わせるだけでなく、あえて答えのない課題に取り組ませたり、安全な範囲でリスクを取ることを応援したりするような育て方が必要かもしれません。
【上司も変わらないと!】
こういう新しい世代をうまく育てていくためには、今の上司たちのやり方も変える必要があるかもしれません。Z世代は、もっとこまめなフィードバックや、分かりやすい説明、そして仕事に対するはっきりした目的を求める傾向がある[10]ので、昔ながらの「あれやれ、これやれ」という指示命令型から、部下の話を聞いて引き出すコーチングや、もっと任せてみるやり方に変えていくことが求められます。上司自身が、この新しい世代のやる気のスイッチやコミュニケーションの取り方を理解して、それに合わせて接し方を変えていくことが、会社全体の元気づくことにつながります。
ポイント: 2025年の新入社員はデジタル得意で目的意識も強い「新紙幣タイプ」。彼らの主体性を尊重し、安心して挑戦できる機会と、こまめなフィードバックで成長を応援しよう!上司も新しい接し方が必要かも。
「自分で考えて動ける人」が増えると、日本はどう変わる?
「自分で考えて動ける人」がたくさんいる社会って、どんな社会なんでしょうか? 日本にとって、どんないいことがあるのでしょうか?
- 国全体の競争力アップ、新しいものが生まれる、仕事がもっとうまくいく: 「自分で考えて動ける人」が多いと、新しいアイデアがどんどん生まれて、社会全体が変わっていく力になります。[4] 一人ひとりが自分から考えて効率よく働くようになれば、会社全体の仕事の成果も上がって、日本が世界の国々と競争していく上で、とても大事な力になります。[12] 実際、将来は「問題を見つける力」や「新しいものを生み出す力」がもっと必要になると言われています。[9]
- 働く人が少なくても大丈夫? 変化に強い社会に: 人が減って働く人が少なくなる問題に対して、「自分で考えて動ける人」が全てを解決するわけではないけど、より難しい仕事や価値の高い仕事を担当することで、限られた人手をうまく使うことに貢献します。[1] また、自分で考えて動ける人が増えると、社会全体が急な変化に対応する力が高まって、ピンチにも強くなり、ずっと新しくなり続けることができると期待されます。[1]
- 働く人自身もハッピーに? やりがいアップ!: 一人ひとりが自分で考えて、自分の得意なことを活かして、意味のある仕事ができる環境では、仕事への満足感ややる気、そして毎日の充実感がアップする傾向があります。[44] これは、もっとやる気があって、満たされた気持ちで働く人が増えることにつながり、将来、みんながお互いを支え合う社会保障制度を長持ちさせることにも役立つかもしれません。[44]
- 新しい価値が生まれる! 地方も元気になるかも?: 「自分で考えて動ける人」は、会社の中で新しい価値を生み出したり、新しいビジネスを始めたりする中心メンバーになることができます。[45] さらに、地方の小さな会社同士が協力して人材をシェアし、AIを使って地域の中で一番合う仕事に人を配置する「地域版・人的資本経営」というアイデアは、「自分で考えて動ける人」が地方の経済を元気にする上でも大事な役割を果たす可能性を示しています。[43]
【働き方が変わる?】
「自分で考えて動ける人」が増えると、日本の働き方も変わるかもしれません。一つの会社にずっといるんじゃなくて、自分でキャリアを作っていくようになると、今までの会社への忠誠心や、知識の伝え方、専門家同士のつながり方などが大きく変わるでしょう。「自分で考えて動ける人」は自分のキャリアを自分で決めることを大事にするし[キャリア自律]、国も仕事を変わりやすくする政策を進めている[12]ので、「会社に入ったら一生安泰」という考え方は薄れて、自分の専門性や将来の目標への気持ちが強まるかもしれません。これは、会社にとっては新しい「どうすれば社員に長くいてもらえるか」という作戦が、個人にとってはもっと計画的な「どう自分のキャリアを作っていくか」という考え方が必要になる、ということです。
【新しいものが生まれやすい社会に?】
「自分で考えて動ける人」がたくさん育てられて活躍するようになれば、日本の「新しいものを生み出す仕組み(イノベーションエコシステム)」が根本から変わるかもしれません。大きな会社の研究開発部門や新しい事業部門だけじゃなくて、もっと身近なところから新しいものが生まれたり、会社を作る人が増えたりするかもしれません。「自分で考えて動ける人」は、自分から問題を見つけて解決する力や新しいものを生み出す力を持っている[6]ので、彼らがもっと自由に動けるようになれば、今までの会社の枠を超えて、社会の「もっとこうだったらいいな」というニーズを見つけて、それを解決する動きが加速するでしょう。これは、日本の新しいビジネス(スタートアップ)をもっと元気にし、新しいものを生み出す源を多様化させることにつながります。
【日本の魅力アップにも?】
もし日本が国全体で「自分で考えて動ける人」を育てることに成功したら、それは日本の国際的な地位を上げることにもつながるかもしれません。経済的な面だけでなく、一人ひとりの力を引き出して社会に貢献する、という人の育て方が、世界の国々にとって「日本のすごいところ(ソフトパワー)」として影響を与えるかもしれません。日本は「課題先進国」として[1]、少子高齢化や技術の進化といった課題に直面していますが、高度な「自分で考えて動ける人」を中心とした作戦でこれらの課題を乗り越えることができれば、同じような課題を抱える他の国々のお手本になることができます。これは、人を中心とした成長や、新しい社会の解決策における日本の評価を高めることにつながるでしょう。
ポイント: 「自分で考えて動ける人」が増えれば、日本はもっと強くて、変化に強くて、みんながもっとハッピーに働ける社会になるかも!地方創生や日本の魅力アップにもつながる大きな可能性を秘めている!
まとめ:2025年以降の日本への戦略的アドバイス
「自分で考えて動ける人」が絶対に必要!(再確認)
このレポートで見てきたように、「自分で考えて動ける人」は、2025年以降の日本が直面するであろう複雑な問題を乗り越えて、経済の元気、新しいものの創造、そして社会全体の強さを保つために、なくてはならない存在です。彼らの「自分からやるぞ!」という気持ち、責任感、ずっと学び続ける意欲、そして一人ひとりの強みを活かす力は、変化の激しい時代において、会社と社会全体が成長し続けるための土台となります。
みんなで育てよう!会社、国、そしてあなたへのお願い
「自分で考えて動ける人」を育てるのは、一つの会社や一人の努力だけではできません。社会全体で協力して取り組むことが必要です。
- 会社へのお願い:
- 「自分で考えて動こう!」「どんどんチャレンジしよう!」「ずっと学び続けよう!」とみんなが思えるような会社の文化に変えていくことに、本気で取り組みましょう。
- 仕事の役割をはっきりさせる「ジョブ型雇用」を計画的に導入したり、実践的に新しいスキルを学べる仕組みを整えたりする会社のルール改革を急ぎましょう。
- 「あれやれ、これやれ」じゃなくて、部下の話を聞いてやる気を引き出す「コーチング」や、もっと任せてみるリーダーシップを育てましょう。
- 「やりがい」を言い訳にタダ働きさせるようなことはせず、ちゃんと評価して給料を払い、安心して働ける環境を整えましょう。
- 国(政策を作る人)へのお願い:
- 一生学び続けること、新しいスキルを身につけること、スムーズに仕事を変えられることを応援する政策を、もっと強く、もっと広げましょう。
- 学校と協力して、小さい頃から「自分で考える力」の基礎を育てる授業を取り入れましょう。
- 小さな会社でも「自分で考えて動ける人」を育てられるように、その大切さを伝え、具体的な手助けをしましょう。
- あなた(一人ひとり)へのお願い:
- 自分の将来は自分で作る!という意識を持って、自分から進んで学んだり成長したりするチャンスを掴みましょう。
- 「自分はもっと成長できる!」と信じる気持ち(成長マインドセット)を持って、変化する仕事のニーズに対応できるように準備しましょう。
- 自分自身をよく知る力と、色々な人とつながる力を、積極的に高めていきましょう。
未来へのメッセージ
「自分で考えて動ける人」がたくさん活躍する社会を作るのは、すぐにはできません。会社、国、学校、そして私たち一人ひとりが、それぞれの役割と責任をちゃんと理解して、ずっと協力しながら努力を続けていく長い道のりです。でも、その先にある日本の未来は、きっと素晴らしいものになるはずです。「自分で考えて動ける人」を育てることは、単に経済を良くするだけでなく、もっと創造的で、変化に強くて、そして人間らしい豊かさを感じられる社会を作るための大切な投資と言えるでしょう。
この取り組みが本当に成功するかどうかは、一人ひとりの力を引き出すことと、会社や社会全体の目標を達成することの、難しいバランスをどう取るかにかかっています。「自分で考えて動ける人」の定義に、会社の目標を理解して貢献することが含まれているように[6]、そして、その育成が社会全体の持続可能性を高めることにつながると期待されているように[1]、個人の「自分で考えて動く力」が、ただの自己満足で終わらず、もっと大きな「みんなのため」という気持ちと結びつくことが重要です。
そして、2025年という年は、この変化のゴールの年ではなく、むしろ大事な中間地点と考えるべきです。「自分で考えて動ける人」を育てることは、新しい問題や技術が出てくるのに合わせてずっと進化し続ける、終わりなき適応のプロセスです。2050年にどんな仕事が必要になるかという予測[9]も示しているように、「自分で考える力」「学び続ける力」「変化に対応する力」といった基本的なことはずっと大事であり続けるでしょうが、求められる具体的なスキルや状況は変わり続けます。だから、2025年に向けて作る戦略は、将来の変化にも柔軟に対応できるように、ずっと改善し、発展していくことを前提として設計される必要があります。
引用文献
[1] 2025年の「働く」ーこれからの10年をどう過ごすかで、未来は … 他
[2] 2025年問題とは?企業への影響や業界別の課題・対策を解説 他
[3] 組織の成長を牽引する自律型人財の育み方 | チエルコミュニケーションブリッジ株式会社 – GLEXA 他
[4] 人材開発は企業発展に不可欠。変化を捉えた「自律型人材」を育成する重要性 | 『日本の人事部』 他
[5] 未来人材ビジョン – 経済産業省 他
[6] 自律型人材とは|育成方法やメリット・デメリットを解説 – Schoo 他
[7] 自律型人材とは?特徴や育成のメリット・デメリットを解説 – HR NOTE 他
[8] マインドセットとは?キャリア開発への影響や成長思考への転換方法を解説 – ライトマネジメント 他
[9] 経済産業省による「未来人材ビジョン」 2050年の産業分類別労働需要は3割増から5割減という大きなインパクトで変化 他
[10] 「2025年度(令和7年度)新入社員のタイプは・・・?」 ‐ JobSuite … 他
[11] 看 護 の 将 来 ビ ジ ョ ン – 日本看護協会 他
[12] 多様な働き方 (2025年2月20日 No.3672) | 週刊 経団連タイムス 他
[13] 雇用主の85%が「従業員のリスキリングを優先する」に同意 | 世界経済フォーラム
[14] 社員のキャリア自律を促し、高度専門人材の確保を急ぐ【2025年 … 他
[15] 人材競争力強化のための9つの提言(案) – 経済産業省
[16] 日本老年人护理政策的未来走向
[17] 自律型人材とは?特性や特徴、行動パターン・育成方法などポイントを解説! – LDcube 他
[18] 「リスキリング」とは? 意味や必要性、推進のステップとポイントを解説 – HRプロ 他
[19] 人的資本を高める日本企業のリスキリング戦略 他
[20] キャリア開発とは|具体的な方法や先進的な企業事例を紹介 … – Schoo 他
[21] キャリア自律とは?強い組織作りのために企業がすべき支援、成功事例を紹介 – ライトワークス
[22] 人財 | 社会 | サステナビリティ | 旭化成株式会社 他
[23] リカレント教育とは?リスキリングとの違いや日本の課題について … 他
[24] 人財成長戦略 – MSD
[25] 自律型人材育成研修 – 株式会社グロービス
[26] キャリア自律とは|実現に向けた5ステップから企業事例、メリット … 他
[27] ソニーグループ、MIXIが注力する人材育成とは?
[28] 「ソニーユニバーシティ」で次世代経営人材を育成【ソニーグループ】
[29] 富士通株式会社|多様な正社員制度の導入事例
[30] Career & Growth Well-being : 富士通 – Global (English)
[31] 大日本印刷株式会社様 他
[32] 第11次職業能力開発基本計画を策定しました – 厚生労働省 他
[33] 自律型人材とは何か?ミドルシニア世代を自律型人材 … – PASONA BIZ 他
[34] キャリア自律とは 支援によるメリット・デメリットを解説 … 他
[35] 【事例あり】キャリア自律とは?企業が支援するメリット・デメリット | アルー株式会社 – alue
[36] 自律と他律、それらを超える「合律」とは?〜それぞれの違いやメリット・デメリットを解説 – alue 他
[37] 「やりがい搾取」とは? 陥りやすい業界・職種、予防のたの … 他
[38] ジョブクラフティングとは 「やりがい」で自律性を高める方法を解説
[39] 自律型人材の特徴と育成方法 | 社員のエンゲージメント向上を支援する 株式会社 NTT HumanEX
[40] 自走・自律型人材の教育方法とは?経営に求められる自走力を解説 – 株式会社manebi
[41] 自律型人材とは?特徴や育成方法、研修事例を紹介 | アルー株式会社 – alue
[42] 自律型人材とは ~育成失敗を回避するポイントと成功の秘訣 – 株式会社グロービス
[43] 人的資本経営2025 :「導入から浸透」への戦略的な取り組み | 『日本の人事部』 他
[44] 自律した個が 「いつでも、どこでも、多くても少なくても働くことができる」 社会の実現 2023 – 経済同友会 他
[45] 2025年の壁とは?DX時代に求められる企業のIT・人材戦略 – 株式会社エデンレッドジャパン 他
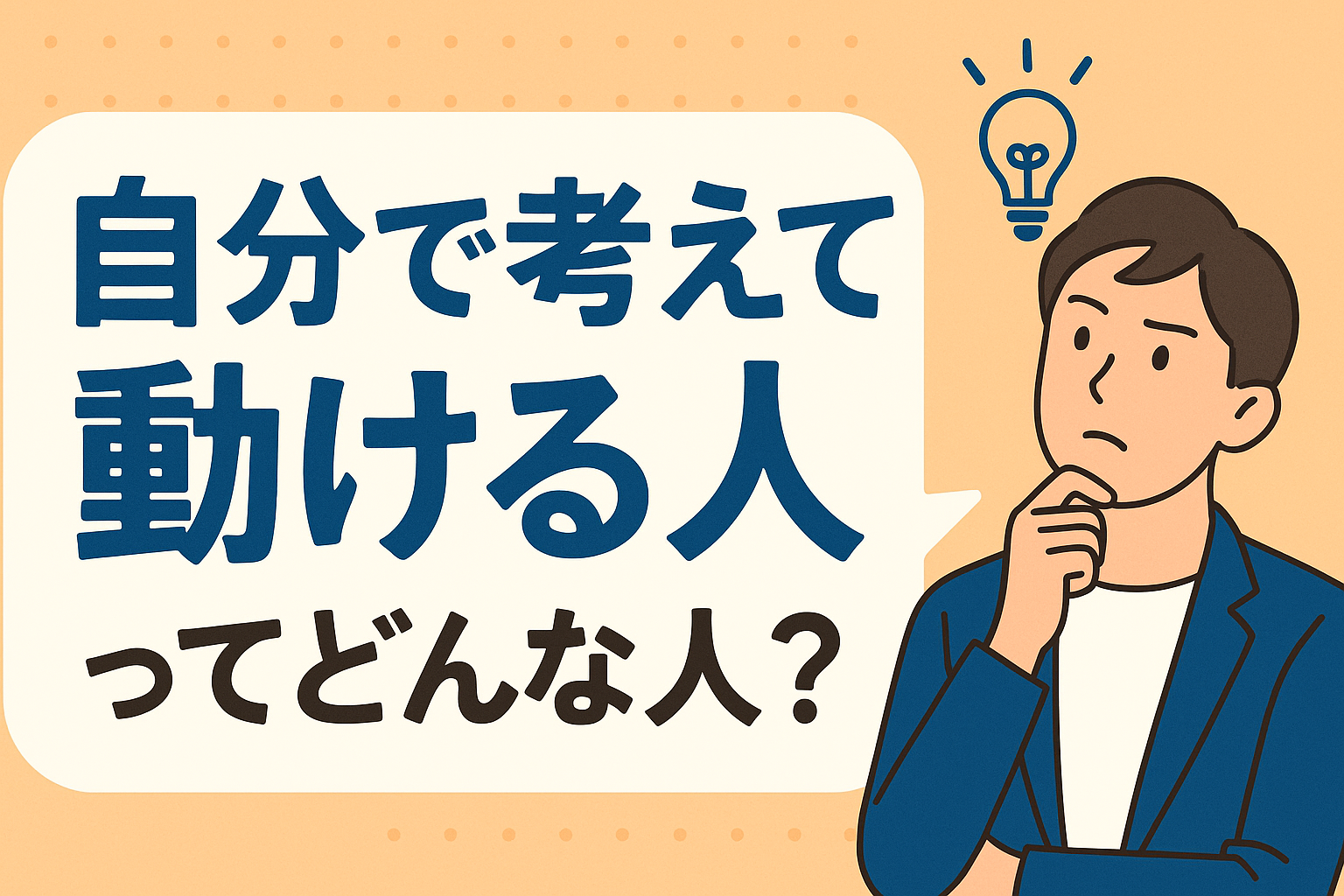

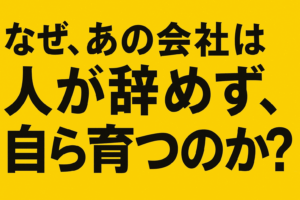
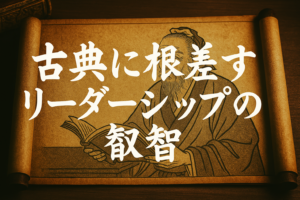
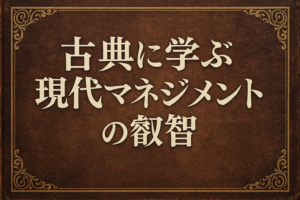
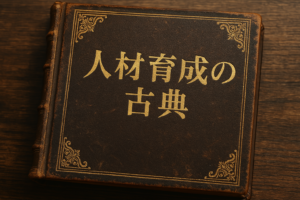
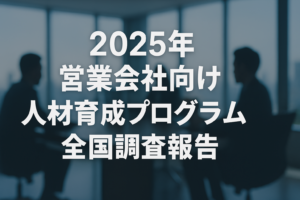


コメント