「日本の年金って、なんだか難しそう…」「外国人でも入らなきゃいけないの?」「もし自分の国に帰ったら、払ったお金はどうなるの?」
日本で生活する外国人の方から、こんな声をよく聞きます。大丈夫、安心してください!このガイドでは、日本の年金制度の「なぜ?」「なにを?」「どうすればいい?」を、ゼロから分かりやすくお伝えします。2025年の最新情報も盛り込みながら、あなたの疑問をスッキリ解消し、日本での生活の安心を一つ増やしましょう。
そもそも、日本の「年金」って何のため?
日本の「年金(ねんきん)」は、みんなで少しずつお金を出し合って、将来誰かが困ったときに助け合うための「大きな貯金箱」のようなものです。
- もし年をとって働けなくなったら?(老齢:ろうれい)
- もし病気やケガで働けなくなったら?(障害:しょうがい)
- もし一家の大黒柱が亡くなったら?(死亡:しぼう)
こんな「もしも」の時に、国がお金を支給して生活を支えてくれる、とても大切な仕組みです。これは、個人の貯金とは別に、社会全体で支え合う「社会保険」という考え方で作られています。
日本の年金は「3階建て」の家みたいなもの
よく日本の年金は「3階建て」と説明されます。
- 1階:国民年金(こくみんねんきん)/基礎年金(きそねんきん)
- これが基本の土台。日本に住む20歳から59歳までの全ての人が入る決まりです。
- 2階:厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
- 会社員や公務員の人が、1階の国民年金にプラスして入る年金です。
- 3階:私的年金(してきねんきん)
- 会社が用意する企業年金や、個人で自由に入るiDeCo(イデコ)など。これは自分で選んで入る、より豊かな生活のためのオプションです。
このガイドでは、特に外国人の方が必ず関わる1階と2階の「公的年金」について、詳しくお話ししますね。
ルールは日本全国どこでも同じ!
年金のルール(誰が入るか、いくら払うか、どんな時にもらえるかなど)は、日本のどこに住んでいても同じです。東京でも、大阪でも、北海道でも、沖縄でも変わりません。
外国人にとって、なぜ年金が大切なの?
- 法律で決まっているから: 日本に住む20歳から59歳の外国人は、日本の年金に入るのが法律で決められています。「入りたくない」はダメなんです。
- 「もしも」の時にもらえる権利: きちんとお金を払っていれば、年をとった時、病気やケガで困った時、家族が亡くなった時に、日本人と同じように年金をもらう権利が得られます。日本で安心して暮らすためのお守りですね。
- 外国人向けの特別ルールもある: 短い期間だけ日本にいて国に帰る人のために、「脱退一時金(だったいいちじきん)」という、払ったお金の一部が戻ってくる仕組みがあります。また、自分の国と日本で二重にお金を払わなくて済むようにしたり、両方の国で年金に入っていた期間を合計できる「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)」という約束もあります。これも後で詳しく説明しますね。
このガイドは【2025年】の情報が中心です
2025年度(2025年4月~2026年3月)の国民年金の月々の支払額や、脱退一時金としてもらえる金額など、最新の情報をお届けします。
外国人も必ず入るの?「強制加入」ってどういうこと?
はい、その通りです。日本の法律では、日本に住所がある20歳から59歳までの人は、国籍に関係なく国民年金に入らなければなりません。 これは外国人の方も同じです。
「住所がある」というのは、ふつう、役所で住民登録をして「住民票(じゅうみんひょう)」が作られている状態のこと。在留カードをもらって日本に中長期で住む外国人は、住民登録をするので、年金に入る義務も発生します。
観光などの短い滞在の人は、住民登録の対象外なので、年金に入る必要はありません。また、特別なビザ(医療滞在ビザなど)の場合は、入らなくてよいこともあります。日本から出国して住民票がなくなると、国民年金に入る資格もなくなります。
あなたはどのタイプ?年金に入る人の3つの種類
年金に入る人は、働き方などによって3つのグループに分けられます。あなたも必ずどれかに当てはまります。
- 第1号被保険者(だいいちごう ひほけんしゃ)
- どんな人?: お店をやっている人、フリーランス、農業をしている人、学生さん(20歳以上)、お仕事をしていない人など。つまり、下の②③に当てはまらない人です。
- どうやって入る?お金は?: 自分で住んでいる街の役所で手続きをして、毎月自分で年金のお金を払います。
- 第2号被保険者(だいにごう ひほけんしゃ)
- どんな人?: 会社員や公務員など、会社や役所に雇われて働く人(70歳未満)。
- どうやって入る?お金は?: 会社が手続きをしてくれます。年金のお金は、毎月のお給料から自動的に引かれ、会社も一部を負担して一緒に払ってくれます。
- 第3号被保険者(だいさんごう ひほけんしゃ)
- どんな人?: ②の会社員や公務員に扶養されている奥さんや旦那さんで、20歳から59歳、日本に住んでいて、年収がだいたい130万円未満の人。
- どうやって入る?お金は?: 扶養している配偶者の会社を通して手続きします。自分で年金のお金を払う必要はありません。
特に「第1号」の人は、手続きも支払いも全部自分でするので、忘れないように気をつけてくださいね。
外国人の年金加入手続き:どこで?何が必要?
- 「第1号」や「第3号」の人の場合:
- いつ?: 日本に来て住民登録をした後、または日本に住んでいる間に20歳になった時。
- どこで?: 住んでいる街の役所の国民年金担当窓口。
- 何がいる?: ふつうは在留カードとパスポート。マイナンバーカードや通知カードも持っていくとスムーズです。手続きが終わると、「基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)」という大切な書類がもらえます(昔は「年金手帳」でした)。
- 「第2号」の人の場合:
- 会社(勤め先)が手続きをしてくれるので、あなたが役所に行く必要はほとんどありません。
もし働き方や家族の状況が変わったら(例:会社をやめてお店を始めた、扶養から外れたなど)、すぐに年金の種類の変更手続きをしてくださいね。
国も外国人の加入をしっかり見ています!
日本政府や日本年金機構(年金を管理する国の機関)は、外国人の方にもちゃんと年金に入ってもらうための取り組みを強めています。住民登録の情報などから、まだ年金に入っていない外国人に連絡したり、手続きを手伝ったりすることもあるかもしれません。年金に入るのは法律で決まった義務なので、しっかり手続きしましょう。
年金にはどんな種類があるの?「国民年金」と「厚生年金」
日本の公的年金の中心は、この2つです。
(A) 国民年金(こくみんねんきん)/基礎年金(きそねんきん)
- 役割と誰が入る?: 日本の年金の「1階部分」。すべての年金の基本です。日本に住む20歳から59歳の全ての人が入ります(第1号、第2号、第3号みんなです)。
- お金はいくら?: 収入に関係なく、みんな原則同じ金額を毎月払います(2025年度の金額は後で説明します)。「第1号」の人は自分で直接払います。「第2号」の人は厚生年金のお金の中に含まれています。「第3号」の人は自分で払う必要はありません。
- どんな時にもらえる?:
- 老齢基礎年金: 原則65歳から、一生もらえるお年寄りのための年金。
- 障害基礎年金: 病気やケガで決められた障害の状態になった時にもらえる年金。
- 遺族基礎年金: 年金に入っていた人が亡くなった時、その人に生活を支えられていた家族(主に子どものいる配偶者や子ども)がもらえる年金。
もらえる老齢基礎年金の金額は、主にお金を払った期間の長さで決まります。40年間全部払うと満額もらえます。
(B) 厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
- 役割と誰が入る?: 公的年金の「2階部分」。会社員や公務員(第2号被保険者)が、国民年金にプラスして入る年金です(70歳未満)。
- お金はいくら?: あなたのお給料やボーナスの金額によって、払うお金が変わります。収入が多いほど高くなります。このお金は、あなたと会社が半分ずつ出し合います(これを「労使折半:ろうしせっぱん」と言います)。あなたが出す分は、お給料から自動的に引かれます。
- どんな時にもらえる?: 国民年金の基礎年金にプラスして、以下の年金がもらえます。
- 老齢厚生年金: 老齢基礎年金に上乗せされる、お年寄りのための年金。
- 障害厚生年金: 障害基礎年金にプラスされる障害の年金。
- 遺族厚生年金: 遺族基礎年金にプラスされる家族のための年金。
厚生年金からもらえる金額は、入っていた期間の長さと、その間のお給料の額によって変わるので、人によって差が大きいです。
【ひと目でわかる】国民年金と厚生年金の違い
| 特徴 | 国民年金(基礎年金) | 厚生年金保険 |
|---|---|---|
| 主に誰が入る? | 日本に住む20歳~59歳の人みんな | 会社員や公務員(70歳未満) |
| お金の計算は? | みんな同じ金額(毎年変わる) | お給料やボーナスによって変わる(現在18.3%の率) |
| お金の払い方は? | 第1号:自分で払う。 第2号:厚生年金と一緒。 第3号:払わなくてよい。 | お給料から自動で引かれる(会社と半分ずつ負担) |
| もらえる年金は? | 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金 (それぞれ基礎年金にプラスしてもらえる) |
| もらえる金額は? | 主にお金を払った期間の長さで決まる | 入っていた期間の長さと、その間のお給料の額で決まる |
見ての通り、会社で働く人が入る厚生年金は、国民年金だけに比べて、将来もらえる年金の額が多くなったり、万が一の時の保障が手厚くなったりする傾向があります。これは、厚生年金が国民年金に上乗せされる仕組みで、会社もお金を半分負担してくれるからです。
2025年度(令和7年度)に払う年金のお金はいくら?
年金制度を続けるためには、みんながお金を払うことが大切です。2025年度(2025年4月~2026年3月)に払うお金について説明します。
(A) 国民年金のお金(保険料:ほけんりょう)
- 毎月の金額: 2025年度の国民年金(第1号の人が払う分)のお金は、1か月 17,510円 です。これは、年齢や収入に関係なく同じですが、毎年見直されます。
- もっと増やしたい人へ(付加保険料:ふかほけんりょう): 「第1号」の人は、毎月の17,510円にプラスして、月々400円を任意で払うことができます。これを払うと、将来もらえる老齢基礎年金が少し増えます。
(B) 厚生年金のお金(保険料率:ほけんりょうりつ)
- お金の割合: 厚生年金のお金の率は、18.3% で決まっています。この率は2017年9月から変わっていません。2025年度もこのままです。
- 会社と半分ずつ: この18.3%を、働くあなた(従業員)と会社が半分ずつ負担します。つまり、あなたが払うのは9.15%、会社も9.15%を払います。
- 国民年金分も入ってる: 厚生年金のお金の中には、1階部分の国民年金のお金も含まれています。なので、厚生年金に入っている人(第2号)は、別に国民年金の17,510円を払う必要はありません。
厚生年金のお金の率がしばらく変わっていないのは、会社や働く人にとって計画が立てやすいですね。でも、日本の高齢化は進んでいるので、将来また率が変わる可能性はゼロではありません。
お金の払い方といつまで?
- 国民年金(第1号の人):
- どうやって払う?: 国から送られてくる「納付書(のうふしょ)」という紙を使って、銀行、郵便局、コンビニで払います。口座からの自動引き落とし(口座振替)やクレジットカード払い、スマホ決済もできます。
- いつまで?: 払う月の次の月の末日まで。
- お得な払い方も!: 半年分や1年分、2年分をまとめて前払い(前納:ぜんのう)すると、少し安くなります。口座振替だと割引が大きいです。また、口座振替で当月分を早く(当月末に)引き落とす「早割(はやわり)」だと、月々60円安くなります。
- 厚生年金(第2号の人):
- どうやって払う?: あなたが払う分(9.15%)は、毎月のお給料やボーナスから自動的に引かれます。会社が、あなたの分と会社が払う分(9.15%)をまとめて、次の月の末日までに国に払います。
お金が払えない時はどうする?(国民年金の免除・猶予制度)
「第1号」の人で、収入が減ったり、仕事を失ったりして、国民年金の17,510円を払うのが難しい時は、申請すればお金の支払いが免除(めんじょ:払わなくてよくなる)されたり、猶予(ゆうよ:待ってもらえる)されたりする制度があります。
- 免除制度: あなたや家族の前の年の収入が少ない場合など、お金の全額または一部(4分の3、半分、4分の1)が免除されます。
- 納付猶予制度: 50歳未満の人で、あなたや配偶者の前の年の収入が少ない場合、支払いを待ってもらえます。
- 学生納付特例制度: 20歳以上の学生さんで、自分の前の年の収入が少ない場合、学生の間は支払いを待ってもらえます。
これらの制度を使うには、必ず申請が必要です。住んでいる街の役所か年金事務所で手続きしてください。
【とても重要!】払わない「未納」と、申請する「免除・猶予」は全然違う!
お金をただ払わない「未納(みのう)」の状態だと、将来年金をもらうための期間にも入らないし、もらえる年金の額も増えません。でも、「免除」や「猶予」を申請して認められれば、その期間も年金をもらうための期間にはカウントされます。もらえる年金の額を計算する時は、全額払った時よりは少なくなりますが、ゼロではありません。免除や猶予されたお金は、後から10年以内なら払うこと(追納:ついのう)もできて、そうすればもらえる年金額を増やすことができます。
だから、もし払うのが難しくても、そのままにしないで、必ず免除や猶予の申請をしてくださいね。
どんな時にお金がもらえるの?年金の種類と条件
日本の年金は、主に3つの「もしも」の時にお金が出ます。
(A) 3つの主な年金
- 老齢年金(ろうれいねんきん): 年をとった時の生活のため。原則65歳から一生もらえます。
- 障害年金(しょうがいねんきん): 病気やケガで法律で決められた障害の状態になった時。若い人でももらえます。
- 遺族年金(いぞくねんきん): 年金に入っていた人やもらっていた人が亡くなった時、その人に生活を支えられていた家族がもらえます。
(B) 老齢年金をもらうための「10年ルール」とは?
お年寄りになって老齢年金をもらうには、基本的にお金を払った期間などが合計10年(120か月)以上必要です。
この「10年」には、以下の期間が全部入ります。
- 国民年金のお金を払った期間
- 厚生年金に入っていた期間
- 国民年金のお金の免除や猶予、学生特例が認められた期間
- 第3号被保険者だった期間
- その他、年金額には反映されないけど期間には入れられる特別な期間(例えば、海外に住んでいた日本人が任意で入らなかった期間や、社会保障協定で他の国の期間と合わせる場合など)
この「10年ルール」は、昔は「25年」でしたが、2017年に短くなりました。
この変更は、特に外国人の方にとって大きな意味があります。昔の25年ルールでは、日本で働く期間が短い多くの外国人が年金をもらうのは難しかったのですが、10年になったことで、日本で10年以上働いたり住んだりする外国人や、後で説明する「社会保障協定」で自分の国と日本の期間を合わせて10年以上になる人が、日本の年金をもらえる可能性がグッと高まりました。
もし10年以上の期間があれば、後で説明する「脱退一時金」はもらえなくなるので、自分の期間がどれくらいあるか知っておくのが大切です。
ただし、10年以上あっても、もらえる年金の金額は、お金を実際に払った期間の長さで決まります。例えば、40年間全部払うと老齢基礎年金は満額ですが、10年間だけ払った場合は、だいたい満額の4分の1くらいになります。
(C) それぞれの年金をもらうための主な条件(かんたんに)
- 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金):
- 原則、お金を払った期間などが10年以上あること。
- 原則、65歳になっていること。(60歳から早めにもらう「繰上げ」や、66歳から遅めにもらう「繰下げ」もできます)
- 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の条件を満たして、厚生年金に1か月でも入っていればもらえます。
- 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金):
- 初めて病院に行った日(初診日)の条件: 障害の原因になった病気やケガで最初に病院に行った日が、年金に入っている間(または20歳になる前など)であること。
- お金を払っていたかの条件: 初診日の前までに、年金に入っていた期間の原則3分の2以上、ちゃんとお金を払っているか免除されていること。または、初診日が2026年3月31日より前で65歳未満なら、初診日の前の1年間にお金の未納がないこと(特別ルール)。
- 障害の程度の条件: 法律で決められた障害の等級(障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級)に当てはまること。身体の障害だけでなく、がんや精神の病気、心臓病なども対象になります。
- 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金):
- 亡くなった人の条件: 亡くなった人が年金に入っていたり、年金をもらっていたりして、ちゃんとお金を払っていたなどの条件を満たしていること。
- 残された家族の条件: 亡くなった人に生活を支えられていた家族であること(一緒に住んでいたか、仕送りがあったなど。収入の制限もあります)。
- もらえる家族の範囲: 遺族基礎年金は、主に「18歳以下の子ども(または20歳未満の障害のある子ども)」がいる配偶者か、その子ども自身が対象。遺族厚生年金は、もっと広い範囲の家族(子どものいない配偶者、親、孫、祖父母など)も対象になることがありますが、年齢などの条件があります。
日本を出る外国人へ:「脱退一時金」という制度があります
「短い期間だけ日本にいて、年金をもらう前に国に帰るんだけど、払ったお金はどうなるの?」
そんな外国人の方のために、「脱退一時金(だったいいちじきん)」という制度があります。
どんな制度?
これは、日本の年金(国民年金か厚生年金)にお金を払ったけど、老齢年金をもらうための10年の期間を満たさないで日本を出る外国人(日本国籍じゃない人)に、払ったお金の一部を返す仕組みです。短い間しか入らなかった人のお金が「ムダにならないように」作られました。
もらうための条件は?
以下の全部に当てはまる必要があります。
- 日本国籍じゃないこと。
- 日本の年金に入っていないこと(つまり、日本を出て、年金に入る資格がなくなっていること)。
- お金を払った期間などが6か月以上あること。
- 国民年金:第1号としてお金を払った期間が合計6か月以上。
- 厚生年金:厚生年金に入っていた期間が合計6か月以上。
- 老齢年金をもらうための10年の期間を満たしていないこと。
- 障害年金などをもらったことがないこと。
- 日本に住んでいないこと(日本を出ていること)。
- 最後に年金の資格がなくなった日から2年以内に請求すること。
いくらもらえるの?(2025年度の目安)
もらえる金額は、国民年金と厚生年金で計算方法が違います。
嬉しいお知らせ! 2021年4月以降に最後にお金を払った(または資格がなくなった)人は、もらえる金額を計算する時の月数の上限が、それまでの3年(36か月)から5年(60か月)に増えました! これで、最大5年分のお金が反映されるようになりました。
- 国民年金の脱退一時金(最後の支払いが2025年度の場合の目安):
| お金を払った月数 | もらえる金額(だいたい) |
|---|---|
| 6か月 ~ 11か月 | 52,530円 |
| 12か月 ~ 17か月 | 105,060円 |
| 18か月 ~ 23か月 | 157,590円 |
| 24か月 ~ 29か月 | 210,120円 |
| 30か月 ~ 35か月 | 262,650円 |
| 36か月 ~ 41か月 | 315,180円 |
| 42か月 ~ 47か月 | 367,710円 |
| 48か月 ~ 53か月 | 420,240円 |
| 54か月 ~ 59か月 | 472,770円 |
| 60か月以上 | 525,300円 |
- 厚生年金の脱退一時金:
あなたの厚生年金に入っていた時の平均のお給料と、入っていた月数によって計算されます。お給料が高くて、入っていた期間が長いほど、もらえる金額も多くなります。
どうやって請求するの?
- いつ請求する?: 日本を出国した後に請求します。日本に住んでいる間はできません。
- いつまで?: 日本に住まなくなった日から2年以内です。
- 請求書はどこで?: 日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます(色々な言葉があります)。
- 何がいる?(主なもの):
- 脱退一時金請求書(書いたもの)
- パスポートのコピー(名前、誕生日、国籍、サイン、在留資格、出国スタンプが見えるページ)
- 日本に住んでいないことがわかる書類(例:住民票の除票のコピー。出国前に役所で「転出届」を出していれば、いらないことも)
- お金を受け取る銀行口座の情報(銀行名、支店名、口座番号、あなたの名前の口座だとわかるもの。日本のゆうちょ銀行や一部のネット銀行はダメなことも)
- あなたの基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳のコピー)
- どこに出す?: 書類をまとめて、郵送で日本年金機構(東京の外国業務グループ宛てが一般的)に送ります。
【出国前のポイント!】 日本を出る前に、必ず住んでいた街の役所で「転出届(てんしゅつとどけ)」を出しておきましょう。そうすると、出国日に住民票が除票になって、日本に住所がないことの証明が簡単になります。
請求してからお金がもらえるまで、数か月(4か月くらいが目安)かかります。
脱退一時金をもらうと、どうなるの?【超重要!】
脱退一時金をもらうと、一つとても大切なことがあります。
そのお金を計算する元になった日本の年金に入っていた期間が、ゼロになってしまいます。
これは、将来、日本の年金(老齢、障害、遺族)をもらうための期間や金額の計算に、その期間が全く入らなくなるということです。また、後で説明する「社会保障協定」で、自分の国と日本の期間を合わせることもできなくなります。
だから、脱退一時金をもらうかどうかは、目先のお金だけじゃなくて、将来年金をもらう可能性を捨てることと引き換えだということを、よく考えてください。特に、日本での期間が10年に近い人や、自分の国が日本と期間を合わせられる「社会保障協定」を結んでいる人は、慎重に判断が必要です。一度もらうと、取り消せません。
税金もかかるの?
脱退一時金には、もらう時に20.42%の所得税がかかります(引かれて振り込まれます)。でも、日本を出た後、手続きをすれば、この税金の一部または全部が戻ってくる(還付される)ことがあります。税金のことは年金事務所じゃなくて、税務署に聞いてくださいね。
あなたの国と日本をつなぐ!「社会保障協定」って何?
海外で働く人が増える中で、年金の問題を解決するために、日本はたくさんの国と「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)」という約束を結んでいます。
何のための約束?
主な目的は2つです。
- お金を二重に払わないため: 日本から外国へ、または外国から日本へ働きに行く時、両方の国の年金に入って、お金を二重に払わなきゃいけない問題をなくします。
- 年金の期間をムダにしないため(期間の通算): 日本と相手の国の年金に入っていた期間がそれぞれ短いと、どちらの国の年金ももらえないことがあります。そんな時、両方の国の期間を合わせて、年金をもらうための最低期間を満たせるようにします。これでお金がムダになるのを防ぎます。
どんな仕組み?
- 二重に払わない仕組み:
会社などから外国に派遣されて働く時、行く期間がだいたい5年以内なら、もといた国の年金にだけ入って、行先の国の年金には入らなくていい、というのが一般的です。そのためには、もといた国の年金機関(日本の場合は日本年金機構)から「適用証明書(てきようしょうめいしょ)」という紙をもらって、行先の国で見せる必要があります。 - 期間を合わせる仕組み(期間の通算):
日本と協定を結んだ国の両方に年金に入っていた期間があるけど、どちらか一方だけでは年金をもらうための最低期間(例えば日本では10年)に足りない時、両方の期間を足し算して、最低期間を満たすか見ます。
例えば、日本で7年、協定を結んだ国(期間通算あり)で4年入っていたら、合計11年。これで日本の老齢年金をもらうための10年の条件クリアです!
ただし、もらえる年金の額は、それぞれの国にお金を払った期間に応じて、それぞれの国から計算されて支払われます。
どの国と約束してるの?(2024年4月時点)
日本は23か国と協定を結んでいます(ドイツ、アメリカ、韓国、フランス、カナダ、インド、中国、フィリピンなど)。
【大切!】 全部の国との協定で「期間の通算」ができるわけではありません。いくつかの国とは「二重に払わない」ことだけが約束されています。自分の国がどっちか、日本年金機構のウェブサイトで確認してくださいね。
脱退一時金とどっちがいい?
もしあなたの国が日本と「期間の通算」ができる協定を結んでいたら、日本を出る時に、
(1) 脱退一時金をもらう(短期のお金は手に入るけど、将来の年金の可能性はなくなる)
(2) 脱退一時金をもらわない(日本の期間を残して、将来自分の国と合わせて両方から年金をもらう可能性を残す)
どちらがいいか、よく考える必要があります。あなたの状況によって違うので、分からなければ専門家(社会保険労務士など)に相談するのもいいですよ。
2025年からの日本の年金はどうなる?外国人への影響は?
日本の年金制度は、社会や経済の変わり目に合わせて、時々見直されています。2025年以降も、いくつか変わるかもしれない点があります。
最近の変更とこれからの注目ポイント
- もっと多くの人が厚生年金に入れるように:
パートやアルバイトで働く人も、厚生年金に入りやすくなるように、ルールが少しずつ変わっています。2024年10月からは、従業員が51人以上の会社で、週20時間以上働くなどの条件を満たす人は、厚生年金に入ることになりました。これからも、もっと多くの人が入れるように変わっていくかもしれません。これまで国民年金だったり、年金に入っていなかった外国人の方も、厚生年金に入るケースが増えるでしょう。 - 「年収の壁」の問題:
扶養に入っている人が、ある程度の年収を超えると自分で社会保険料を払うことになるので、働く時間を調整する「年収の壁」という問題があります。これについても話し合われています。 - その他にも…:
お年寄りが働きながらもらう年金の調整、厚生年金のお金を計算する元になるお給料の上限の見直し、遺族年金のあり方など、色々なことが話し合われています。
これらの話がどうなるかは、まだ決まっていませんが、2025年以降、新しいルールが少しずつ始まるかもしれません。
外国人の加入チェックは厳しくなるかも
年金のルールとは別に、日本年金機構が外国人の方の年金加入状況をしっかりチェックする動きが強まっています。住民登録の情報と照らし合わせて、まだ入っていない人や払っていない人に、きちんと手続きするように連絡が来ることが増えるかもしれません。
2025年、外国人が知っておくべきことまとめ
- 入る義務ともらう権利は変わらない: 日本に住む20歳~59歳の外国人は年金に入る義務があり、お金を払えば日本人と同じように年金をもらう権利があります。
- 2025年度のお金は決まっている: 国民年金は月17,510円、厚生年金の率は18.3%(会社と半分こ)。
- 外国人向け制度は使える: 脱退一時金や社会保障協定は引き続き使えます。脱退一時金の計算が最大5年分になったのは良いニュースですね。
- 加入チェックは厳しくなるかも: きちんと手続きをして、お金を払いましょう。
- 厚生年金に入る人が増えるかも: パートなどで働く外国人も、厚生年金に入るケースが増えています。
日本の年金制度は、外国人にとっても、よりしっかりと管理される方向に向かっていると言えます。
最後に:外国人の皆さんへ、これだけはやっておこう!
日本の年金、少しは身近に感じてもらえたでしょうか?最後に、皆さんにぜひやってほしいことをお伝えします。
- 必ず手続きを!: 日本に来たら、または20歳になったら、自分がどの年金に入るか確認して、すぐに手続きをしてください。
- 自分のお金の状況を把握!: 自分がどの種類で、誰がお金を払うのか(自分?会社?配偶者の会社?)を知っておきましょう。
- お金を払う!(または免除申請): 期限までにちゃんとお金を払いましょう。払うのが難しければ、必ず免除や猶予の申請を。
- 大切な書類は保管!: 「基礎年金番号通知書」は宝物のように。日本年金機構の「ねんきんネット」で自分の記録が見られるので、登録すると便利です。
- 日本を出る時は計画的に!:
- 自分の年金期間が10年あるか確認。
- 10年未満なら脱退一時金をもらえるか確認。
- 自分の国と日本の社会保障協定をチェック。
- 脱退一時金をもらうか、期間を残すか、よく考える。
- 日本を出る前に、必ず役所で「転出届」を出す。
- 新しい情報をチェック!: 年金のルールは変わることがあります。日本年金機構のウェブサイト(色々な言葉があります)などで、新しい情報を見るようにしましょう。
日本の年金は、あなたを守る大切な仕組みです。このガイドが、あなたの日本での安心な生活の助けになれば、とても嬉しいです。



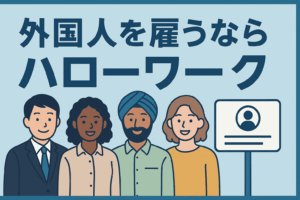

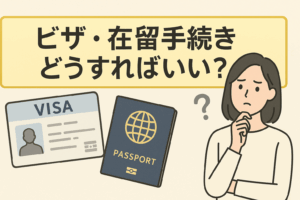

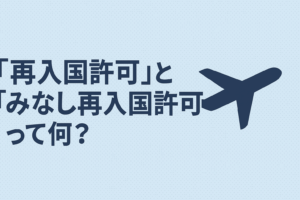
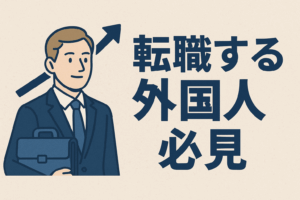
コメント