2025年における義務的住居確保・生活契約支援策に関する報告書
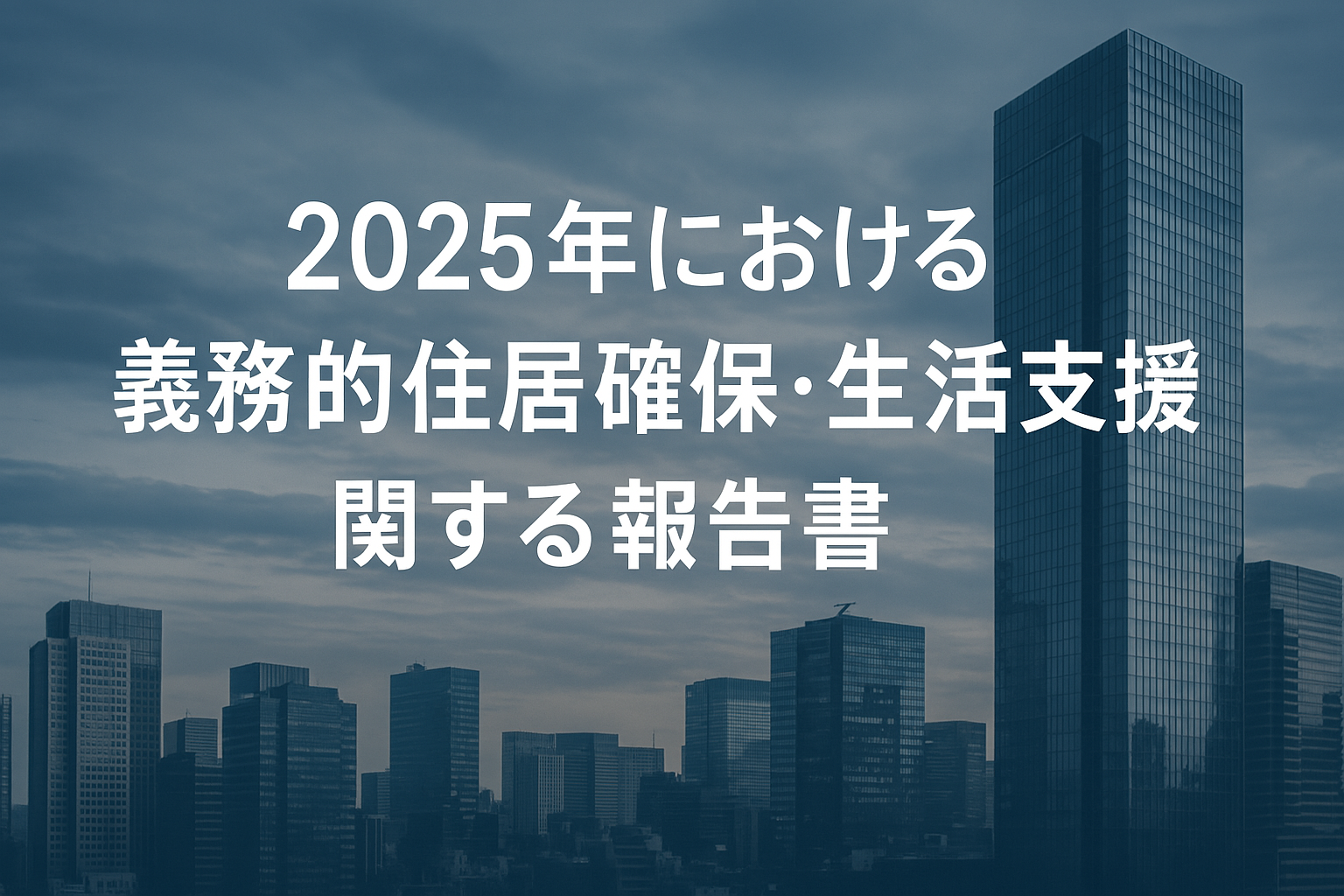
- はじめに
日本社会は、高齢化の進展、経済格差の拡大といった構造的な課題に直面しており、住居の確保や生活に必要な契約を結ぶことが困難な人々が増加しています。このような状況を踏まえ、2025年は、社会福祉制度における重要な転換期を迎えます。政府は、生活困窮者自立支援法や住宅セーフティネット法といった主要な法律を改正し、住居確保支援策や生活困窮者への包括的な支援体制の強化を図る予定です。本報告書では、2025年に日本全国で実施される義務的な住居確保支援策と、生活に必要な契約(電気、ガス、水道、インターネット等)に関する支援策について、その具体的な内容、対象者、申請方法などを詳細に分析します。本報告を通じて、これらの支援策が、住居の安定確保と自立促進にどのように貢献するのかを明らかにすることを目的とします。
- 2025年における義務的住居確保支援策
- 住居確保給付金の拡充:
2025年4月1日の施行が予定されている改正生活困窮者自立支援法に基づき、住居確保給付金制度が拡充されます 1。この制度は、離職などにより経済的に困窮し、住居を失うおそれのある人々に対して、家賃相当額を一定期間支給するものです 5。今回の拡充の重要な点は、家賃の低い住宅への転居費用を補助する仕組みが新たに設けられることです 1。これまで、住居確保給付金は主に家賃の支払いを支援するものでしたが、転居に伴う初期費用が経済的な負担となり、より低廉な家賃の住宅への移動を妨げるケースがありました。この新たな支援策は、そのような課題に対応し、経済困窮者の住居の安定確保をより一層促進することが期待されます。
受給対象者は、離職・廃業後2年以内、または個人の責任によらない理由で給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している人などです 6。また、世帯収入や預貯金額が一定の基準以下であること、ハローワーク等で求職活動を行っていること(転居費用補助の場合は不要 6)などの要件があります 6。申請手続きは、居住地の自立相談支援機関に相談し、必要な書類(本人確認書類、収入を証明する書類、預貯金額が確認できる書類、離職・廃業等を証明する書類など 6)を提出する流れとなります 5。給付金は、原則として自治体から大家等へ直接支払われます(代理納付 6)。この給付金を受ける権利は、譲渡、担保供与、差し押さえの対象とならず、また租税その他の公課を課すことができないと定められています 11。特に、配偶者と死別して年金収入が減少した高齢者や、疾病等で離職して就労収入を増やすのが難しい人などが、今回の拡充による支援の対象として想定されています 3。
- 住宅セーフティネット法の改正:
低所得者や高齢者、障害者といった住宅確保要配慮者の居住の安定を図ることを目的とした住宅セーフティネット法も、2025年秋頃に改正・施行される予定です 2。この改正では、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の拡充や、登録住宅の改修・入居に対する経済的支援の強化が図られます 12。具体的には、賃貸住宅のオーナーが物件情報を都道府県などの行政機関に登録することで、住宅確保要配慮者は登録された賃貸住宅の情報を容易に検索できるようになります 12。
登録住宅に対しては、耐震改修工事、シェアハウスへの用途変更工事、間取り変更工事、子育て世帯対応工事、安否確認ができる設備導入工事などを行った場合に、改修費の3分の1(上限50万円まで)の補助金が支給されます 12。また、低所得者のために家賃を通常より低く設定した場合には、家賃低廉化補助として月額最大4万円までの補助金が支給されます 3。さらに、家賃債務保証料の低廉化に係る補助として、住宅確保要配慮者と保証契約を締結した保証会社に対して最大6万円の補助が支給されます 12。
今回の改正では、賃貸オーナーの不安軽減策として、終身建物賃貸借の利用促進や、居住支援法人による残置物処理の推進、家賃債務保証業者の認定制度の創設なども盛り込まれています 13。終身建物賃貸借は、賃借人が死亡するまで契約が更新されず、死亡時に終了するもので、身寄りのない高齢者などが安心して賃貸契約を結びやすくなります 13।また、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されることで、入居者の死亡後の残置物処理に関するトラブルを未然に防ぐことが期待されます 13。家賃の滞納に困らない仕組みとして、国土交通大臣が認定した家賃債務保証業者に対して、独立行政法人住宅金融支援機構による保険適用が行われ、保証リスクが低減されるようになります 13。生活保護受給者が入居する場合には、住宅扶助費(家賃)について、原則として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う「代理納付」が導入される予定です 13。
- 居住サポート住宅と居住支援法人:
改正住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者のニーズに応じた見守りや生活相談、福祉サービスとの連携などを行う「居住サポート住宅」の認定制度が創設されます 2。これらの住宅では、居住支援法人等が入居者の安否確認(ICT等を活用した1日1回以上の確認や、1ヶ月に1回以上の訪問等による見守り 17)や、生活や心身の状況が不安定になった際の福祉サービスへのつなぎなどの支援が行われます 2。居住支援法人は、住宅確保要配慮者が安心して地域生活を送れるよう、入居支援だけでなく、入居中の生活支援、退去時の支援など、多岐にわたるサポートを提供します 13。
- 居住支援協議会:
住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制を強化するため、国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定し、市区町村による居住支援協議会の設置が促進されます(努力義務化 13)。居住支援協議会は、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退去時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進する役割を担います 1。協議会は、大家と要配慮者の双方にとって安心できる市場環境の整備、居住支援法人等を活用した入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化といった目標達成を目指します 13。協議会の機能・役割は、地域の状況や課題によって様々ですが、基本的には、多様な関係者を“つなぐ”ことにより、それぞれの業務範囲・得意分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の隙間を埋めることができる“関係者同士が連携協働するプラットフォーム”としての役割が期待されています 19。
- 2025年における生活に必要な契約支援策
- 外国人労働者への支援:
2025年においても、特定技能1号の在留資格で働く外国人労働者に対しては、受け入れ企業(特定技能所属機関)または登録支援機関による義務的な支援が継続されます 24。この義務的支援には、住居の確保に向けた支援だけでなく、銀行口座の開設、携帯電話やライフライン(電気、ガス、水道など)、インターネットの契約といった生活に必要な契約に関する支援が含まれます 24。受け入れ企業は、外国人労働者が日本で安心して生活できるよう、これらの契約手続きを補助することが求められます 26。具体的には、契約手続きに関する情報提供、書類作成のサポート、必要に応じて保証人となることなどが含まれます 24。住居に関しては、企業が借り上げて提供する義務はありませんが、外国人労働者自身が契約できる場合はそれでも問題ありません。ただし、契約手続きのサポート(通訳、書類確認、保証人の準備など)は必須です 27。
- その他の潜在的な支援策:
高齢者、障害者、低所得者といった他の脆弱な立場にある人々に対する生活に必要な契約に関する直接的な義務的支援策は、提供された資料からは明確には示されていません。しかし、住居確保支援策が拡充されることで、結果的にこれらの人々が住居を確保しやすくなり、それに伴い電気、ガス、水道などの契約を結ぶ必要が生じるため、間接的な支援効果が期待されます。例えば、住居確保給付金によって家賃の支払いが支援されることで、住居を維持し、結果としてライフラインの継続利用につながります。また、住宅セーフティネット法による住宅の確保支援は、生活基盤の安定につながり、生活に必要な契約を結ぶための前提条件となります。一部の自治体では、高齢者向けの生活支援サービスとして、ライフラインの解約手続きの代行などが提供されている事例 29 もありますが、これらは義務的な支援というよりは、地域の実情に応じた取り組みと考えられます。低所得者向けの物価高騰支援給付金などは、生活費全般を支援するものであり、間接的に生活に必要な契約の費用負担を軽減する効果はありますが、契約手続きそのものを支援するものではありません 30。
- 支援策の対象となる人々
- 住居確保給付金: 離職・廃業後2年以内の方、または個人の責任によらない理由で収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方 6。その他、収入や資産が一定基準以下であること、求職活動を行っていること(転居費用補助の場合は不要 6)などが要件となります 6。特に、単身高齢者や疾病等により就労が困難な方も対象となることが想定されています 1。
- 住宅セーフティネット法: 低所得者、高齢者、障害者、発災後3年以内の被災者、外国人など、住宅の確保に特に配慮を必要とする人々が対象となります 2。
- 居住サポート住宅: 住宅セーフティネット法と同様に、低所得者、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者が対象となります。特に、安否確認や生活相談、福祉サービスとの連携といったサポートを必要とする方が対象となります 2。
- 外国人労働者: 特定技能1号の在留資格を有する外国人が対象となります 24。
- 支援策を利用するための申請方法や窓口
- 住居確保給付金: 居住地の市区町村にある自立相談支援機関が主な窓口となります 5。申請者は、まず自立相談支援機関に電話等で相談し、面談の予約を取る必要があります 5。面談時には、必要書類の説明を受け、申請書類を作成します 5。作成した書類を担当窓口に提出後、審査を経て支給対象となると証明書や決定通知が届きます 5。
- 住宅セーフティネット法: 登録されている賃貸住宅の情報は、国土交通省が運営する「セーフティネット住宅情報提供システム」などで検索できます 12。入居を希望する物件が見つかった場合は、その物件の管理会社やオーナーに直接問い合わせて入居申請を行います 12。居住支援協議会も、物件情報の提供や入居支援を行っていますので、地域の協議会に相談することも有効です 13。
- 居住サポート住宅: 居住サポート住宅の情報も、セーフティネット住宅情報提供システムを通じて検索できる可能性があります。また、地域の居住支援法人や自治体の窓口に問い合わせることで、詳細な情報を得ることができます。申請方法については、各住宅の管理事業者によって異なるため、直接確認が必要です。
- 外国人労働者: 特定技能1号の外国人労働者は、所属する企業または契約している登録支援機関を通じて、住居の確保や生活に必要な契約に関する支援を受けます。自ら手続きを行うことが難しい場合は、これらの機関に相談することが最初のステップとなります 24。
- 結論
2025年には、日本において、住居の確保と生活に必要な契約に関する義務的な支援策がより一層強化される見込みです。住居確保給付金の拡充は、経済困窮者の住み替えを支援し、より安定した住環境への移行を促進します。住宅セーフティネット法の改正は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進し、大家と入居者の双方にとって安心できる環境整備を目指します。居住サポート住宅の創設と居住支援法人の活動は、住居だけでなく、生活支援や福祉サービスとの連携を提供し、より包括的なサポート体制を構築します。また、外国人労働者に対する手厚い支援は、多文化共生社会の実現に向けた重要な取り組みと言えるでしょう。これらの支援策が適切に機能することで、 vulnerable な立場にある人々が地域社会で安心して生活を送るための基盤がより強固になることが期待されます。今後は、これらの制度の円滑な実施と、利用者のニーズに合わせた柔軟な運用が重要となります。
| 支援策 | 主な内容 | 対象者 | 申請窓口 |
| 住居確保給付金 | 家賃相当額の支給、転居費用の補助 | 離職・廃業者等、低所得者 | 各市区町村の自立相談支援機関 |
| 住宅セーフティネット法 | 賃貸住宅登録制度、改修費補助、家賃低廉化補助、家賃債務保証料補助 | 低所得者、高齢者、障害者等 | セーフティネット住宅情報提供システム、自治体窓口 |
| 居住サポート住宅 | 安否確認、生活相談、福祉サービス連携 | 低所得者、高齢者、障害者等 | 各住宅の管理事業者、居住支援法人、自治体窓口 |
| 外国人労働者支援 | 住居確保、生活契約のサポート | 特定技能1号の外国人労働者 | 所属企業または登録支援機関 |
引用文献
- 住居確保給付金の対象拡大へ 生活困窮者自立支援法など改正案を …, 4月 2, 2025にアクセス、 https://fukushishimbun.com/series08/34003
- 【Vol.86】セーフティネットに係る2つの法改正と居住支援の課題 ~本格的な家賃補助の検討を, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.sompo-ri.co.jp/issue_quarterly/20250331-17419/
- 本格的な家賃補助制度の導入に向けて~住居確保給付金や家賃低廉化補助の拡充も視野に, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.sompo-ri.co.jp/2025/01/30/16105/
- 生活困窮者支援で転居費用も給付 改正法が来年4月施行 – 福祉新聞Web, 4月 2, 2025にアクセス、 https://fukushishimbun.com/series08/35029
- 【2025年版】引っ越しに使える補助金はある?, 4月 2, 2025にアクセス、 https://hojyokin-concierge.com/media/2024/03/27/2024_tenkyo_jyoseikin_jyoken
- 家賃を払えない人を救う「住居確保給付金」とは? 2025年4月1日には制度拡充も – ホームズ, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_01189/
- 住居確保給付金事業のお知らせ – 中野区, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/hogo/jyukyokakuho.html
- 住居確保給付金について – 愛知県, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html
- 厚生労働省生活支援特設ウェブサイト | 住居確保給付金:制度概要, 4月 2, 2025にアクセス、 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
- 住居確保給付金申請前に事前にお読みください | 札幌市生活就労支援センター ステップ, 4月 2, 2025にアクセス、 https://step-sapporo.jp/housingbenefit/
- 生活困窮者自立支援法 – e-Gov 法令検索, 4月 2, 2025にアクセス、 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105?occasion_date=20250401
- 2025年秋頃改正。住宅セーフティネット法の概要や改正点を解説, 4月 2, 2025にアクセス、 https://biz.homes.jp/column/topics-00208
- 住宅セーフティネット法、2025年10月改正へ 高齢者などの入居支援 – ツギノジダイ, 4月 2, 2025にアクセス、 https://smbiz.asahi.com/article/15494062
- 改正住宅セーフティネット法は賃貸ビジネスにも寄与するのか …, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00392/
- 2025年秋の施行を目指す住宅セーフティネット制度の改正案とは? – ホームズ, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_01194/
- 住宅セーフティネット法改正で何が変わる?不動産オーナーが知るべきポイント, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.homenet-24.co.jp/media/mimamori/a43
- 1. 大家が賃貸住宅を提供しやすく、 要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備 – 国土交通省, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001879546.pdf
- 居住サポート住宅とは?|生涯現役ハウス横浜支部 – note, 4月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/sghyokohama/n/n82bc0d49dc8d
- 住宅セーフティネット制度の見直しの背景・必要性, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/kensetsu_jutaku/oshirase/kyojyusien.files/0009_20241224.pdf
- 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001603480.pdf
- 高齢者に対する居住支援施策について, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/content/001434201.pdf
- 居住支援協議会 参考(2) – 国土交通省, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/common/001117438.pdf
- 単身高齢者、障がい者らに安心の住まいを提供 | ニュース – 公明党, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.komei.or.jp/komeinews/p353754/
- 【2025年版】登録支援機関とは?特定技能外国人支援に関する役割、要件、申請方法について, 4月 2, 2025にアクセス、 https://linku-s.com/media/tourokushienkikan/
- 「登録支援機関」の役割とは?義務的支援の内容や監理団体との違いを外国人雇用労務士が解説, 4月 2, 2025にアクセス、 https://japannesia.com/howto/support-organization/
- 特定技能外国人の義務的支援 必須10項目から支援計画まで徹底解説, 4月 2, 2025にアクセス、 https://nihongocafe.jp/specific-skills-foreigners-mandatory-support/
- 特定技能に住居準備は必要?企業が押さえるべき義務とポイント, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.rikuaji.com/5060
- 2025年における登録支援機関の義務的支援と任意的支援に関する全国調査報告書, 4月 2, 2025にアクセス、 https://blog.kenkyo.ai/2025/04/01/2025%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%A8%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%9A%84/
- 身元保証等高齢者サポート事業に関連する制度の概要等, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000895032.pdf
- 2025年(令和7年)最新情報を提供!物価高騰支援給付金とは? – EXPACT株式会社, 4月 2, 2025にアクセス、 https://expact.jp/2025_kyufukin/
- 【2025年最新】非課税世帯に3万円給付!概要やその他経済対策も紹介 – ちょっと得する知識, 4月 2, 2025にアクセス、 https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/001375.html
- 2025年2月最新!3万円給付金はいつもらえる? – みんなの補助金コンシェルジュ, 4月 2, 2025にアクセス、 https://hojyokin-concierge.com/media/2024/08/20/Teisyotoku_tuikakyuhukin_itu
- 低所得者支援及び定額減税補足給付金 自治体向け概要資料 – 地方創生, 4月 2, 2025にアクセス、 https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/04_gaiyousiryou.pdf
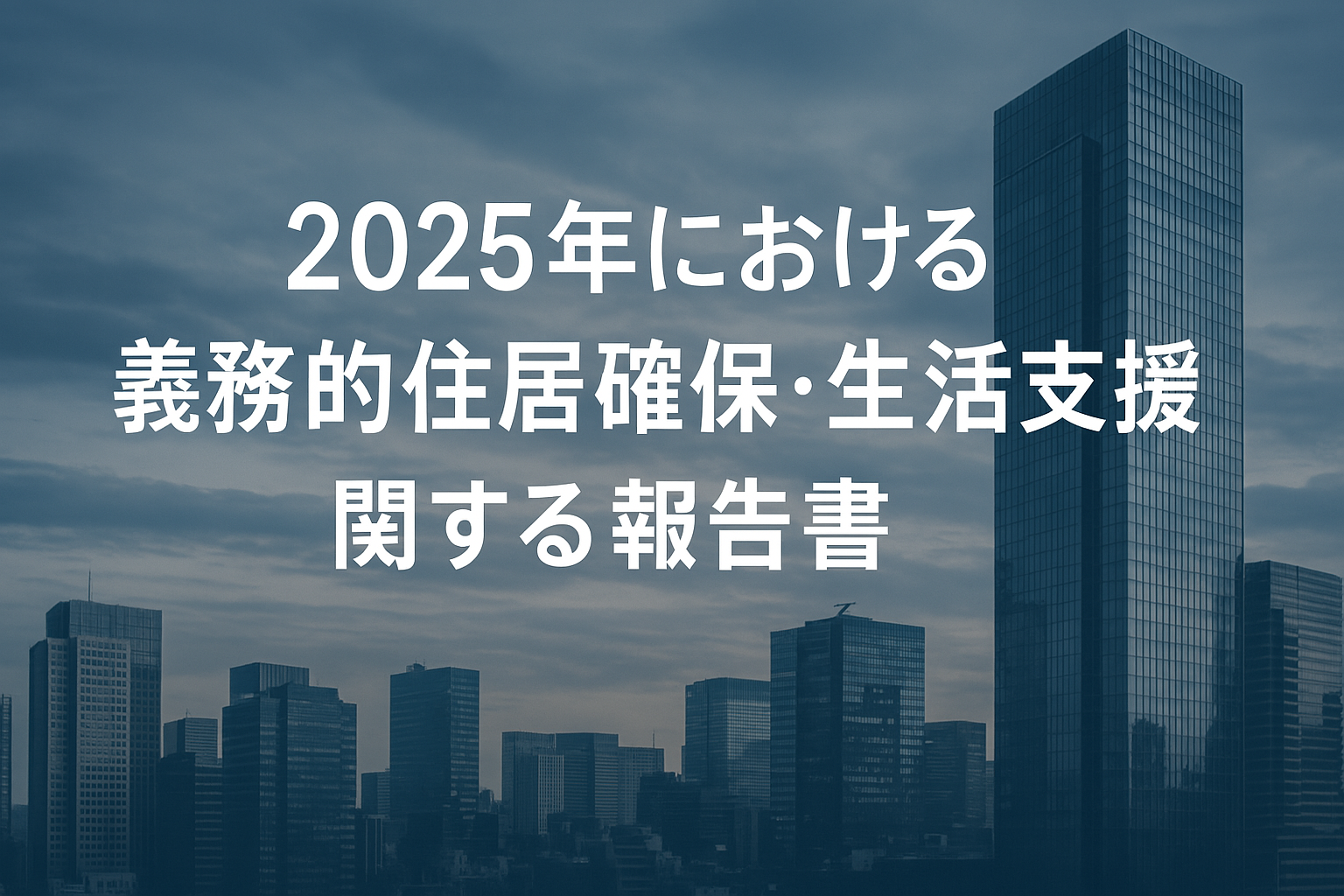




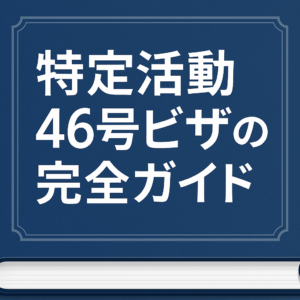
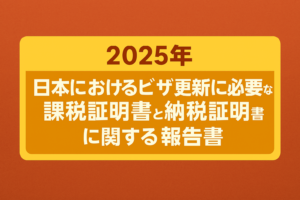

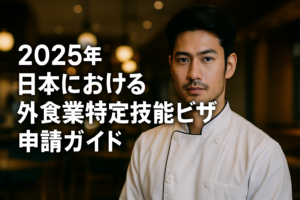
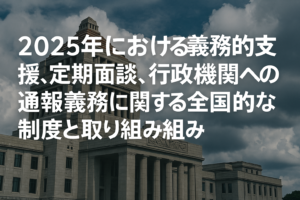
コメント