エグゼクティブサマリー
2025年の日本において、「婚活」は依然として結婚に至る重要な経路であり続けている。大手結婚相談所ネットワークであるIBJは、2024年に過去最多の成婚組数を報告しており 1、婚活市場の活況を示唆している。市場は、AI技術の導入やマッチングアプリの進化 3、そして「ファミレス恋愛」に代表されるようなコスト意識の高まり 6 や、神社仏閣でのイベント開催といった新たな出会いの場の出現 3 など、テクノロジーと社会トレンドの両面で多様化・進化を遂げている。成婚の成功は、年齢、収入、居住地域といった人口統計学的要因に依然として影響されるものの 7、その影響度合いには変化も見られる 8。国や地方自治体による婚活支援策は全国的に展開されているが、その内容は地域によって差がある 10。婚活サービス利用者は、サービスを通じて出会った相手との関係満足度が高い傾向にあると報告されているが 5、多様な選択肢や期待値の調整といった課題も存在する。2025年に婚活を通じて結婚を目指す上では、利用可能なリソースを活用し、戦略的に活動に取り組むことが成功の鍵となるだろう。
1. 日本における婚活の現状(2024-2025年):概観
1.1 市場の重要性:結婚への主要経路としての婚活
かつては特別な活動と見なされがちだった婚活は、現代日本の結婚において、もはやニッチな存在ではなく、主要なチャネルの一つへと変貌を遂げている。2023年に結婚した人のうち、実に15.3%が婚活サービス(結婚相談所、婚活サイト・アプリ、婚活パーティー等)を通じて相手を見つけており、これらのプラットフォームへの依存度の高さがうかがえる 5。これは、従来主流であった知人からの紹介や職場での出会いといった経路からのシフトを示しているが、一方で、オフィス回帰の流れの中で職場が出会いの場として再認識される動きも見られる 3。
特に注目すべきは、インターネットを介した婚活サービス(ネット系婚活)の隆盛である。2023年の婚姻者のうち、ネット系婚活サービスを通じて結婚した人の割合は11.4%に達し、過去最高を記録した 5。これは、デジタルプラットフォームが人々の関係構築プロセスにいかに深く浸透しているかを明確に示しており、オンラインでの出会いに対する抵抗感の低下と、その有効性の向上が背景にあると考えられる。
婚活市場自体も成長軌道にあると予測されている。結婚・恋愛感情サービス市場は、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.1%での成長が見込まれている 14。この成長は、伝統的な結婚率の低下や、個人の幸福追求、メンタルウェルネスへの関心の高まり、そして関係構築サポートへの需要増加といった要因によって牽引されている 14。これは、婚活サービスへの持続的な需要と、サービスの継続的な進化を示唆している。
1.2 主要統計:成功率と活動期間
婚活市場における活動の活発さは、主要事業者から報告される成婚数にも表れている。例えば、日本結婚相談所連盟(IBJ)のプラットフォームでは、2024年の成婚組数が16,398組に達し、過去最多を更新した 1。(ただし、IBJが公開した別の分析レポート『成婚白書』では、分析対象となった2024年の成婚者数を15,374名としている 7。これは集計対象や期間の違いによる可能性があり、留意が必要である。)このような数字は、確立されたネットワーク内での高い活動レベルを示している。IBJグループは、日本の年間婚姻組数の4%を創出することを目標に掲げている 15。
婚活サービス、特に結婚相談所を利用して成婚に至った人々の活動期間は、比較的短い傾向にある。IBJのデータによれば、初婚者の場合、成婚に至るまでの平均在籍期間は約9ヶ月、結婚を前提とした交際期間(真剣交際期間)は約4ヶ月であった 8。これは、一般的な恋愛における平均交際期間が約4.3年であることと比較すると 8、婚活サービス利用者が結婚という明確な目的意識を持ち、効率的に意思決定を行っていることを示唆している。
ただし、婚活の成功率は一様ではない。特定の条件下では高い成功率が報告されている。例えば、IBJネットワーク内では、都市部に住む30代前半の男性の成婚率は50%に迫る水準に達するケースもある 7。しかし、全体的な成功率は、後述する様々な要因によって大きく左右される。
1.3 成功要因:人口統計学的影響
婚活の成否には、個人の属性が依然として大きな影響を与えている。
- 年齢: 伝統的に、男女ともに若い年齢の方が成婚しやすい傾向にある。IBJの2024年成婚者データによると、初婚者の成婚時の平均年齢は女性が34歳、男性が36歳であった 8。しかし、近年の傾向として、男性においては年齢が上がるほど成婚が難しくなる傾向がより顕著になっている。特に40代になると、たとえ高い年収であっても成婚率が低下するケースが見られ、高収入というアドバンテージが年齢の壁を越えにくくなっていることが示唆される 7。この事実は、男性もまた、早い段階で婚活を開始することの重要性が増していることを物語っている 8。
- 収入: 男性の場合、一般的に年収が高いほど成婚率は高くなる。特に年収600万円以上が一つの目安とされ、IBJ加盟相談所では、この層の男性会員が全体の約半数を占める 7。しかし、前述の通り、年齢が上昇すると収入のプラス効果は弱まる 7。一方で、2024年のデータでは、20代男性においては年収500~1,000万円台でも成婚率が50%を超えるなど、若年層においては以前と比較して年収の影響がやや緩やかになっている可能性も示唆されている 8。
- 地域: 婚活市場には明確な地域差が存在し、特に男性にとっては都市部が有利な環境となっている。IBJの分析によると、都市部在住の男性は地方在住の男性よりも成婚率が9.2ポイント高く 9、30代前半では成婚率が50%に達するケースもある 7。これは、都市部における出会いの機会の多さ、平均所得の高さ、そして婚活サービスへのアクセスの容易さなどが複合的に影響していると考えられる。
- 外見・身だしなみ: 多くの婚活者が相手に求める条件として「人柄」を挙げる一方で、最初の接点となる「見た目」が、実際には重要な初期フィルターとして機能している 16。ある調査では、婚活女性の96%が相手のファッションや身だしなみを気にすると回答したのに対し、自身のそれに「大いに自信がある」と答えた男性はわずか5%に留まった 7。これは、第一印象における期待値と自己評価の間にギャップが存在する可能性を示しており、外見への配慮が初期段階での関係構築において無視できない要素であることを示唆している。
これらの分析から、いくつかの重要な点が浮かび上がる。まず、結婚相談所などでの比較的短い成婚期間 8 は、利用者が明確な結婚意欲を持ち、サービスが提供する構造化されたプロセス(プロフィール、お見合い、カウンセリング等)を活用して効率的に意思決定を進めている結果と考えられる。この効率性は、時間を有効に使いたい、あるいは曖昧な関係を避けたいと考える利用者にとっては大きな魅力であろう。しかし、同時に、短期間での決断を迫られるプレッシャーを生む可能性も否定できない。
次に、高収入の男性であっても年齢が上がると成婚が難しくなるという事実 7 は、単に「高収入=有利」という単純な図式では捉えきれない複雑な力学が存在することを示している。40代以降になると、経済力だけではカバーしきれない、年齢に関連する他の要因(価値観の柔軟性、ライフスタイルの互換性、子供に対する考え方の一致など)が、より重要なハードルとして浮上する可能性がある。これは、収入、年齢、そして相手からの魅力度の関係が非線形であることを示唆している。
さらに、都市部男性の顕著な有利性 9 は、単に出会いの母数が多い、収入が高いといった理由だけではないかもしれない。都市部における生活様式がアプリや相談所の利用により親和性が高い、あるいは、地方に比べてフォーマルな婚活サービスに対する社会的な抵抗感が少ないといった文化的背景も影響している可能性がある。逆に、地方では、依然として伝統的なコミュニティ内でのつながりに依存する傾向があるかもしれないが、そのつながり自体が希薄化している可能性もある。この地域差は、全国一律ではない婚活体験の実態を反映しており、例えば地方部でのアクセス向上策と、競争が激しい都市部でのカウンセリングやニッチなマッチング支援といった、地域の実情に合わせた、よりきめ細やかな公的支援の必要性を示唆している。
2. 2025年の婚活を形作る進化するトレンド
2025年の婚活市場は、テクノロジーの進化、経済・社会状況の変化、そして人々の価値観の変容を受けて、常に新しい動きを見せている。
2.1 テクノロジーの統合:AIとアプリの高度化
- AIの活用深化: 人工知能(AI)は、単なる条件フィルタリングを超えて、婚活の様々な側面に統合されつつある。自治体が支援するマッチングシステムにおいて、価値観診断テストの結果をもとにAIが相性の良い相手を提案する試み 11 や、民間のサービスにおいてプロフィールの最適化やコミュニケーションのアドバイス(「AIモテ」)にAIを活用する動き 3 が見られる。これは、社会全体におけるAI活用の広がりを反映した動きと言える 3。
- マッチングアプリの中心的役割と進化: マッチングアプリは依然として婚活の中心的なツールであり、多くの人々が利用している。利用者の約半数強(57.8%)は1つのアプリに絞って活動しているが、残りの42.2%は複数のアプリを併用しており、目的に応じて使い分ける層も少なくない 18。アプリ利用に対するオープンさも増しており、約9割の男女が友人や知人にアプリ利用を話せる(特に女性は91.3%)と回答している 18。これは、アプリ利用が社会的に広く受容され、スティグマが薄れていることを示している。
- アプリの専門化・特化: アプリ市場は多様化し、特定のニーズに応えるものが登場している。例えば、年収や職業証明を重視するハイクラス層向けアプリ(例:「Gorgeous」20)や、明確な結婚意欲を持つ層に特化したサービス(例:ブライダルネット利用者の96%が結婚を見据えて活動 7)などが存在する。
2.2 経済・社会の影響
- コスト意識の高まり: 食料品をはじめとする物価上昇が続く中、家計への影響はデートのスタイルにも及んでいる。「ファミレス恋愛」という言葉に象徴されるように、ファミリーレストランなど比較的安価な場所でのデートを好む傾向が見られる 6。これは、経済的なプレッシャーが、関係構築の初期段階における行動様式を変化させていることを示唆している。
- テーマ型婚活の広がり: 婚活イベントは、単なる出会いの場から、特定の興味関心や地域性を結びつける形へと進化している。神社仏閣での縁結びイベント 3 や、大阪・関西万博に関連した「たこやき婚」3 などがその例である。共通の趣味や価値観に基づいたつながりを求める動きの表れと言える。地方自治体も、ワーケーション 15 や地域の魅力発信 11 といったテーマを婚活イベントに取り入れている。
- 社会的影響力の波及: 大谷翔平選手の結婚発表が婚活への関心を高めた「大谷婚」現象 3 のように、著名人の動向や社会的な出来事が、個人の婚活へのモチベーションに影響を与えることがある。これは、社会的な物語やムードが個人の意思決定に作用する側面を示している。
- 家族形態の変化への対応: 離婚率や再婚率の上昇に伴い、少なくとも一方の親が実子でない子を含む家族形態(ステップファミリー)が増加しており、これに対応した「ステップファミリー婚」3 も、今後の婚活における重要な考慮事項となりつつある。婚活サービスも、こうした多様な家族形態を前提としたサポート体制の構築が求められる可能性がある。
- 合理的な結婚観の浸透: 結婚をより合理的に捉え、婚前契約を結ぶカップルなども現れており、今後もこうした傾向は増えると予想される 3。これは、婚活サービス利用者がライフプランに関するすり合わせを重視する傾向 5 とも符合する動きである。
2.3 出会いの場と価値観の変化
- 職場の再評価: 一部でオフィス回帰が進む中、日常的にオフラインで時間を共にする「職場」が、新たな(あるいは再認識された)出会いの場として機能し始めている 3。これは、婚活サービスを代替するものではなく、共存する出会いのチャネルの一つとして捉えるべきだろう。
- ユニークな出会いの場の活用: 定番のパーティー会場だけでなく、神社仏閣といったユニークな場所がマッチングイベントの舞台として活用されている 3。これは、特定の価値観を持つ層にアピールしたり、従来とは異なる雰囲気での出会いを演出したりする狙いがあると考えられる。
- 「生き抜く力」の重視: 物価上昇や天災リスクなど、社会・経済的な不安定さが増す中で、本業以外の収入源を持つ、自己実現のために活動しているといった「生き抜く力」や「頼りがい」が、パートナーとしての魅力として評価される傾向がある 3。これは、単なる経済力だけでなく、変化に対応できるレジリエンス(回復力・適応力)や安定性への希求を反映している可能性がある。
これらのトレンドを俯瞰すると、2025年の婚活市場は、画一的なものではなく、多様な選択肢が存在する場であることがわかる。AIを活用したハイテクなマッチング 3 と、神社でのイベント 3 や職場での再会 3 といった伝統的・体験的なアプローチが共存している。これは、利用者が自身の価値観や予算、テクノロジーへの親和性に応じて、様々な手法を組み合わせながら活動している実態を示唆している。サービス提供者や支援機関は、このようなマルチチャネル化の現実を認識する必要があるだろう。
また、マッチングアプリの利用が一般化し 18、多くの人が気軽に利用する一方で、経済的な理由からデートの内容が質素になる傾向 6 が見られる。これは、アプリが出会いの「きっかけ」を提供するツールとして定着したものの、その後の関係性の進展(=デート活動)は、経済状況によって左右される度合いが強まっている可能性を示唆している。初期の出会いはデジタルで効率化されつつも、関係を深めるプロセスにおいては、経済的な価値観の合致や、質素なデートへの理解といった要素が、より重要になっているのかもしれない。
さらに、不安定な社会情勢を背景に、パートナーに「生き抜く力」やレジリエンスを求める傾向 3 が強まっている点は興味深い。これは、経済的な不安定さや自然災害への不安に対する心理的な反応とも考えられる。単にロマンチックな魅力や社会的地位だけでなく、困難な状況を乗り越える能力や、実用的なスキル、堅実な金銭感覚といった、より現実的な「信頼性」や「生存能力」が重視されるようになっている可能性がある。これは、従来のステータス指標とは異なる、新たなパートナー評価軸の出現を示唆しているのかもしれない。
3. 婚活サービスのナビゲーション:比較分析
多様化する婚活市場において、自分に合ったサービスを見つけることは成功への第一歩である。ここでは、主要な婚活サービスの種類とその特徴を比較分析する。
3.1 結婚相談所 (Kekkon Sodanjo)
- 特徴: 多くの場合、IBJ 7 のような連盟組織に加盟し、ネットワークを形成している。専任のカウンセラーによるカウンセリング、プロフィール作成支援、相手の紹介(マッチング)、お見合いのセッティング、交際中のフォローアップなど、体系的で手厚いサポートを提供する 10。
- 利用者層: 結婚に対する真剣度が高い個人が集まる傾向がある 7。IBJの例では、年収600万円以上の男性が約半数を占めるなど 7、比較的安定した経済基盤を持つ層が多い。成婚者の平均年齢は女性34歳、男性36歳(初婚の場合)といったデータもある 8。
- 費用: 一般的に、入会金、月会費が必要となり、加えてお見合い料や成婚料が発生する場合が多い。アプリと比較すると高額になる傾向があるが、その分、本人確認や独身証明などの提出が義務付けられていることが多く、信頼性の高い出会いが期待でき、個別サポートも充実している。
- 展開状況: IBJのような全国規模のネットワークを通じて、日本全国でサービスが提供されている 1。自治体が運営する結婚支援センターの中には、結婚相談所の仕組みを参考にしたり、連携したりしているケースもある 11。
3.2 マッチングアプリ (Matching App)
- 特徴: Pairs、Omiai 6、Tinder 14 のような大規模プラットフォームから、特定の層に特化したニッチなアプリ(例:Gorgeous 20、ブライダルネット 7)まで、多種多様なサービスが存在する。利用者が主体的に相手を検索し、コミュニケーションをとるスタイルが基本。
- 利用者層: 20代~30代を中心に、幅広い層に利用されている 5。近年は、明確な結婚意欲を持って利用するユーザーも増加している 2。
- 費用: 結婚相談所に比べて低価格なものが多く、月額定額制が主流(女性無料の場合もある)。より多くの機能を利用できる有料プランが用意されていることも多い。
- 機能・安全性: プロフィール閲覧、スワイプ機能、メッセージ交換が基本機能。サービスによっては、収入証明や職業証明の提出機能 20、AIによるレコメンド機能 3、安全対策機能などを備えている。一方で、利用者の安全確保は依然として課題であり、公的なガイドライン策定やサポート体制強化を求める声もある 21。
- 展開状況: スマートフォンがあれば全国どこからでもアクセス可能であり、婚活市場における主要な勢力となっている 5。
3.3 婚活パーティー・イベント (Konkatsu Party/Event)
- 特徴: 独身者が直接顔を合わせて交流するために企画されたイベント。一度に100名以上が参加する大規模なもの 7 から、趣味、年齢層、職業などを限定した小規模でテーマ性のあるもの(例:「たこやき婚」3、自治体主催の地域密着型イベント 11)まで様々。
- 利用者層: アプリや相談所よりも、直接会って話すことを好む層が参加する傾向がある。イベントのテーマや主催者によって、参加者の属性は大きく異なる。
- 費用: イベントごとに参加費を支払う形式が一般的。一回の出会いの機会としては、比較的安価に参加できる場合が多い。
- 形式・運営: 直接的な交流が可能だが、成果は当日の参加者構成やイベントの進行形式に左右される。民間のイベント会社(例:オミカレ 16)や、NPO、地方自治体などが主催することが多い 15。
- 展開状況: 日本全国で開催されており、地域や目的に応じた多様なイベントが見られる。
これらのサービスを比較検討する際、かつての「相談所=真剣・高額」「アプリ=気軽・安価」「パーティー=対面」といった単純な区分は、もはや実態にそぐわなくなりつつある点に注意が必要である。結婚相談所がAIを含むデジタルツールを導入し 11、マッチングアプリが収入証明などの信頼性向上策を講じ 7、婚活パーティーがより専門的・目的志向的に進化している 3 からだ。利用者は、単にサービスの「種類」で選ぶのではなく、それぞれのサービスが提供する具体的な機能、サポート体制、利用者の真剣度、費用対効果などを、自身のニーズと照らし合わせて慎重に評価する必要がある。
また、多くの選択肢があるにも関わらず、利用者の半数以上が単一のアプリのみを使用しているというデータ 18 は、興味深い示唆を与えている。これは、利用者が選んだプラットフォームに高い満足度を感じている可能性を示す一方で、複数のサービスを比較検討したり、並行利用したりすることに対する精神的な負担感(いわゆる「アプリ疲れ」)が、他の選択肢を探求する意欲を削いでいる可能性も考えられる。もし後者の要因が大きいのであれば、それは市場において、より効果的な単一プラットフォームへの期待、あるいは複数アプリの利用を支援するツールの必要性を示唆しているのかもしれない。いずれにせよ、アプリ利用が一般化 18 した現在においても、その利用体験自体は多くのユーザーにとって依然として労力を要するものである可能性がうかがえる。
表1:日本の婚活サービス比較概要(2025年)
| サービス種別 | 主な手法 | 代表的な費用体系 | 主な対象年齢層 | 主な特徴 | 全国的な利用可能性 |
| 結婚相談所 | カウンセリング、紹介、お見合い | 高額(入会金+月会費+成婚料など) | 30代~40代中心 | 手厚いサポート、本人確認、高い真剣度、成婚へのコミットメント | ネットワークにより高 |
| マッチングアプリ | 利用者主導の検索・メッセージ | 低~中価格(月額定額制、女性無料も) | 20代~30代中心 | 大規模な会員数、手軽さ、多様な選択肢、AI機能、一部で証明機能 | インターネットで高 |
| 婚活パーティー | 対面での直接交流 | 中価格(イベント毎の参加費) | イベントによる | 直接対話、雰囲気重視、テーマ設定(趣味・地域など)、短時間での多数との接触 | 主催者により変動 |
(出典:3に基づき作成)
4. 利用者体験:認識、満足度、課題
婚活サービスの利用者が実際にどのような経験をし、何を感じているのかを理解することは、サービスの有効性を評価し、今後の改善点を探る上で不可欠である。
4.1 利用者の満足度と意識
- 高い関係満足度: 婚活サービスを通じて恋人ができた人は、それ以外の出会い(例:職場、友人紹介など)で恋人ができた人と比較して、現在の恋人との関係に対する満足度が高い傾向にある(婚活サービス経由:71.5%、その他:65.5%)5。
- 満足度の背景: この満足度の高さは、婚活プロセスにおいて、休日の過ごし方、愛情表現の方法といった日常的な事柄から、子ども、住まい、キャリアプランといった長期的な人生設計に関わる重要な項目について、相手とより深く、具体的にすり合わせができていることと関連している可能性がある 5。サービスが提供する構造化された環境が、通常は時間をかけて明らかになる価値観やライフプランに関する対話を、初期段階から促進しているのかもしれない。
- 利用への意識: 前述の通り、マッチングアプリの利用については、友人や知人に話せるという人が約9割に上り、オープンな姿勢が広がっている 18。一方で、婚活サービスを利用していない層の中には、依然としてサービスに対する一定のイメージ(例:最後の手段、費用が高いなど)を持つ人もいるが、否定的なイメージは年々薄れてきている 13。非利用者がサービスの利用を検討するきっかけとしては、「自然な出会いでは難しいと思ったとき」や「一生独身の可能性に不安を感じるようになったとき」、「自分の人生について考えてみたとき」などが挙げられている 13。
4.2 優先順位と判断基準
- 人柄 vs. 見た目: 多くの婚活者が、交際相手や結婚相手に最も重視する点として「人柄」を挙げる 16。しかし、現実の出会いの初期段階においては、「見た目」が相手に興味を持つかどうかの最初の関門(足切りライン)として機能している実態も指摘されている 16。これは、理想として掲げる条件と、実際の第一印象における判断基準との間に乖離があることを示唆しており、特にプロフィール写真などが重視されるアプリ等では、この傾向が顕著になる可能性がある。
- 職業・収入への関心: 特定のサービス、特にハイクラス層をターゲットにしたものでは、相手の職業や収入に対する関心が高い。あるハイクラス向けアプリでは、利用者の75.4%が「出会いたい職業の人に出会えた」と回答し、男性会員の6割以上が職業証明または年収証明を提出済みであった 20。これは、経済的安定性や社会的ステータスを重視する層が存在することを示している。
- 自己投資への意識(性差): 2025年に向けた抱負として、男女ともに「恋人を作る」ことを挙げる人が多い中で、特に女性は「外見の自分磨き」(約半数)や「内面の自分磨き」(約43%)を目標に掲げる割合が男性よりも高い傾向が見られた 22。これは、婚活市場において、女性がより自己改善への意識を高く持っている、あるいは、そのような努力を期待されていると感じている可能性を示唆している。
4.3 よくある障壁と成功戦略
- 成功者の特徴: 婚活サービスを利用して恋人ができた人とできなかった人を比較した場合、成功した人々に共通して見られる特徴として、「前向きな姿勢」が最も多く挙げられている。加えて、「自己理解(自分の価値観や相手に求めることの明確化)」や「相手との価値観のすり合わせ」に関する意識や行動も、成功者の方が高い傾向にあった 5。
- 出会いの機会不足: 婚活を始めるきっかけとして、「日常で異性と接点がない」ことを挙げる人は少なくない 6。現代社会における出会いの構造的変化が、婚活サービスの需要を支える一因となっている。
- 費用対効果の判断: 多様なサービスが存在する中で、それぞれの費用と期待できる効果(出会いの質・量、サポート内容など)を比較検討し、自身にとって最適な選択を行うことは、利用者にとって暗黙の課題となっている。
- 属性による障壁: 男性にとっては、特に40代以降の年齢の壁を乗り越えるためには、収入の高さをアピールするだけでは不十分であり、他の魅力を伝える戦略的な努力が必要となる 7。女性にとっては、外見に対する期待に応えるプレッシャーや、キャリアと家庭の両立に関する悩みなどが障壁となる場合がある。
これらの利用者体験に関する分析から、いくつかの重要な点が浮かび上がる。婚活サービス利用者の関係満足度が高いという事実は 5、これらのプラットフォームが、時にプレッシャーを伴う可能性はあるものの、結婚生活の基盤となる重要な価値観やライフプランに関する初期段階での対話を促進することで、結果的により適合性の高い長期的な関係構築に貢献している可能性を示唆している。通常の関係では避けがちな、あるいは時間をかけて明らかになるような本質的なテーマについて、早期に向き合うことを促す構造が、満足度の高い関係につながっているのかもしれない。
「人柄重視」という理想と、「見た目が第一関門」という現実のギャップ 16 は、パートナー選択における普遍的な人間の傾向を反映している。特に、プロフィール写真が重要な役割を果たすマッチングアプリのようなプラットフォームは、意図せずともこの第一印象への偏重を増幅させ、従来の魅力の基準に合致しない利用者が、内面的な資質に気づいてもらう前に候補から外されてしまうリスクを高める可能性がある。これは、サービス提供者側には、初期段階でも人柄を効果的に伝えられるような機能開発の必要性を示唆し、利用者側には、このバイアスを認識した上で、自身の個性を効果的にアピールする戦略の必要性を示唆している。
そして、婚活の成功が、単なる属性のマッチングだけでなく、「前向きな姿勢」「自己理解」「価値観のすり合わせ」といったマインドセットや対人スキルに大きく左右されるという発見 5 は、極めて重要である。これは、成功のためには、相手を探す技術(どのサービスを使うか、どうアピールするか)だけでなく、自分自身と向き合い、他者と建設的な関係を築く能力(ソフトスキル)が不可欠であることを意味している。したがって、これらの内面的な要素に焦点を当てたコーチングやセミナー、カウンセリングといった支援が、単なるマッチング機能の提供と同等、あるいはそれ以上に、利用者の成功率を高める上で重要な役割を果たす可能性がある。これは、効果的な婚活支援には、よりホリスティック(全体的)な視点が求められることを示唆している。
5. 結婚希望者への公的支援:国と地方自治体の取り組み
少子化が深刻な国家的課題となる中、政府および地方自治体は、結婚を希望する人々への支援を重要な政策課題と位置づけ、様々な取り組みを進めている。
5.1 国の戦略と方向性
- 少子化対策の柱: 国、特にこども家庭庁は、結婚支援を少子化対策の重要な柱の一つと捉えている 24。背景には、2023年の婚姻数が戦後初めて50万組を下回る47万4717組となったことへの強い危機感がある 26。
- ライフデザイン支援: 「若者のライフデザインや出会いの支援」24 を重点項目とし、若者が早期に結婚や出産を含む自身の将来設計について考えるきっかけ作りを後押しする方針である。具体的には、妊娠前の健康管理(プレコンセプションケア)に関する知識普及支援 24 や、若者や専門家からのヒアリングを踏まえた施策の検討が進められている 21。
- 地方への財政支援: 「地域少子化対策重点推進交付金」などの制度を通じて、地方自治体が実施する結婚支援活動(イベント開催、マッチングシステム導入、相談体制整備など)や、結婚に伴う新生活を経済的に支援する「結婚新生活支援事業」(家賃、引越費用等の補助)に対して財政的な支援を行っている 12。
- 環境整備と連携強化: 効果的な支援策を全国に展開するため、地方自治体が取り組みやすいようなガイドラインの策定 26 や、官民連携の強化 21 を目指している。経済的支援(新婚世帯への住居費補助 12、若年層の所得向上策 21)、支援策に関する情報アクセスの改善 21、マッチングアプリの安全性確保 21 なども検討課題となっている。
5.2 地方自治体のプログラム:多様な実践
- 地域差の存在: 結婚支援に対する取り組みの熱意や内容は、都道府県や市町村によって大きな差が見られる 10。内閣府の2021年度調査によれば、福井県、鳥取県、徳島県などが多様な施策を積極的に展開している一方で、千葉県、神奈川県、奈良県(当時)のように取り組み数がゼロの県も存在する 10。多くの市町村レベルでも独自の支援事業が展開されている(例:秋田県内各市町村 29、長野県・岐阜県の一部市町村 30、香川県まんのう町 31、三重県 11、長崎県 11、大分県 11、島根県 11、福岡県うきは市 11 など)。
- 支援拠点の設置: 多くの自治体では、「OITAえんむす部出会いサポートセンター」11 や「みえ出逢いサポートセンター」11 のような専門の支援センターを設置し、相談対応や情報提供、イベント企画などを行っている。これらは、民間の結婚相談所とは異なり、低コストで利用できる「新しい公共型サービス」としての位置づけを目指す場合もある 23。
- 広域連携の推進: より効率的で広範な支援を提供するため、都道府県と市町村、あるいは隣接する自治体同士が連携して事業を実施するケースが増えている 11。お見合いシステムの共同利用や、合同イベントの開催などがその例である。
5.3 提供される支援の種類
地方自治体が提供する婚活支援は多岐にわたる。
- 経済的支援: 主に国の「結婚新生活支援事業」を通じて、対象となる新婚世帯に対し、住居費や引越費用の一部を補助する形で提供される 12。婚活中の男女からは、婚活自体にかかる費用への直接的な経済支援を期待する声も上がっている 32。
- イベント・セミナーの開催: マッチングパーティー、交流イベント、婚活ツアー(例:ワーケーション婚活 15、地域の魅力をPRするイベント 11)などを企画・実施する。また、コミュニケーション能力向上、ライフデザイン設計、あるいは未婚の子を持つ親向けといった、様々なテーマのセミナーも開催されている 11。
- マッチングシステムの提供・改善: 自治体独自の会員制マッチングシステムを導入・運営し、出会いの機会を提供する。近年は、価値観診断などに基づきAIが相性の良い相手を推薦するシステムの導入・改良を進める自治体が増えており、マッチングの質の向上を目指している 11。システムの運用に関わる職員や相談員の研修にも力が入れられている 17。
- 相談・ボランティアネットワーク: 結婚支援センターでの専門相談員による個別相談に加え、「縁結びist」(大分県 11)、「はぴこ」(島根県 11)、「婚活マスター」(京都府 17)といった、地域住民を中心としたボランティアの相談員・仲人を養成し、活用する動きが広がっている。これらのボランティアは、お見合いの仲介、交際中の相談、イベント運営補助など、きめ細やかな「伴走型支援」を担うことが期待されている 11。国も、標準化された研修プログラム(結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム)の活用を推進している 17。オンラインでの相談体制を整備する動きもある 11。
- 情報提供: 結婚、妊娠・出産、子育て、仕事との両立など、ライフステージに応じた情報や、利用可能な行政サービスに関する情報をウェブサイトやパンフレット、セミナー等を通じて提供する 11。
公的支援の現状を見ると、まず、自治体間の取り組みの温度差 10 は、住民がアクセスできる公的婚活サポートの質と量に地理的な不平等を K生じさせている可能性がある。個人の婚活の成否が、居住する地域の自治体の積極性に左右されるという状況は、公平性の観点から課題と言える。国レベルでの支援策が、全ての地域で一定水準のサポートが提供されるよう、どのように働きかけていくかが問われるだろう。
次に、自治体によるAIマッチングシステムの導入拡大 11 は、公的サービスにおける大きな技術的転換点である。マッチングの効率化や質の向上が期待される一方で、個人の価値観といった機微な情報の取り扱いに関するデータプライバシーの問題、アルゴリズムが特定の価値観や属性を無意識に助長してしまうバイアスの問題、そして「相性の良さ」を公的機関がどのように定義し、測定するのかといった倫理的な問いも投げかける。技術導入の恩恵を最大化するためには、透明性の確保と慎重な運用設計が不可欠となる。
そして、AIのような先端技術の活用と並行して、ボランティアによる「伴走型支援」の育成に力が入れられている点 11 は、単なるマッチングだけでは不十分であるという認識の表れであろう。婚活プロセスにおける悩みや不安に寄り添い、励ますといった人間的なサポートの重要性が認識され、地域コミュニティの力を活用しようとする動きが見られる。テクノロジーによる効率化と、人による温かみのある支援を組み合わせたこのハイブリッドなアプローチこそが、公的支援の効果を高める鍵となるのかもしれない。
表2:日本の政府・地方自治体による婚活支援策概要(2025年)
| 支援の種類 | 具体例 | 主な対象者 | 利用可能性に関する注記 | 関連情報源例 |
| 経済的支援 | 結婚新生活支援事業(家賃・引越補助) | 対象となる新婚世帯 | 国の制度に基づき、実施自治体にて申請 | 12 |
| イベント・セミナー | 婚活パーティー、交流イベント、地域PRツアー、ワーケーション婚活、ライフデザインセミナー、親向けセミナー | 結婚希望者、若者、親世代 | 自治体により開催頻度・内容・規模が大きく異なる。ウェブサイト等での告知を確認 | 11 |
| マッチングシステム | 自治体運営の会員制システム、AI活用マッチング | 登録した結婚希望者 | 都道府県・市町村が運営する支援センター等への登録が必要。AI導入は一部自治体 | 11 |
| 相談・ボランティア | 結婚支援センターでの相談、ボランティア仲人(縁結びist、はぴこ等)による紹介・相談、伴走型支援 | 結婚希望者 | センター設置状況、ボランティア制度の有無は自治体による。研修を受けたボランティアが対応 | 11 |
| 情報提供 | 結婚・子育て支援情報、ライフプランニング情報、利用可能な制度案内 | 結婚希望者、若者、住民全般 | 自治体のウェブサイト、広報誌、支援センター窓口などで提供 | 11 |
(出典:27 の情報に基づき作成)
6. 2025年 婚活成功のための戦略的考察
多様化・複雑化する婚活市場において、2025年に結婚という目標を達成するためには、戦略的な視点を持つことが不可欠となる。以下に、成功に向けた考慮事項と具体的な推奨事項をまとめる。
6.1 最適な道の選択:自己分析とサービスのマッチング
まず、自身の性格、価値観、ライフスタイル、そして婚活にかけられる予算や時間を客観的に評価することが重要である。手厚いサポートと確実性を求めるならば結婚相談所、多くの選択肢の中から主体的に相手を探したい、あるいは費用を抑えたいならばマッチングアプリ、直接会って話すことから始めたいならば婚活パーティーやイベント、といったように、自身の優先順位と各サービスの特性(本レポートの表1参照)を照らし合わせる必要がある。一つの方法に固執せず、状況に応じて複数のサービスを組み合わせることも有効な戦略となり得る。
6.2 トレンドの活用:変化する市場への適応
AIによるマッチング提案 3 など、新しいテクノロジーが提供する機会を認識し、利用可能な場合は試してみる価値はあるだろう。ただし、テクノロジーはあくまでツールであり、最終的な判断は自身で行う必要がある。また、「ファミレス恋愛」6 のようなコスト意識の高まりがデートのあり方に影響を与えている可能性を理解し、相手への配慮を示すことも大切である。自身の趣味や関心に合致したテーマ型イベント 3 に参加することは、価値観の近い相手と出会う効率的な方法となり得る。
6.3 期待値の管理:現実認識と自己肯定
婚活市場における年齢や収入といった要素の影響 7 を認識することは重要だが、それに囚われすぎる必要はない。むしろ、自身でコントロール可能な要素、すなわち、前向きな姿勢、自己理解、コミュニケーション能力、そして相手への配慮といった内面的な側面に焦点を当てるべきである 5。外見が第一印象に影響を与える現実 16 を受け止めつつ、自身の個性を効果的に伝える工夫も求められる。焦らず、しかし着実に、自身のペースで活動を進めることが、精神的な消耗を防ぐ上でも重要となる。
6.4 サポートシステムの活用:利用可能な資源の探索
居住する地方自治体が提供している婚活支援プログラム 11 について、積極的に情報を収集することが推奨される。自治体のウェブサイトや広報、あるいは設置されている支援センターに問い合わせることで、イベント、セミナー、相談サービス、マッチングシステムなどの情報を得られる可能性がある。特に、ボランティアによる相談・仲介ネットワーク 11 が整備されている地域では、個別性の高いサポートを受けられるかもしれない。コミュニケーションスキルや自己理解を深めるためのセミナーなどが提供されていれば、積極的に活用したい。
6.5 結論としての推奨事項:行動への指針
2025年に婚活を通じて結婚を目指す個人への具体的なアドバイスとして、以下の点が挙げられる。
- 目標設定の明確化: 自身がどのような結婚生活を望み、パートナーに何を求めるのかを具体的に言語化する。
- 積極性と持続性: 受け身にならず、主体的に行動を起こす。同時に、結果に一喜一憂せず、前向きな気持ちで活動を継続する 5。
- 自己投資: 外見的な魅力向上 16 だけでなく、自己理解を深め、コミュニケーション能力を高めるなど、内面的な成長にも投資する 5。
- オープンなコミュニケーション: 相手との間で、価値観やライフプランについて早期から率直に話し合う姿勢を持つ 5。
- 情報収集と柔軟性: 様々なサービスや支援策に関する情報を常にアップデートし、状況に応じて活動方法を見直す柔軟性を持つ。
2025年の婚活成功は、単一の要因によって決まるものではない。それは、適切な戦略、継続的な努力、そして健全なマインドセットの組み合わせによって達成される可能性が高い。市場のトレンドや利用可能なサポートシステムを理解し、それらを自身の状況に合わせて賢く活用することが、目標達成への道を切り拓くだろう。
特に、多様なサービスやアプローチが存在する現代においては、一つのチャネルに固執するのではなく、複数の手法を組み合わせる「ブレンド型アプローチ」が有効である可能性が高い。例えば、マッチングアプリで出会いの母数を広げつつ、趣味に関連するテーマ型イベントで共通の関心を持つ相手と深く交流し、必要に応じて結婚相談所や自治体のカウンセリングサービスで専門的なアドバイスやサポートを求める、といった形である。各手法の長所を活かし、短所を補い合うことで、より効果的かつ効率的に婚活を進めることができるだろう。
さらに、婚活プロセスは時に精神的な負担を伴うことも事実である。成功者の特徴として「前向きな姿勢」が挙げられていること 5 や、「アプリ疲れ」の可能性が示唆されていることからも、自身の感情的なウェルビーイング(幸福感)を管理することの重要性が浮かび上がる。目標達成のためには、適切な休息を取り、友人や家族、あるいは専門家からのサポートを求め、小さな成功体験を大切にするなど、精神的な消耗(バーンアウト)を防ぎながら持続可能な形で活動を続ける視点が不可欠である。この自己ケアの側面は、しばしば見過ごされがちだが、長期的な視点で見れば、マッチングテクニックと同等に重要な戦略的要素と言えるだろう。
引用文献
- 【婚活のIBJ】2024年の成婚組数が16,398組と過去最多に。 (2025年3月5日) – エキサイトニュース, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2025-03-05-7950-810/
- 【都市部の男性は婚活に有利?!婚活の地域差を公開】都市部に住む男性は成婚率が高く, 4月 13, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000830.000007950.html
- 「2025年の恋愛・婚活トレンド」予測!職場恋愛は、Z世代にとって新鮮⁉ – Ameba News, 4月 13, 2025にアクセス、 https://news.ameba.jp/entry/20250326-57599872
- 婚活実態調査2024|桑原亘之介 – note, 4月 13, 2025にアクセス、 https://note.com/kuwa589/n/n066405c9a36c
- 婚活実態調査 | マーケットを読む・調査データ | リクルートブライダル総研, 4月 13, 2025にアクセス、 https://souken.zexy.net/research_news/lovemaking/konkatsu.html
- 恋愛婚活ラボ 2025年「恋愛・婚活のトレンド予測」、恋愛・婚活も物価上昇を反映した姿に?, 4月 13, 2025にアクセス、 https://news.mynavi.jp/article/20250320-3157773/
- 1万人超の婚活データを分析した『成婚白書 2024年度版』公開!男性は、年収だけでなく「年齢」も重視される傾向が。 | 株式会社IBJのプレスリリース – PR TIMES, 4月 13, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000829.000007950.html
- 2025年4月10日公開!成婚白書2024年度版で見る婚活市場の最新動向 – ベストカレンダー, 4月 13, 2025にアクセス、 https://bestcalendar.jp/articles/press/43557
- 【都市部の男性は婚活に有利?!婚活の地域差を公開】都市部に住む男性は成婚率が高く, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.fnn.jp/articles/-/856337
- 「県内自治体の婚活支援の現状と課題」, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.crinet.co.jp/WordPress/wp-content/uploads/2024/06/20240605.pdf
- 令和5年度 地域少子化対策重点推進交付金 採択事例集 – こども家庭庁, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d92922d1-a79e-4798-bcd6-d2da80498467/53d9572b/20230401_policies_shoushika_koufukin_01.pdf
- 地域少子化対策重点推進交付金 – こども家庭庁, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin
- 婚活実態調査 2024 – リクルート, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240924_marriage_02.pdf
- 結婚と恋愛感情サービス 市場の成長、予測 2025 に 2032 – Pando, 4月 13, 2025にアクセス、 https://pando.life/article/961461
- 【IBJ】行政・自治体向け結婚支援 – 地域社会に根ざし、未来を共に築くお手伝いを!IBJグループのサービスと成婚のノウハウを活かし、行政や自治体と連携し、少子化対策と地域の活性化に取り組んでまいります。, 4月 13, 2025にアクセス、 https://konkatsu-support.ibjapan.jp/
- 2024年婚活・恋活の振り返り、2025年の抱負、見た目についての意識に関する調査リリースを公開いたしました | 株式会社オミカレ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://omicale.co.jp/news/20250128/
- 令和6年度 こども家庭庁行政事業レビュー公開プロセス, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ca6e69f8-26ba-4aed-821b-95831969e310/ba051eeb/20240607_project-review_2024_07.pdf
- 婚活アプリ・マッチングアプリ利用経験者の96%が結婚を意識して真剣に活動 – IBJ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.ibjapan.jp/information/2025/03/24-2.html
- 1万人超の婚活データを分析した『成婚白書 2024年度版』公開 | 株式会社IBJ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.ibjapan.jp/information/2025/04/10-4.html
- 【ゴージャス通信2025年3月】最新恋活・婚活トレンド調査!4人に3人が「出会いたい職業の方と出会えた」と回答!うち6割以上の男性が年収や職業を証明済み! – FNNプライムオンライン, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.fnn.jp/articles/-/842548
- 党青年委 若者の結婚支援へ全力 | ニュース – 公明党, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.komei.or.jp/komeinews/p368316/
- 【オミカレ婚活実態調査】結婚相手は人柄重視!と言いつつ実は”見た目”が足切りライン?第一印象を左右する外見で気を付けたいポイントは? /令和の婚活者が選ぶ「生まれ変わったらなりたい外見の芸能人」も発表 – PR TIMES, 4月 13, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000020019.html
- 一般社団法人 日本婚活支援協会, 4月 13, 2025にアクセス、 https://konkatu.or.jp/
- 【独自】「ライフデザイン」「出会い」政府が“婚活支援”へ 19日に検討会立ち上げ 結婚、出産など若者らにヒアリング – FNNプライムオンライン, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.fnn.jp/articles/-/730526?display=full
- 「異次元の少子化対策」が支援”出会える県の婚活” – 東洋経済オンライン, 4月 13, 2025にアクセス、 https://toyokeizai.net/articles/-/664815
- 「若者のライフデザインや出会いの支援」 こども家庭庁が少子化対策の一環で新たな婚活支援に乗り出す方針 – YouTube, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=X1hOTHQQ-SM
- 少子化対策で政府が婚活支援を検討! – 大薗労務経営事務所-Zono Visa Office-, 4月 13, 2025にアクセス、 https://ork-office.jp/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%A9%9A%E6%B4%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4/
- 地域における結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援事業の 調査研究・効果検証と先進事例 – 内閣府, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.cao.go.jp/yosan/pdf/h28/27010600_naikakufu_kokai_sankou04.pdf
- 【全国掲載】自治体(都道府県・市)が運営・主催する婚活支援サービス一覧 – Next Level, 4月 13, 2025にアクセス、 https://next-level.biz/maripita/category/marriagesupport/
- 【婚活協会】地域情報サイト『Jタウンネット』と全国の自治体向け結婚支援+移住・定住促進を同時にサポートする「移住婚」プロモーションの連携を開始 | 一般社団法人日本婚活支援協会のプレスリリース – PR TIMES, 4月 13, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000044362.html
- 行政の結婚支援事業の現状と課題, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.jcrd.jp/seminar/pdf/images/01-jinzai/01-leader/docu/H27/33mannou.pdf
- 【婚活中男女に聞いた】政府に期待する少子化対策は?1位「教育費用の支援」2位「婚活に関する経済的支援」 | 株式会社TMSホールディングスのプレスリリース – PR TIMES, 4月 13, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000010090.html


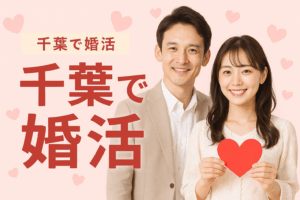
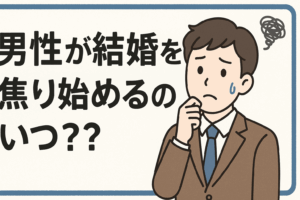

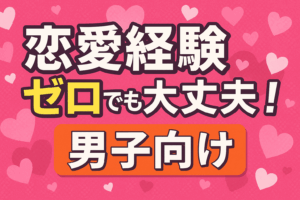
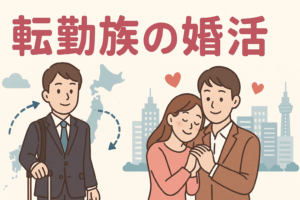

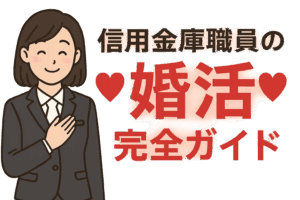

コメント