「年末調整が終わったけど、まだ何か書類を出すの?」「『法定調書合計表』って聞いたことあるけど、何を書けばいいかサッパリ…」
会社や個人で事業をされている皆さん、年末年始の忙しい時期を乗り越えてホッとしている頃かもしれませんが、実はもう一つ、とっても大切な書類の提出が迫っています。それが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(きゅうよしょとくのげんせんちょうしゅうひょうとうのほうていちょうしょごうけいひょう)」、略して「法定調書合計表」です!
この記事では、令和6年(2024年)に皆さんが支払ったお給料や報酬などについてまとめるこの「法定調書合計表」の書き方や出し方について、税金の専門家が、まるで隣で教えてくれるみたいに、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、
- 「法定調書合計表」って、そもそも何なの?
- 誰が、いつまでに出さなきゃいけないの?
- どんなことを書けばいいの?書き方のコツは?
- どうやって税務署に出すの?
といった疑問がスッキリ解消!令和7年(2025年)1月31日までに、全国の税務署へ正しく書類を提出できるよう、お手伝いします。
まずは知っておこう!「法定調書合計表」って、どんな書類?
A. 正式な名前と、その役割って?
この書類の正式な名前は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」。長いですよね!
簡単に言うと、これはあなたが1年間(令和6年分なら2024年1月~12月)に従業員さんに払ったお給料や、弁護士さん・税理士さんなどに払った報酬などについて、「何人に、合計いくら払って、税金はいくら預かりましたよ~」というのをまとめて報告する「表紙」みたいなものです。
あなたが作った色々な「法定調書」(ほうていちょうしょ:例えば、お給料の「源泉徴収票」や、報酬の「支払調書」など、法律で決められた報告書のこと)の、いわば「まとめのサマリーシート」だと考えてください。
この合計表は、それぞれの法定調書(税務署に出す必要があるもの)と一緒に、あなたの会社やお店がある場所の税務署に出します。国(国税庁)が、「この会社は、ちゃんとお給料や報酬を払って、正しく税金を預かっているかな?」というのを、1年分まとめてチェックするための、とっても大事な書類なんです。
B. どんな法律で決まってるの?国からのお知らせは?
「法定調書」や、この「法定調書合計表」を出すことは、所得税法や相続税法といった、国の税金に関する法律でちゃんと決められています。これは、みんなが正しく税金を納めるために、国が「こういう支払いをしたら報告してくださいね」とお願いしているからなんです。
そして、国税庁(国の税金を集めるお役所)は、これらの法律を実際にどうやって守ればいいか、もっと詳しいルールや書き方などを「手引(てびき)」や「通達(つうたつ)」という形でお知らせしてくれています。特に、2025年1月に出す分(令和6年分)については、国税庁が出している「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という本が、一番大事な公式ガイドブックになります。
C. 日本全国どこでも同じ書き方なの?
はい、その通り!この「法定調書合計表」の書き方や書類の形(様式:ようしき)は、国税庁が決めていて、日本全国どこでも同じです。北海道の会社も、沖縄のお店も、東京の事務所も、みーんな同じルールで書きます。
国税庁のウェブサイトから、この書類の用紙(PDFファイル)をダウンロードできるんですが、それも全国共通。インターネットでデータを出す時のルール(文字の入れ方とか)も、全国で統一されています。
これは、国税庁が日本全国のたくさんの会社やお店から、毎年ものすごい数の書類を集めてチェックするので、ルールや形がバラバラだと大変だからなんですね。みんなが同じルールで書類を作ってくれれば、国税庁も効率よく仕事ができるし、私たちも「あっちの地域とこっちの地域でやり方が違う!」なんて混乱しなくて済みます。
【2025年1月31日〆切!】提出のルールを確認しよう!(令和6年分)
A. いつまでに出すの?期限は令和7年1月31日(金曜日)!
令和6年(2024年)に支払ったお給料などに関する法定調書と、この法定調書合計表を税務署に出す締め切りは、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)です。これは絶対に守らなきゃいけない期限!この日までに、あなたの会社やお店がある場所の税務署長さん宛てに提出してくださいね。
B. 誰が出さなきゃいけないの?
基本的には、「法定調書」(例えば、お給料の源泉徴収票や、弁護士さんへの報酬の支払調書など)を作って、相手に渡す義務がある会社や個人事業主の皆さんは、この「法定調書合計表」も出す義務があります。
従業員さんにお給料を払っている社長さん、個人にお仕事を頼んでお金を払っている会社、法律で決められた不動産の取引をした人などが当てはまります。
【ちょこっと注意!】
それぞれの法定調書(源泉徴収票とか支払調書とか)は、払った金額が少ない場合など、「税務署には出さなくていいですよ」というケースがあります。でも、そういう場合でも、この「法定調書合計表」自体は、税務署に出さなきゃいけないことがあるんです!その時は、合計表の「摘要(てきよう)」っていう欄に「出すものはありません(該当なし)」みたいに書いて出すことになります。
これは、国税庁が「法定調書合計表」を、「こういう支払いをする可能性のある会社やお店は、全部把握しておきたいな」と考えているからなんです。だから、特定の法定調書を税務署に出す必要がなくても、「うちは今年、報告する支払いはありませんでした」ということを、この合計表でちゃんと伝える必要があるんですね。
C. どんな法定調書の合計を書くの?主な6種類はコレ!
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という名前の通り、主に以下の6種類の法定調書の情報をまとめて書きます。
【法定調書合計表にまとめる主な法定調書】
| No. | 法定調書の種類(日本語) | どんな書類?(かんたんに) |
| :-: | :———————————————– | :———————————————————————————————————————— |
| 1 | 給与所得の源泉徴収票 | 従業員さんなどに払った1年分のお給料・ボーナスの合計額や、預かった税金(源泉徴収税額)、社会保険料の金額などを書いた紙。 |
| 2 | 退職所得の源泉徴収票 | 会社を辞めた人に払った退職金の金額や、勤めていた年数に応じた控除額(税金が安くなる金額)などを書いた紙。 |
| 3 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 弁護士さんや税理士さんへの報酬、原稿料、講演料など、法律で決められた報酬・料金を払った時に作る紙。 |
| 4 | 不動産の使用料等の支払調書 | 会社や不動産屋さんが、土地や建物を借りた時のお金(家賃とか権利金とか)を払った時に作る紙。 |
| 5 | 不動産等の譲受け(ゆずりうけ)の対価の支払調書 | 会社や不動産屋さんが、不動産を買った時にお金を払った時に作る紙。 |
| 6 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 会社や不動産屋さんが、不動産の売買や貸し借りの仲介をしてくれた人へ手数料を払った時に作る紙。 |
法定調書合計表には、これらの種類ごとに合計額を書くための専用の欄が用意されています。
【令和6年分】書類はどこで手に入れる?どうやって書くの?
A. 最新の用紙(様式)は、国税庁のウェブサイトからゲット!
令和6年(2024年)の支払いについてまとめる法定調書合計表(令和7年1月31日に出す分)の公式の用紙は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。国税庁が出している「手引」にも、ウェブサイトから取ってね、と書いてあります。
とっても大事なのは、必ず正しい年分の用紙を使うこと! 国税庁は、だいたいPDFっていうファイル形式で用紙を用意していて、機械で読み取りやすいOCR対応の用紙もあります。国税庁のウェブサイトで「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」みたいな言葉で検索するのがおすすめです。税務署の窓口でも用紙をもらえるかもしれませんが、ウェブサイトから最新のものをダウンロードするのが一番確実です。
B. 法定調書合計表、どこに何を書くの?ステップ・バイ・ステップ解説!
国税庁が出している「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の31ページから32ページに、法定調書合計表のそれぞれの欄の詳しい書き方が載っています。
主な項目はこんな感じです。
- あなた(支払者)の情報:
- あなたの住所(会社なら場所)、名前(会社なら会社名)、電話番号、マイナンバー(個人事業主の場合)または法人番号(会社の場合)を書きます。
- どんな事業をしているか(事業種目)も書きます。
- 1. 給与所得の源泉徴収票合計表:
- A 俸給、給与、賞与等の総額:
- 人員: 1年間にお給料などを払った人の合計人数(途中で辞めた人も含みます)。
- 支払金額: 1年間に払ったお給料などの合計金額。
- 源泉徴収税額: 預かった所得税と復興特別所得税の合計金額。
- 左のうち、源泉徴収税額のない者: 上の「人員」のうち、税金を預からなかった人の数。
- B 源泉徴収票を提出するもの:
- 税務署に「給与所得の源泉徴収票」を出す必要がある人について、人数、支払金額、源泉徴収税額を書きます。
- A 俸給、給与、賞与等の総額:
- 2. 退職所得の源泉徴収票合計表:
- A 退職手当等の総額:
- 1年間に退職金を払った全ての人の人数、支払金額、源泉徴収税額を書きます。
- B Aのうち、源泉徴収票を提出するもの:
- 税務署に「退職所得の源泉徴収票」を出す必要がある人(主に会社の役員さん)について、人数、支払金額、源泉徴収税額を書きます。
- A 退職手当等の総額:
- 3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表:
- 弁護士さんへの報酬とか、原稿料とか、法律で決められた報酬・料金の種類ごとに、個人に払った分と会社などに払った分に分けて、それぞれ人数、支払金額、源泉徴収税額を書きます。
- 4. 不動産の使用料等の支払調書合計表:
- お金を受け取った人が個人か会社かなどで分けて、人数(件数)、支払金額を書きます。
- 5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表:
- これも、お金を受け取った人が個人か会社かなどで分けて、人数(件数)、支払金額を書きます。
- 6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表:
- これも同じように、お金を受け取った人が個人か会社かなどで分けて、人数(件数)、支払金額を書きます。
- その他の大事な項目:
- 摘要: 何か特別なことがある場合や、税務署に出す法定調書がない時に「該当なし」と書く欄です。
- 翌年以降送付: 税務署から来年以降、この合計表の用紙を送ってもらう必要がなければ「否」に〇をします。
- 調書の提出区分: 初めて出すのか、追加で出すのか、間違って訂選挙げるのか、など、当てはまるものを選んでコード(番号)を書きます。
- 提出媒体: インターネット(e-Tax)で出すのか、CDとかで出すのか、紙で出すのか、出し方によって決まったコードを書きます。
- 税理士番号: 税理士さんがこの合計表を作った場合に、その税理士さんの登録番号などを書きます(書いても書かなくてもOK)。
それぞれの欄には、令和6年(2024年)にあなたが支払った情報をもとに作った、個々の法定調書(源泉徴収票や支払調書)から集計した数字を、正確に書き写す必要があります。
C. ここに注意!よくある間違いと、国税庁からのアドバイス
法定調書合計表を作るときは、とにかく「正確さ」が一番大事!国税庁の「手引」には、こんな注意点が書かれています。
【法定調書合計表を作るときの主な注意点】
| どこで?何に注意? | よくある間違い・気をつけること | どうすればいいの?(国税庁のアドバイス) |
|---|---|---|
| 全体 | 相手に渡す源泉徴収票などにマイナンバーや法人番号を書いちゃう | 相手に渡す控えには、マイナンバーや法人番号は書いちゃダメ! |
| 全体(手書きの場合) | 機械が読みにくいペンで書いちゃう | 機械で読み取るので、黒のボールペンで、丁寧に、ハッキリと書いてね。 |
| 全体(手書きの場合) | 金額を書く欄に「¥」マークとか書いちゃう | マス目がある欄は、マス目の中に丁寧に数字を書いてね。「¥」みたいな記号は書かないで。 |
| 給与所得の源泉徴収票合計表 | 「A」の「左のうち、源泉徴収税額のない者」の欄を書き忘れちゃう | 税金を預からなかった人の人数をちゃんと書いてね。書き忘れが多いみたいなので注意! |
| 給与所得の源泉徴収票合計表 | 年の途中で入社した人の、前の会社の給料の扱い | 「A 俸給、給与、賞与等の総額」の欄には、基本的には前の会社の給料は入れないで、あなたの会社で払った分だけを書く。税務署に出す「B 源泉徴収票を提出するもの」の欄には、前の会社の分も合わせて年末調整した金額を書く。 |
| 給与所得の源泉徴収票合計表 | 年末調整で税金を返しすぎちゃった時 | 年末調整の結果、返しすぎちゃった税金があって、それがあなたの会社が預かっていた税金よりも多い場合は、「源泉徴収税額」の欄には「0(ゼロ)」と書く。 |
| 摘要欄 | 税務署に出す法定調書が何もない場合 | 合計表の「摘要」の欄に「該当なし」と書いて出してね。ただし、インターネット(e-Tax)で「出す義務はありません」と連絡した場合は、出さなくてOK。 |
| 摘要欄 | 特定の不動産の支払調書をまとめて出すから、一部を省略する時の書き方 | 「不動産の使用料等の支払調書」とかの摘要欄に書くことで、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を出さなくてよくなる場合の書き方があるよ。 |
この合計表、書く項目がたくさんあって、数字をまとめるルールもちょっと複雑ですよね。国税庁がこーんなに詳しい「手引」や「書き方」を用意してくれているのも、それだけ分かりにくいってことの裏返し。もし出し忘れたり、間違って書いたりすると、罰金を取られることもあるので、軽い気持ちでやっちゃダメですよ!
だから、この書類作りは「ただの事務作業でしょ?」なんて思わずに、国税庁の最新の案内をよーく読んで、それぞれの欄の意味(特に「A欄:全部の合計」と「B欄:税務署に出す分」の違いとか)をちゃんと理解することが大切です。もし分からなかったら、税理士さんみたいな専門家に相談するのも良い方法ですよ。
どうやって出すの?提出方法いろいろ
A. どこに出すの?あなたの地域の税務署へ
作った法定調書合計表は、関係する法定調書(源泉徴収票とか支払調書とか)と一緒に、あなたの会社やお店がある場所の税務署長さんに出します。会社なら本店がある場所、個人事業主なら住んでいる場所かお店がある場所の税務署ですね。
いくつかの税務署では、郵送で送られてきた書類を、まとめて別の場所(業務センター)で処理していることもあるみたい。もし郵送で出す場合は、送る前に国税庁のホームページとかで「どこに送ればいいのかな?」と確認するのが大事です。
【超重要まちがいポイント!】
お給料の源泉徴収票とほとんど同じ内容で、市役所とか区役所とかに出す「給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)」っていう書類があります。これは税務署じゃなくて、それぞれの市役所とかに出すので、間違えないように気をつけてくださいね!
B. どんな出し方があるの?e-Tax、CD、紙、クラウド…
国税庁は、法定調書合計表と法定調書を出す方法として、主に以下の4つを認めています。
- e-Tax(イータックス): インターネットを使って出す電子申告。事前に使うための手続きが必要です。国税庁は、このe-Taxを使うのを一番おすすめしています。
- 光ディスク等(ひかりディスクなど): CDやDVDにデータを入れて出す方法。事前に税務署のOKが必要なこともあります。
- 書面(しょめん): 印刷した紙に書いて、郵送するか、税務署の窓口に直接持って行く方法。
- クラウドサービス等: 国税庁が認めたインターネット上のサービスを使って出す方法。比較的新しい出し方で、事前に使う契約とか、税務署への届け出が必要です。
どの方法で出すかは、あなたが出す法定調書の枚数や、会社の事務のやり方、パソコンとかの得意度によって変わってくるかもしれませんね。
【法定調書合計表の提出方法くらべてみよう!】
| 提出方法 | どんな感じ? | 主なルール・気をつけること | 強制的にこれじゃなきゃダメな時(後で説明) | 国税庁のおすすめ度・その他 |
|---|---|---|---|---|
| e-Tax(イータックス) | インターネットで出すオンライン提出 | 事前に登録、ID番号をもらう、対応ソフトかe-Taxソフト(WEB版)を使う | ある枚数以上の法定調書を出す義務がある時 | 国税庁イチオシ!便利で24時間いつでも出せる。 |
| 光ディスク等(CD・DVDなど) | 作ったデータをCDとかに入れて出す | 事前にOKをもらう必要があることも。データの形は国税庁が決めたもの(CSVとか)。 | ある枚数以上の法定調書を出す義務がある時 | たくさんのデータを出す時に使う。 |
| 書面(紙) | 印刷した紙に書いて郵送するか持っていく | 国税庁が出している用紙を使う。手書きの時は、機械で読み取るから黒のボールペンでハッキリと。 | 基本的に、電子申告の義務がない時 | 出す枚数が少ない時に使う。 |
| クラウドサービス等 | 国が認めたインターネット上のサービスを使って出す | 認可されたサービスとの契約、税務署に「使います」と届け出る必要あり。 | ある枚数以上の法定調書を出す義務がある時 | 比較的新しい方法。どのサービスが使えるか確認してね。 |
C. 「インターネットで出しなさい!」電子申告の義務って?
法定調書を出す時、「インターネット(e-Tax)か光ディスクで出しなさいよ!」と法律で決められちゃう基準があります。
今のルールだと、2年前(令和4年分)に税務署に出さなきゃいけなかった特定の法定調書(例えば、お給料の源泉徴収票)の枚数が、種類ごとに100枚以上だった場合は、令和6年分の法定調書(令和7年1月に出す分)は、インターネットか光ディスクで出すのが義務になります。
そして、この「100枚以上」という基準は、将来もっと厳しくなる予定なんです!令和9年1月1日以降に出す法定調書(つまり令和8年分から)は、この基準が「30枚以上」に引き下げられます。
これは、国税庁が「もっと税金の手続きをデジタル化したい!」「仕事をもっと効率よくしたい!」「データの分析能力を上げたい!」と強く考えている証拠です。今の100枚基準でも、たくさんの会社がインターネットでの提出に変わってきていますが、30枚に下がると、今まで紙で出していた中小企業の皆さんにも大きな影響が出てきます。
だから、今は100枚未満でも、30枚以上の法定調書を出している会社やお店は、令和9年の変更に備えて、早めにe-Taxの使い方を覚えたり、対応できる会計ソフトに変えたり、税理士さんと相談したりする準備を始めるのがおすすめです。これは、多くの皆さんにとって、税金のルールを守る上で大きな変わり目になるでしょう。
【2025年提出】特に気をつけてほしい大事なこと!
A. マイナンバーと法人番号の扱いは慎重に!
法定調書合計表には、支払者であるあなたが個人の場合はマイナンバー、会社の場合は法人番号を書く必要があります。同じように、それぞれの法定調書(例えば、お給料の源泉徴収票)には、お金を受け取る人のマイナンバーを書く必要があります。
これらの番号の扱いには、とっても厳しいルールがあります。例えば、従業員さんなどに渡す源泉徴収票の「本人に渡す分(控:ひかえ)」には、マイナンバーを書いてはいけないことになっています。
個人情報や会社の識別番号をちゃんと管理することは、国税庁がデータを正しく照らし合わせたり、みんなのプライバシーを守ったりするために、ものすごく大切なんです。
B. もし出し忘れたり、遅れたり、間違えたりしたら…どうなるの?
法定調書合計表を含め、法定調書を出さなかったり、期限に遅れたり、ウソを書いて出したりすると、所得税法などの法律にもとづいて、罰則(罰金や、ひどい場合は懲役)が科される可能性があります。例えば、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」なんていう決まりもあるんです。
国税庁は、これらの書類をちゃんと出すことを、税金の制度を守る上でとっても大事なことだと考えています。わざとじゃない、ちょっとした間違いですぐに罰則!とはならないかもしれませんが、ずっと出さなかったり、わざとウソを書いたりすると、税務署の厳しい調査や、法律的な手続きにつながる可能性が高くなります。
こういう罰則があるってことは、法定調書の作成や提出は、「ただの事務作業でしょ?」じゃなくて、法律的にもすごく重い責任がある行動なんだ、ってことを示しています。だから、会社やお店は、データを集めたり、記録を管理したり、出す前にちゃんとチェックしたりする社内のルールをしっかり作って、「正確に」「期限までに」出すことを一番大事にしなきゃいけないんです。
まとめ:これでバッチリ!最後に確認しておきたいこと
法定調書合計表を令和7年(2025年)1月に出す(令和6年分)にあたって、特に大事なことをもう一度おさらいしましょう!
- 締め切りは絶対守る!: 令和7年1月31日(金曜日)です。
- 正しい用紙を使う!: 令和6年(2024年)の支払いについてまとめる、国税庁が決めた用紙を使いましょう。
- 数字は正確に!: それぞれの法定調書から合計表に書き写す数字は、絶対に間違えないように!
- インターネットで出す義務があるか確認!: 今の「100枚以上」ルールと、将来の「30枚以上」ルールを頭に入れて、あなたの会社やお店がインターネットで出す義務があるか確認して、ちゃんと対応しましょう。
期限までに、正確に出すための【とっておきアドバイス】
- 早めに準備をスタート!: 年末調整が終わったら、すぐに法定調書と合計表を作る準備を始めて、1月のギリギリにならないようにしましょう。
- 公式ガイドブックを必ず読む!: 国税庁が出している最新の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を絶対に参考にしてください。
- 数字はダブルチェック!: 合計表に書く数字は、元の法定調書の合計と合っているか、しっかり確認しましょう。
- 使っているソフトを確認!: 会計ソフトや給料計算システムを使っているなら、それが最新の税金のルールや書類の形に対応しているか確認しましょう。
- インターネット提出の準備も!: インターネットで出す義務がある会社や、将来そうなるかもしれない会社は、e-Taxの使い方や、国が認めたクラウドサービスについて、事前に慣れておきましょう。
- 困ったら専門家に相談!: 複雑なケースや、「これでいいのかな?」と迷うことがあったら、税理士さんみたいな専門家に相談するのも良い方法です。
- 最新情報をいつもチェック!: 国税庁のウェブサイトなどで、提出に関する最後の新しい情報やお知らせが出ていないか、気をつけて見ておきましょう。
これらのことを守れば、法定調書合計表をちゃんと作って出すことができて、税金のルールもしっかり守れますよ!頑張ってくださいね!
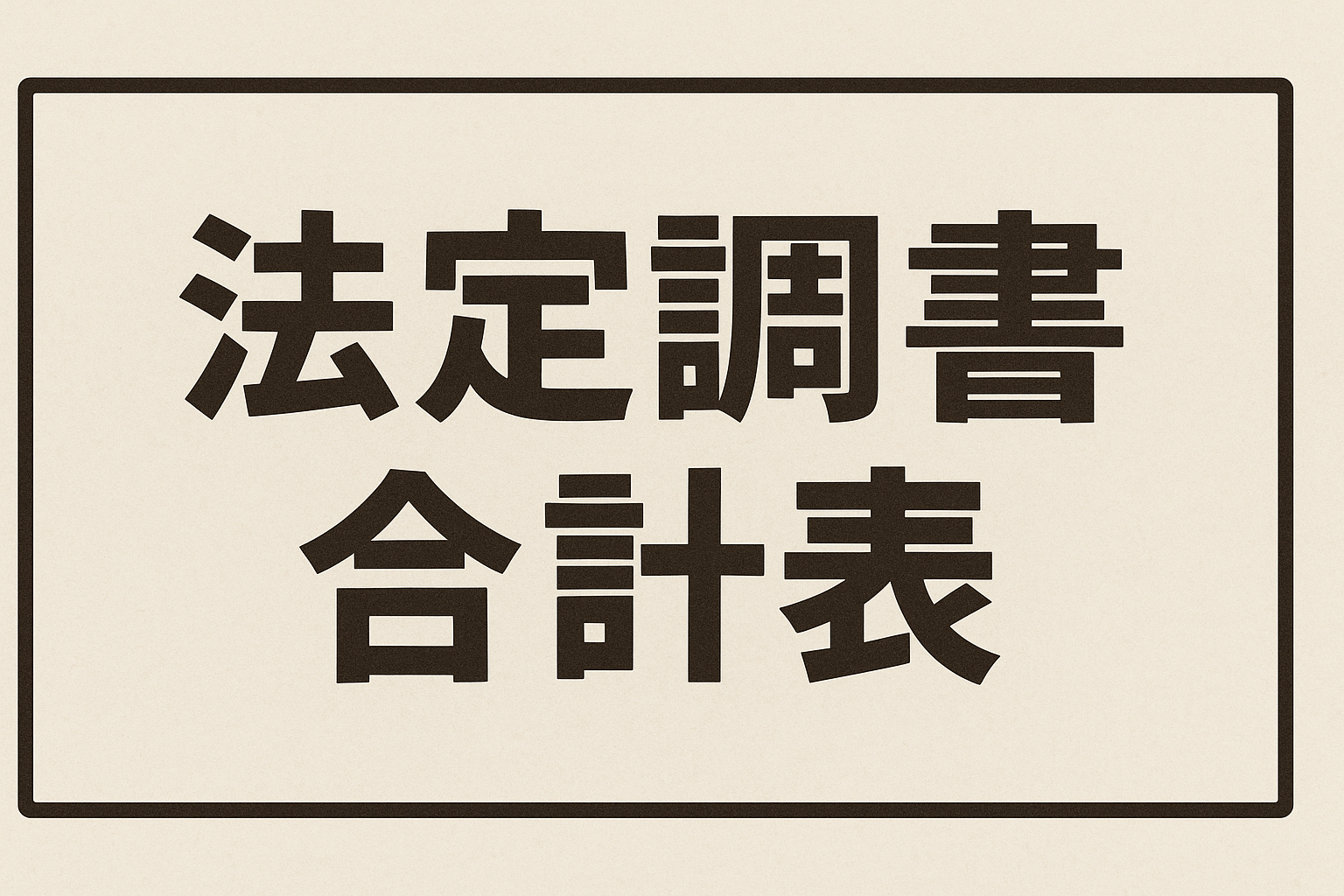

コメント