「日本での生活、仕事と家庭の両立が大変…」「信頼できる家事のサポートがあれば、もっと日本でのキャリアに集中できるのに」そんな悩みを抱える日本在住の外国人の方々へ。実は、一定の条件を満たせば、外国人のあなたが家事使用人を合法的に雇用する方法があることをご存知でしたか?日本の高齢化や女性の社会進出を背景に、家事支援サービスの需要は高まっています。[1] これまで外国人家事使用人の直接雇用には厳しい制限がありましたが、近年、特定の条件下でその受け入れを認める法的枠組みが整備されてきました。[1] 本記事では、日本に住む外国人の方が、家事使用人を合法的に雇うための主要な2つの方法、「特定活動ビザ」による直接雇用と「国家戦略特区制度」の活用について、専門的知見に基づき、分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、複雑な法的要件や手続き、費用、そして雇用主としての責任まで、具体的な情報を得ることができます。あなたとご家族の日本での生活をより豊かに、そしてキャリアをさらに輝かせるための一歩を、一緒に踏み出しましょう!
はじめに:日本で外国人家事使用人を雇うということ
日本で外国人の家事使用人を雇うことは、単に人手を確保するという以上に、出入国管理法や労働関連法規が複雑に絡み合う、専門的な知識が求められる領域です。雇用主となるあなたは、これらの法的要件を正確に理解し、遵守する責任を負います。本稿が、その複雑な制度を理解するための一助となることを目指しています。
特に重要なのが、厚生労働省が公表している「家事使用人の雇用ガイドライン」です。[3] 個人家庭に直接雇用される家事使用人は、労働基準法の大部分の適用が除外される一方で、労働契約法は適用されるという特殊な立場にあります。[3] このガイドラインは、公正な労働条件、明確な雇用契約の締結、安全で尊重される労働環境の確保に関する詳細な推奨事項を示しており、法令遵守はもちろん、良好な雇用関係を築き、維持するために不可欠な指針となります。本稿全体を通じて、このガイドラインの重要性を強調していきます。
それでは、日本で外国人家事使用人を雇用するための主要な2つのルートについて、詳しく見ていきましょう。
選択肢1:「特定活動」ビザによる直接雇用 – 条件と手続きを徹底解説
日本に在留する特定の資格を持つ外国人の方が、外国人家事使用人を直接雇用するための主要な方法の一つが、在留資格「特定活動」の利用です。これは一般的な就労を広範に認めるものではなく、活動範囲が厳格に限定されている点をまず理解する必要があります。[1]
在留資格「特定活動(家事使用人)」とは?
この在留資格は、雇用主である特定の外国人の世帯内における家事労働(掃除、洗濯、料理、育児補助など)に限定して活動することを許可するものです。[6] 他の仕事に従事したり、他の雇用主の下で働いたりすることは固く禁じられています。在留期間は通常1年、6ヶ月、または3ヶ月が付与され、条件を満たせば更新の可能性がありますが、[6] 原則として永住許可には繋がらない点に留意が必要です。[8]
誰が家事使用人を雇えるの?適格な雇用主(スポンサー)の条件
「特定活動」ビザで家事使用人を雇用できるのは、特定の高度な在留資格を持ち、かつ厳格な要件を満たす外国人に限られます。主な対象者は以下の通りです。
- 外交官等(特定活動1号):外交官や領事官などが対象です。[1] 原則として、他に家事使用人を雇用していないことが条件となります。[6]
- 高度専門職(HSP):多くの外国人経営者、研究者、専門家にとって、これが最も現実的な選択肢となるでしょう。
- 雇用主の条件:
- 有効な「高度専門職」の在留資格を保有していること。[1]
- 世帯年収が1,000万円以上であること(HSP本人と配偶者の年収合算可)。[1, 9]
- この制度で雇用できる家事使用人は1名のみ。[1]
- HSP向け2つのサブタイプ:
- 入国帯同型(特定活動2号の2):HSPが日本に入国する前から1年以上継続して雇用しており、一緒に入国(または追って入国)する家事使用人が対象。[1] HSPが日本から出国する際には共に出国することが予定されている必要があります。[1]
- 家庭事情型(特定活動2号):既に日本に住んでいるHSPが、特定の家庭の事情(13歳未満の子の養育、または配偶者が病気等で日常の家事が困難な状況)により家事使用人の必要性を証明できる場合に利用可能。[1] この「家庭の事情」は客観的証拠をもって立証する必要があり、適格性の重要な判断基準となります。この事情が解消した場合(例:子供が13歳に達した)、在留資格の更新が許可されない可能性があります。[10]
- 雇用主の条件:
- 経営・管理ビザ保有者:
- 「経営・管理」の在留資格を持ち、日本における事業所の長(代表取締役など)またはこれに準ずる地位にあること。[7, 9, 13]
- 上記HSPの「家庭事情型」と同様の「家庭の事情」(13歳未満の子、または日常の家事に従事できない配偶者)の要件を満たす必要があります。[7]
- 雇用できる家事使用人は1名のみで、[9] 十分な経済力も求められます。[13]
- 法律・会計業務ビザ保有者:
- 「法律・会計業務」の在留資格を持ち、日本における法律事務所または会計事務所の長などに該当すること。[1]
- こちらも「家庭の事情」の要件を満たす必要があり、[1] 雇用できるのは1名のみです。[1]
- 高度金融人材(特定活動2号の3):特定の金融専門家を対象とした、より新しい専門的なカテゴリーです。[6]
家事使用人自身の適格要件:誰を雇えるの?
上記の雇用主の条件に加えて、雇用される家事使用人自身も以下の要件を満たす必要があります(多くの個人雇用主向け「特定活動」タイプに共通)。
- 年齢:申請時点で18歳以上であること。[1]
- 報酬:月額20万円以上の報酬が保証されていること。[1] この20万円は、家事使用人に支払われるべき最低「現金」給与として扱うことが強く推奨されます。雇用主が住居や食事を提供する場合でも、それを理由に現金給与を20万円未満に減額するべきではありません。この点は、家事使用人の生活を守るための重要な基準です。
- 言語能力:雇用主が家庭内で主に使用する言語で日常会話ができること。[1] 国籍が異なる場合は、語学能力を証明する書類の提出を求められることがあります。[13]
- 業務の専従性:雇用主である特定の外国人の世帯の家事のみに従事すること。他の仕事は固く禁じられています。[1]
- 人数制限:雇用主は、この制度で1名の家事使用人のみを雇用できます。[1]
「特定活動」ビザに関する考察:制度の意図と注意点
この「特定活動」ビザによる家事使用人の雇用制度は、誰でも簡単に利用できるものではなく、特定の高い専門性を持つ外国人材が、家庭内の事情によってキャリアを中断することなく日本で活躍し続けることを支援するための、的を絞った例外的な措置と言えます。特に「家庭の事情」という条件は、単なる利便性のためではなく、真に必要な状況であることを示す重要なフィルターとして機能します。この条件が変化した場合(例:子供の成長、配偶者の回復)、在留資格の更新に影響が出る可能性があることを理解しておく必要があります。[10] また、月額20万円以上という報酬基準は、雇用主にとって相応の経済的負担となりますが、これは家事使用人の生活を保障し、適正な雇用関係を築くための重要な要素です。雇用契約書の作成にあたっては、厚生労働省のモデル雇用契約書の使用も検討しましょう。[10]
申請手続きと主な必要書類:COE申請が基本
海外にいる家事使用人を呼び寄せる場合、通常、まず日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)を申請します。COEが発行された後、家事使用人本人が自国の日本大使館・総領事館でCOEを用いて査証(ビザ)を申請するという流れになります。
主な必要書類は以下の通りですが、必ず事前に最新情報を確認してください。[8]
- 共通:在留資格認定証明書交付申請書、家事使用人の写真、返信用封筒、雇用契約書(業務内容、期間、地位、報酬を明記)。
- 雇用主に関する書類:在留資格証明(在留カードコピー等)、収入証明(HSPは世帯年収1000万円以上を証明する課税証明書等[8])、「家庭の事情」証明(子の出生証明書、配偶者の診断書等[8])、他に家事使用人を雇っていない旨の文書[8]。経営・管理者の場合は地位を証明する会社登記簿謄本等。[17]
- 家事使用人に関する書類:年齢証明(パスポートコピー等)、言語能力証明(必要な場合[8])。「入国帯同型」の場合はHSPとの1年以上の継続雇用証明。[1]
COE申請の審査には通常1ヶ月程度かかるとされていますが、[8] 状況により変動します。制度が複雑であるため、行政書士や入管業務専門の弁護士に相談することを強く推奨します。[8]
次に、もう一つの選択肢である国家戦略特区制度について見ていきましょう。
選択肢2:国家戦略特区プログラム – 事業者を通じた家事支援サービス
「特定活動」ビザによる直接雇用が難しい場合でも、家事支援を受ける方法があります。それが「国家戦略特別区域(NSSZ)プログラム」を活用した、認定事業者を通じた家事支援サービスの利用です。これは、特に女性の就労促進や家事支援ニーズへの対応を目的として、指定された国家戦略特区内において外国人が家事支援サービスを提供することを認める制度です。[18]
国家戦略特区プログラムの概要と目的
この制度は、一般的な入国管理規則の特例として設けられており、第三者管理協議会および認定された特定機関(家事代行サービス事業者)によって運営されています。[18] 利用者(各家庭)は、これらの認定事業者とサービス契約を結び、外国人家事使用人と直接雇用契約を結ぶわけではありません。[19] これが「特定活動」ビザによる直接雇用との大きな違いです。また、この制度下では、家事使用人の住み込みでの就労は原則として禁止されており、家事使用人は認定事業者の従業員として各家庭に派遣される形となります。[2]
「特定活動」ビザによる直接雇用との主な違い
- 雇用関係:利用者は認定事業者の顧客であり、直接的な雇用主としてのビザ発給責任や管理責任を負いません。家事使用人は認定事業者に雇用され、ビザ手続き、研修、労務管理等は全て事業者が行います。
- 利用のハードル:「特定活動」ビザのように雇用主の在留資格や収入による厳格な制限はなく、国家戦略特区内に居住していれば、より広範な層が利用できる可能性があります。
- 規制と監督:第三者管理協議会による監督と、国家戦略特区ガイドラインの遵守が求められます。
利用できる地域と認定事業者
この制度を利用できるのは、指定された国家戦略特区(東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、千葉市など一部地域[18, 21])に限られます。認定されている主な事業者としては、株式会社ダスキン、株式会社ベアーズ、株式会社ニチイ学館(サニーメイドサービス)、株式会社パソナ(クラシニティ)、株式会社ピナイ・インターナショナルなどが挙げられます。[2] これらの事業者は、特定の国(例:フィリピン)から人材を募集し、専門的な研修を提供していることが多いのが特徴です。[2]
サービス内容と費用(事業者による)
提供されるサービスには、通常、掃除、洗濯、料理、買い物が含まれます。[19] 育児支援が提供されることもありますが、家事使用人の日本語能力に関する条件が付く場合があります。[20] 費用は事業者やプラン(定期、スポット、利用時間)によって異なり、多くは時間料金制です。例えば、ニチイ学館のサニーメイドサービスでは、月1回1時間(スタッフ2名)のプランが9,900円から、スポットプランは1回1時間(スタッフ2名)で13,200円からといった料金設定があります(別途交通費)。[2, 33] パソナのクラシニティでは、週1回3.5時間利用の場合、1時間あたり3,900円(税抜)+交通費といった例が見られます。[2, 34] 利用者は通常、清掃用具の提供や光熱費を負担します。[30]
国家戦略特区プログラムのメリット・デメリット
メリットは、利用者の収入や在留資格に関する厳格な要件がなく、家事支援を必要とするより多くの世帯が利用しやすい点です。また、事業者が家事使用人の採用、研修、労務管理を行うため、利用者の負担が軽減されます。一定のサービス品質も期待できるでしょう。
デメリットは、あくまで事業者を通じたサービス利用であり、家事使用人を直接選んだり、細かく指示したりする自由度は低いことです。また、住み込みでの利用は原則できません。[2] そして何より、サービス提供地域が限定されている点が大きな制約となります。
次の章では、家事使用人を雇用する上での法的な義務や注意点について解説します。
雇用主の重要な責任:労働条件、社会保険、税金について
外国人家事使用人を雇用する際には、日本の法律やガイドラインに基づき、雇用主として果たすべき様々な責任が生じます。特に「特定活動」ビザによる直接雇用の場合、契約内容の明確化、適切な労働条件の提供、そして社会保険や税金に関する取り扱いを正しく理解しておくことが、トラブルを未然に防ぎ、良好な雇用関係を築く上で不可欠です。
雇用契約の作成(「特定活動」ビザの場合):書面で明確に!
家事使用人との間で、業務範囲、労働時間、報酬(月額20万円以上を明記)、休日、契約期間、解雇条項などを明確に定めた雇用契約書を作成することが極めて重要です。[3] 厚生労働省の「家事使用人の雇用ガイドライン」では、以下の点が推奨されています。[3, 4]
- 書面による契約:家事使用人が同意すれば電子メールも可。
- 労働時間:1日8時間、週40時間を上限とし、時間外労働は合意の上で限定的に。
- 休日:週に少なくとも1日、または4週間に4日以上(週休2日を目指すことを推奨)。
- 契約期間:最長3年(家事使用人が60歳以上の場合は5年)を推奨。
- 公正な処遇:国籍を理由とする差別的取り扱いの禁止。[35]
- 職務内容の明確化:危険な作業や特別な資格を要する業務(例:医療行為)は避ける。
- 解雇:労働基準法の原則に準じ、十分な予告(例:30日前)または予告手当の支払い。
厚生労働省が提供するモデル雇用契約書の使用も検討しましょう。[10] これは、法的な問題を避けるための良い出発点となります。
労働条件と環境:安全と尊厳を守る
家事使用人が安全かつ健康に働けるよう、適切な労働条件と環境を整えることも雇用主の重要な責務です。厚生労働省のガイドラインでは、以下の点が強調されています。[3]
- 安全な労働環境と適切な用具の提供。
- 適切な業務量と労働時間の管理(記録を推奨)。
- 住み込みの場合:適切な個室、寝具、トイレ・浴室へのアクセス、プライバシーの確保。
- 誤解を避けるため、貴重品は雇用主が管理。
- 家事使用人のパスポートを雇用主が保管しないこと。[35]
社会保険と税金:誰が何を負担する?
社会保険や税金の取り扱いは、雇用形態によって大きく異なります。
- 直接雇用(「特定活動」ビザ)の場合の雇用主(個人家庭):
- 健康保険・厚生年金保険:通常、個人家庭はこれらの被用者保険の「強制適用事業所」とはならず、雇用主が家事使用人を加入させる義務はありません。[4] 家事使用人は原則として自身で国民健康保険および国民年金に加入する必要があります。[41]
- 雇用保険:家事使用人は原則として雇用保険の適用対象外です。[47]
- 労働者災害補償保険(労災保険):雇用主は、家事使用人の労災保険への「特別加入」を検討すべきです。これは、多くの場合、家事使用人が登録している職業紹介所を通じて手続きできます。[3] 加入していない場合でも、業務上の負傷に対して適切な補償を行う道義的責任が生じる可能性があります。[4]
- 所得税・住民税:家事使用人本人が自身の所得税・住民税の支払い責任を負います。通常、個人家庭の雇用主(1人または2人の家事使用人を雇用)は給与からの源泉徴収を行う必要はなく、家事使用人が自身で確定申告を行います。[3]
- 国家戦略特区プログラムの事業者(認定事業者)の従業員の場合: この場合、家事使用人は認定事業者の正規従業員です。したがって、事業者は他の企業の従業員と同様に、雇用する家事使用人を健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入させる責任を負います。[37] これは直接雇用との大きな違いです。
雇用主の届出義務:ハローワークへの届け出を忘れずに
外国人を雇用する事業主(「特定活動」による家事使用人を直接雇用する場合を含む)は、原則として、雇入れ時および離職時に、ハローワーク(公共職業安定所)にその旨を届け出る必要があります。[35] これは、外国人労働者の雇用管理に関する広範な制度の一部であり、忘れずに行いましょう。
次の章では、家事使用人を雇用する際に実際にかかる費用について詳しく見ていきます。
家事使用人の雇用にかかる費用:予算を立てる際の重要ポイント
外国人家事使用人を雇用するには、給与だけでなく、様々な費用が発生する可能性があります。事前にこれらの費用を把握し、しっかりと予算を立てておくことが、後々のトラブルを防ぎ、安定した雇用関係を維持するために重要です。ここでは、主な費用項目について解説します。
必ずかかる費用:給与
「特定活動」ビザによる直接雇用の場合、家事使用人に対して月額最低20万円の給与を支払うことが法的に義務付けられています。[1] これは最も基本的な、そして大きな費用となります。この金額は、あくまで最低基準であり、経験やスキルに応じてこれ以上の金額を設定することも検討しましょう。
場合によってかかる費用:紹介手数料、ビザ申請費用、渡航費など
- 紹介・斡旋手数料:もし、家事使用人を見つけるために人材紹介会社を利用する場合、その手数料が発生します。手数料は紹介会社や契約内容によって大きく異なりますが、一般的には家事使用人の年収の一定割合(例えば20~35%[53])となることが多く、数十万円から百万円を超えるケースも考えられます。
- ビザ申請費用:
- 在留資格認定証明書(COE)の交付申請や、海外の日本大使館・総領事館での査証(ビザ)発給には、それぞれ実費がかかる場合があります(COE申請自体は無料[21])。
- もし、ビザ申請手続きを行政書士などの専門家に代行依頼する場合は、その報酬が必要となります。例えば、高度専門職の家事使用人ビザ申請サポートで137,500円~といった料金例もあります。[57]
- 渡航費:家事使用人が海外から来日する場合、その渡航費を雇用主が負担する必要が生じることがあります。[35] 例えば、マニラから東京への片道航空券は時期や航空会社により約24,000円から60,000円以上、[58] ジャカルタから東京の場合は約20,000円から43,000円以上といった費用感です。[60]
- 生活費(直接雇用で住居・食事を提供する場合の雇用主負担分):月額20万円の給与とは別に、雇用主が住居を提供する場合は、その家賃相当額や光熱費が実質的な雇用主負担となります。厚生労働省のガイドラインでは、住み込みの家事使用人に適切な居住空間を提供することが強調されています。[3] 食事を提供する場合も同様です。
- 保険費用:雇用主が家事使用人のために労災保険の特別加入手続きを行う場合や、万が一の事故に備えて民間の賠償責任保険に加入する場合は、その保険料が必要になります。
- その他の潜在的費用:必要に応じて、家事使用人のための語学研修費用(基本的な会話能力を超えるレベルを目指す場合など[55])、来日時の健康診断費用、[53] 住居の初期設定費用(家具家電など)なども考慮に入れておくと良いでしょう。
国家戦略特区プログラムを利用する場合は、これらの費用の多くは認定事業者が提示するサービス料金に含まれていることが一般的です。事前にサービス内容と料金体系をしっかりと確認しましょう。
家事使用人の雇用は、経済的な負担も伴います。これらの費用を総合的に考慮し、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。次の章では、実際に家事使用人をどのように探せばよいかについて解説します。
家事使用人の探し方:直接雇用と事業者利用、それぞれの方法
日本で外国人家事使用人を雇用したいと考えたとき、具体的にどのようにして適切な人材を見つければよいのでしょうか。主に「特定活動」ビザによる直接雇用を目指す場合と、国家戦略特区プログラムの認定事業者を利用する場合とで、探し方が異なります。それぞれのケースについて見ていきましょう。
「特定活動」ビザ(直接雇用)の場合:信頼できるルートを見つける
ご自身で直接雇用する家事使用人を探す場合、いくつかの方法が考えられますが、信頼性と法的手続きの確実性が重要になります。
- 個人的な紹介や推薦:既に日本で家事使用人を雇用している知人からの紹介や、母国で信頼できる人からの推薦は、安心感のある方法の一つです。ただし、その方が日本の在留資格要件を満たせるかどうかは別途確認が必要です。
- 家事使用人専門の国際人材紹介会社:日本国内または海外には、家事使用人の紹介を専門に行う国際的な人材紹介会社が存在する場合があります。利用する際は、その会社が日本の法律を遵守し、適切な許認可を得て運営されているかを必ず確認しましょう。悪質なブローカーを介してしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
- 行政書士や入管業務専門の弁護士からの紹介:ビザ申請手続きを専門家に依頼する場合、その専門家が人材探しの相談に乗ってくれたり、信頼できる紹介ルートを推薦してくれたりすることがあります。[57] 例えば、コモンズ行政書士事務所は、ウェブサイトでそのようなサービスを示唆しています。[57]
注意点:海外から直接個人的に募集をかける場合、ビザ申請の複雑さや、契約内容の有効性、相手の信頼性などを確認するのが難しくなることがあります。慎重な対応が求められます。
国家戦略特区プログラムの場合:認定事業者にコンタクト
国家戦略特区制度を利用して家事支援サービスを受けたい場合は、話がシンプルです。まず、ご自身の居住地が国家戦略特区の対象エリアに含まれているかを確認します。対象エリアであれば、その地域で活動している認定事業者に直接連絡を取ります。主な認定事業者としては、株式会社ベアーズ、株式会社ニチイ学館(サニーメイドサービス)、株式会社パソナ(クラシニティ)などがあります。[2] これらの事業者は、多くの場合、独自の基準で選考し、専門的な研修を受けさせた外国人スタッフを抱えています。各事業者のウェブサイトなどでサービス内容や料金、利用条件などを確認し、問い合わせてみましょう。
【参考】日本における一般的な外国人向け人材紹介会社について
日本には、様々な分野の外国人材を専門とする一般的な人材紹介会社も多数存在します。[53] 例えば、ウィルテック、ゴーウェル、グローバルパワー、YOLO JAPAN、Daijob.comなどです。ただし、これらの多くは法人向けの採用支援が中心であり、個人家庭向けの家事使用人の紹介に特化しているわけではありません。しかし、外国人材の採用に関する一般的な情報収集や、特定のスキルを持つ人材を探す際の参考として、視野に入れておく価値はあるかもしれません。
次の章では、ここまでの内容を踏まえ、具体的な事例を通じて制度の理解を深めます。
【ケーススタディ】経営管理ビザを持つAさんの場合:家事使用人呼び寄せの実際
これまでの解説を踏まえ、具体的な事例を通じて、外国人が日本で家事使用人を呼び寄せる際のプロセスとポイントを見ていきましょう。ここでは、元記事[7, 13]で触れられているケースを参考に、経営管理ビザを持つAさんが、中国で長年雇用していた家事使用人のDさんを日本に呼び寄せたいと考えた場合を想定します。
Aさんの状況と希望
- Aさんの在留資格:日本の「経営・管理」ビザを保有し、会社の代表取締役として活動。
- 家族構成:6歳のお子さんがいる。
- 希望:中国で長年家事や育児を手伝ってくれていた家事使用人のDさん(中国籍)を、日本での生活をサポートしてもらうために呼び寄せたい。
Dさんを呼び寄せるための分析と課題
- 雇用主(Aさん)の適格性:
- 在留資格:「経営・管理」ビザを保有しており、代表取締役であるため「事業所の長」の基準を満たす可能性が高い。
- 家庭の事情:6歳のお子さんがいるため、「13歳未満の子の養育」という「家庭の事情」の条件を満たしている。
- 経済力:月額20万円以上の給与をDさんに支払える十分な経済力があることを証明する必要がある。
- 人数制限:Dさん以外に家事使用人を雇用していないことが前提。
- 家事使用人(Dさん)の適格性:
- 年齢:18歳以上であると仮定。
- 言語能力:AさんとDさんは共に中国語を母語とするため、日常会話のコミュニケーションに問題はないと推測される。
- 報酬:日本で月額20万円以上の報酬を受け取ることが必須。これが最大の課題となる可能性がある。Dさんの中国での給与がこれに満たない場合、日本での雇用契約ではこの基準をクリアする必要がある。
- 専従性:Aさん世帯の家事のみに従事することが条件。
解決策と結果
AさんとDさんが日本の法的要件を満たすためには、特にDさんの報酬条件の調整が不可欠です。Aさんは、Dさんとの間で新たに日本での就労に関する雇用契約を締結し、月額20万円以上の報酬を支払うことを明確に約束しました。その他の書類(Aさんの収入証明、Dさんとの関係証明、家庭の事情を証明する書類など)も不備なく準備しました。
結果として、これらの準備と適切な申請手続きを経て、Dさんは無事に「特定活動」の在留資格認定証明書(COE)を取得し、日本でAさんの家事使用人として働くことができるようになりました。
この事例から学ぶべき教訓
このケーススタディは、以下の重要なポイントを教えてくれます。
- 全ての基準を満たすことが不可欠:雇用主と家事使用人の双方が、定められた全ての適格性基準(在留資格、家庭の事情、年齢、報酬、言語能力など)を満たす必要があります。
- 既存の雇用条件の調整:特に海外から長年雇用している家事使用人を呼び寄せる場合、日本での法的要件(特に報酬基準)に合わせて雇用契約を見直す必要があります。
- 「家庭の事情」の明確な立証:「13歳未満の子の養育」または「日常の家事に従事できない配偶者」という理由は、客観的な証拠をもって明確に示す必要があります。
- 専門家との連携の有効性:このような複雑なケースでは、早い段階で行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めることが、成功の確率を高めます。
次の最終章では、本報告書のまとめと、外国人家事使用人の雇用を検討している皆さんへの主要な推奨事項をお伝えします。
結論:法令遵守と適切な準備で、外国人家事使用人の円滑な雇用を実現しよう
本稿では、日本に在留する外国人の方が、外国人の家事使用人を合法的に雇用するための主要な2つの方法、「特定活動」ビザによる直接雇用と、国家戦略特区制度の活用について、その法的枠組み、条件、手続き、費用、そして実務上の留意点を包括的に解説してきました。どちらの道を選ぶにしても、日本の法律とガイドラインを正確に理解し、遵守することが不可欠です。
2つの主要な経路の概要を再確認
まず、「特定活動」ビザによる直接雇用は、外交官、高度専門職、経営・管理者、法律・会計専門家といった特定の高いステータスを持ち、かつ明確な家庭のニーズ(13歳未満の子の養育、または日常の家事に従事できない配偶者の存在など)がある外国人を対象とした、非常に選択的な制度です。雇用主と家事使用人の双方に厳格な条件が課せられますが、直接的な雇用関係を築けるというメリットがあります。
一方、「国家戦略特区プログラム」は、指定された特区内において、認定された家事代行サービス事業者を通じて外国人家事支援サービスを利用するものです。利用者の在留資格や収入に関する厳格な制約は比較的少なく、より広範な層が利用しやすい反面、あくまで事業者を通じたサービス利用であり、家事使用人を直接選んだり、住み込みで働いてもらったりすることは原則できません。
法令遵守の徹底が何よりも重要!
外国人家事使用人の雇用を成功させるための最も重要な鍵は、法令遵守の徹底です。以下の点を常に念頭に置いてください。
- 在留資格条件の厳格な遵守:雇用主と家事使用人の双方の在留資格、収入、家庭のニーズ、報酬、業務範囲など、定められた条件を常に満たし続ける必要があります。
- 厚生労働省ガイドラインに沿った雇用契約の締結:特に直接雇用の場合、業務内容、労働時間、報酬、休日などを明確に定めた雇用契約書を作成し、家事使用人の権利を保護することが求められます。
- 社会保険および税務上の義務の理解と履行:雇用形態に応じて、社会保険の加入や税金の取り扱いについて正しく理解し、必要な手続きを行いましょう。
経済的な計画と準備を怠らない
家事使用人の雇用は、月額20万円以上の給与(直接雇用の場合)に加え、紹介手数料、ビザ申請費用、渡航費、生活費(住居・食事提供の場合)など、相応の経済的負担を伴います。事前にしっかりと費用を計算し、無理のない計画を立てることが重要です。
専門家への相談が成功への近道
外国人家事使用人の雇用に関する法的枠組みは複雑であり、解釈や運用が変更される可能性もあります。資格審査の初期評価からビザ申請、雇用契約書の作成に至るまで、円滑かつ法令に準拠した手続きを確保するためには、これらのビザ申請や外国人雇用を専門とする経験豊富な行政書士や入管業務専門の弁護士に相談することを強く推奨します。[8] 専門家のアドバイスは、時間と労力を大幅に削減し、不測の事態を避ける上で非常に有効です。
長期的な視点を持った計画を
家事使用人の在留資格は、多くの場合、更新が必要であり、その更新は当初の条件が維持されているかどうかにかかっています。また、あなた自身の在留資格の変更(例えば、高度専門職の方が永住許可を取得した場合など)が、家事使用人の在留資格に影響を与える可能性があることも忘れてはいけません。[57] 厚生労働省のガイドラインでは、有期雇用契約が5年を超えて更新され、家事使用人が希望した場合には無期雇用契約に転換する可能性についても触れられています。[3] このような長期的な視点も持ちながら、雇用計画を立てることが求められます。
日本での生活がより快適で充実したものになるよう、本記事が外国人家事使用人の雇用を検討されている皆様の一助となれば幸いです。適切な知識と準備をもって臨めば、きっと素晴らしいサポート体制を築くことができるでしょう。
引用文献
本記事の作成にあたり、以下の情報を参考にしました。
- 外国人の家事使用人が日本で働くためには? – 広島のビザ申請・帰化申請支援センター (2025年5月15日閲覧)
- 外国人による家事代行。東京・神奈川・大阪で規制緩和 – グローバル採用ナビ (2025年5月15日閲覧)
- 家事使用人を雇用する際の注意点とは? ガイドラインや知っておきたいポイントを解説 – freee (2025年5月15日閲覧)
- 家事使用人(外交・公用) – 新宿のビザ・帰化申請相談センター (2025年5月15日閲覧)
- 【解決事例】経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法 – 行政書士法人第一綜合事務所 (2025年5月15日閲覧)
- 特定活動「家事使用人」の特徴や申請方法・必要書類など詳しく解説 – さむらい行政書士法人 (2025年5月15日閲覧)
- 特定活動ビザで家事使用人(メイドさん)を雇用したい – 外国人ビザ申請サービス (2025年5月15日閲覧)
- 高度外国人材の家事使用人 | 行政書士深田国際法務事務所 (2025年5月15日閲覧)
- 在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人) – 法務省 (2025年5月15日閲覧)
- 家事支援外国人受入事業 – 神奈川県ホームページ (2025年5月15日閲覧)
- 家事支援外国人受入事業 – 近畿経済産業局 (2025年5月15日閲覧)
- ベアーズの国家戦略特区による家事代行サービス – ベアーズ (2025年5月15日閲覧)
- www.mhlw.go.jp (厚生労働省 外国人雇用状況の届出制度関連資料など) (2025年5月15日閲覧)
- 外国人従業員を雇用したときの手続き – 日本年金機構 (2025年5月15日閲覧)
- 外国人雇用の際に社会保険加入は必要? – マネーフォワード クラウド (2025年5月15日閲覧)
- 雇用保険に加入できない人とは? – 社会保険労務士事務所オフィスつみき (2025年5月15日閲覧)
- 外国人採用にかかる費用とは? – グローバル採用サポネット (2025年5月15日閲覧)
- 高度人材・高度専門職の家事使用人の雇用 – コモンズ行政書士事務所 (2025年5月15日閲覧)
- 航空券価格情報 (例: jp.trip.com, www.expedia.co.jp) (2025年5月15日閲覧)



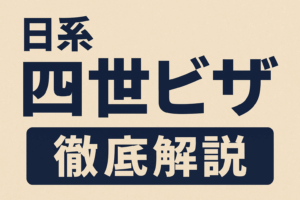

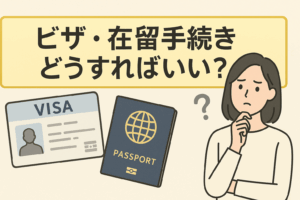




コメント