– 概要:2025年 特定技能外国人支援計画の主要な変更点と実務への影響
本報告書は、2025年4月1日に施行される特定技能外国人(1号)支援計画に関する重要な改正点について分析するものである。今回の改正では、四半期ごとの定期報告から年1回への変更、地域共生施策への協力義務の新設、在留申請書類の変更、運用要領の改訂などが主な内容となっている。これらの変更は、特定技能外国人の受け入れ機関および登録支援機関に大きな影響を与える可能性があり、制度のスムーズな運用のためには、これらの変更点を正確に理解し、適切に対応することが不可欠となる。
– はじめに:特定技能ビザ制度の概要と支援計画の重要性
深刻化する人手不足に対応するため、日本政府は2019年4月1日に在留資格「特定技能」を創設した 1。この制度は、生産性向上や国内人材の確保を図ってもなお人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることを目的としている。現在、介護、ビルクリーニング、製造業、飲食料品製造業、外食業、農業、漁業、建設、宿泊、航空、自動車運送業、鉄道、海運、林業、紙・パルプ製造業、繊維・衣服製造業の16分野が指定されている 2。
特定技能1号の在留資格で日本で働く外国人に対しては、受け入れ機関または登録支援機関が、その日本での安定した就労と生活を支援するための計画(特定技能外国人支援計画)を作成・実施することが義務付けられている 3。この支援計画は、入国前のガイダンスから始まり、住居の確保、生活に必要な契約支援、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談など、多岐にわたる支援内容を包含する。2025年4月1日からの支援計画の改正は、制度の運用効率化、地域社会との共生促進、および受け入れ・支援体制の強化を目的として行われるものである 4。
– 2025年4月1日施行の特定技能制度における主要な改正点
- 受け入れ機関および登録支援機関の報告義務の変更:
- 随時届出(必要に応じた報告): 「受入れ困難の届出」の対象範囲が拡大され、在留資格許可後1ヶ月以内に就労を開始しない場合や、雇用後に1ヶ月以上活動ができない事情が生じた場合も届出が必要となる 5。ただし、自己都合による退職のみの場合は、この届出の対象外となるが、雇用契約終了の届出は引き続き必要である。また、「基準不適合に関する届出」の内容が、従来の出入国または労働関係の不正行為から、特定技能基準省令の各号に適合しない場合に変更される 5。具体例として、税金や社会保険料の滞納、非自発的離職の発生などが挙げられる。さらに、受け入れ機関(自社支援の場合)または登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施が困難となった場合に、新たな届出が必要となる 5。これらの変更は、外国人の就労状況や支援体制の変化をより迅速かつ適切に把握することを目的としていると考えられる。
- 定期届出(定期的な報告): これまで四半期(年4回)ごとに行われていた定期届出の頻度が、2025年4月1日以降、年1回に変更される 5。新たな年次報告の提出期間は、翌年の4月1日から5月31日までとなり、前年の4月1日から当年の3月31日までの受入れ、活動、支援実施状況を報告する 5。なお、2025年1月から3月までを対象とした最後の四半期ごとの定期届出は、2025年4月15日までに従来通り提出する必要がある 5。また、「受入れ・活動状況届出書」と「支援実施状況届出書」が統合され、「受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」(参考様式第3-6号)として一本化される 5。報告内容には、特定技能外国人の年間労働日数や労働時間、支払われた賃金の総額、賃金の昇給率などが含まれ、事業所ごとに個別のシートを作成し、年間労働日数、支払総額、支援実施状況の詳細を記載する必要がある 5。
- 背景と影響: 定期届出の頻度を減らすことで、受け入れ機関や登録支援機関の事務負担軽減が期待される。しかし、年1回の報告となることで、より詳細な情報が求められる可能性があり、日頃からの正確な記録と管理がより一層重要となる。また、随時届出の対象範囲拡大は、問題発生時の迅速な対応を促すとともに、よりきめ細やかな外国人材の管理を求めるものと考えられる。
- 在留申請における手続きと必要書類の変更:
- 申請書への項目の追加: 在留資格申請書(所属機関等作成用)に、地方公共団体からの地域共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力を行う意思があるかどうかを示す項目(項番32)が新たに追加される 6。
- 初回受け入れ時の提出書類の変更: 特定技能外国人を初めて受け入れる場合、外国人本人に関する書類に加えて、受け入れ機関の適格性を証明する書類(登記事項証明書、役員の住民票、労働保険料・社会保険料・国税・法人住民税の納付状況を示す書類、報酬に関する説明書、雇用経緯に関する説明書など)の提出が求められる 5。
- 2回目以降の申請における書類の簡略化: 2回目以降の在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請においては、原則として外国人本人の書類のみで申請が可能となる 5。ただし、審査の過程で必要と判断された場合は、受け入れ機関に関する書類の提出が求められる場合がある。
- 書類省略の要件: オンラインで在留申請を行い、かつ全ての届出を電子的に行っている特定の事業規模の要件を満たす機関については、受け入れ機関の適格性に関する書類の提出が省略可能となる 5。ただし、従来のルールとは異なり、書類の省略にはオンライン申請と電子届出が必須となる。
- 「協力確認書」の提出: 特定技能外国人を初めて受け入れる際、または在留期間更新・変更申請を行う際に、市区町村に対して「協力確認書」を提出することが新たに義務付けられる 4。この書類は、地方自治体の共生施策への協力を約束するものであり、様式は2025年3月下旬に入管庁HPで公表予定である。
背景と影響: 初回受け入れ時の書類提出の厳格化は、悪質な受け入れ機関を排除し、制度の適正な運用を図る目的があると考えられる。一方、2回目以降の申請手続きの簡略化は、継続的な受け入れを行う機関の負担を軽減する。オンライン申請と電子届出の義務化は、手続きの効率化と迅速化を促進する。また、「協力確認書」の提出義務は、外国人材の地域社会への統合をより一層推進する意図が示されている。 - 地域共生社会の実現に向けた地方自治体との連携強化:
- 受け入れ機関および登録支援機関は、地方自治体から共生施策への協力要請があった場合、必要な協力を行う義務が新たに課せられる 4。協力の内容としては、ゴミ出しのルール、防災訓練、日本語教室の案内などを外国人に周知することなどが想定されている。
- 1号特定技能外国人に対する支援計画には、地方自治体の実施する共生施策の内容を踏まえることが求められる 4。具体的には、地域イベントへの案内や日本語教室の活用などが考えられる。
背景と影響: 特定技能外国人の増加が見込まれる中で、彼らが地域社会に円滑に溶け込み、安心して生活できる環境を整備することが重要となっている。この改正は、受け入れ機関だけでなく、地域社会全体で外国人材を支える体制を構築することを目的としている。受け入れ機関は、これまで以上に地域社会との連携を密にし、情報共有や協力体制を構築する必要がある。 - 定期面談のオンライン実施とその他の運用面の変更:
- 受け入れ機関等は、定期的に行う(3ヶ月に1回以上)面談について、対象となる特定技能外国人の同意を得ている場合に限り、オンラインでの実施が可能となる 5。ただし、初回面談は対面で行う必要がある。
- 受け入れ機関による不正行為の類型に、「特定技能外国人の意思表示を妨げる行為または入管法や労働関係法令違反、支援基準不適合に関する事実を隠蔽する目的で必要な記録等を作成しない行為」が追加される 5。
- 登録支援機関が受け入れ機関から委託された支援業務の全部を他の機関に再委託することが禁止される 5。
- 1号特定技能外国人支援計画の基準が強化され、地方自治体の実施する共生施策を踏まえた適切な実施が求められる 5。
- 2025年4月1日より、在留資格の変更許可申請や在留期間更新許可申請などの手数料が改定される 9。
背景と影響: 定期面談のオンライン化は、時間や場所の制約を軽減し、より柔軟な面談の実施を可能にする。不正行為の定義の明確化と再委託の禁止は、制度の透明性と信頼性を高めることを目的としている。支援計画の基準強化は、外国人材への質の高い支援の提供を促す。手数料の改定は、入管手続きの財源確保を目的としたものと考えられる。
– 1号特定技能外国人に対する支援内容の詳細
特定技能1号外国人に対する支援は、義務的支援と任意的支援に分けられる 3。
- 義務的支援: 受け入れ機関が必ず実施しなければならない支援であり、自社で実施できない場合は登録支援機関に委託する必要がある。
- 入国前の事前ガイダンス(雇用契約や日本での活動内容の説明、本人確認を含む)。
- 出入国時の空港等への送迎(出国時は保安検査場前まで)。
- 住居確保に向けた支援(保証人の確保等)。
- 生活に必要な契約に関する支援(銀行口座開設、携帯電話契約等)。
- 在留中の生活オリエンテーションの実施(生活一般、行政手続き、医療機関、緊急時対応、法的保護について8時間以上実施し、確認書に署名が必要)。
- 日本語学習機会の提供(日本語教室、eラーニング、教材の情報提供等)。
- 相談や苦情への対応。
- 日本人との交流促進に関する支援。
- 非自発的離職時の転職支援(必要な行政手続きの情報提供、次の受け入れ機関に関する情報提供、ハローワークや職業紹介事業者の案内、推薦状の作成等)。
- 外国人およびその監督者との定期的な面談(3ヶ月に1回以上)。
- 労働関連法令違反時における行政機関への通報。
- 任意的支援: 義務ではないが、より手厚い支援を提供することで、外国人材の日本での生活や就労の安定に繋がる。例えば、より詳細な事前ガイダンス、住居や契約に関する更なる支援、生活オリエンテーションの充実、日本語学習機会の追加提供などが挙げられる 3。
背景と影響: 義務的支援の内容は、外国人材が日本で安心して生活し、円滑に就労するための基礎となる重要な項目である。任意的支援を充実させることは、外国人材の定着促進や企業イメージの向上にも繋がる可能性がある。
– 2025年計画における申請手続きと必要書類
受け入れ機関が特定技能外国人を受け入れるための一般的な手続きは、まず外国人との雇用契約を締結し、支援計画を作成(または登録支援機関に委託)することから始まる。その後、外国人は技能試験や日本語試験に合格する必要がある(免除要件該当者を除く) 1。在留資格の申請は、外国人本人または受け入れ機関の職員等が行う。2025年4月1日以降は、前述の通り、初回申請時には受け入れ機関の適格性を証明する書類が追加され、申請書には地域共生施策への協力に関する項目が追加される 6。また、在留期間更新等の申請時には、「協力確認書」の提出が求められる 4。申請に必要な書類の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認する必要がある。登録支援機関は、受け入れ機関からの委託に基づき、支援計画の実施や申請手続きのサポートを行う。
– 全国的な支援体制と地域ごとの取り組み
特定技能外国人に対する支援の基本的な枠組みは全国共通であるが、2025年の改正では、地域共生社会の実現に向けて、地方自治体との連携がより一層重視される。地方自治体は、地域の実情に応じた共生施策(日本語教室の開催、地域イベントの案内、生活相談窓口の設置など)を展開することが期待され、受け入れ機関や登録支援機関は、これらの施策に協力し、支援計画に反映させることが求められる 4。したがって、今後は地域ごとの特性に応じた支援の展開がより重要になると考えられる。
– 2025年支援計画と特定技能ビザ要件との関連性
有効な支援計画(または登録支援機関への支援委託)の存在は、特定技能1号ビザ取得の前提条件の一つである。2025年の支援計画の改正は、特定技能ビザに関する規制の改定と密接に関連しており、例えば、地域共生施策への協力は、ビザ申請の手続きや運用要領にも反映される 4。したがって、特定技能ビザの取得および維持のためには、改正後の支援計画の内容を正確に理解し、遵守することが不可欠となる。
– 改正規則下における受け入れ機関および登録支援機関の義務と責任
改正後の規則において、受け入れ機関は、支援計画の策定・実施(または登録支援機関への委託)、報告義務の履行(随時および年次)、地域共生施策への協力、適切な労働環境の整備、記録の作成・保管など、多岐にわたる義務を負う 5。登録支援機関は、委託契約に基づき、義務的支援の提供、支援実施状況の報告、再委託の禁止などの責任を負う 5。これらの義務を怠った場合、罰則や特定技能外国人受け入れの停止、登録支援機関としての登録取り消しなどの処分を受ける可能性がある。
– 結論:主要な変更点のまとめ、関係者への影響、およびコンプライアンスに向けた提言
2025年4月1日に施行される特定技能外国人支援計画の改正は、報告義務の変更、申請手続きの見直し、地域社会との連携強化など、多岐にわたる内容を含んでいる。これらの変更は、受け入れ機関および登録支援機関にとって、制度の理解を深め、新たな対応策を講じる必要性を示唆している。特に、地域共生社会の実現に向けた地方自治体との協力は、今後の外国人材受け入れにおいて重要な要素となる。
コンプライアンスを確保するためには、関係者は以下の点に留意することが推奨される。
- 出入国在留管理庁および厚生労働省が公表する最新の法令やガイドラインを十分に確認すること。
- 新たな報告様式や申請書類の変更点、提出期限などを正確に把握し、社内手続きやシステムを更新すること。
- 地域自治体との連携体制を構築し、共生施策に関する情報を収集し、支援計画に適切に反映させること。
- 特定技能外国人に対する支援体制を見直し、必要に応じて登録支援機関との連携を強化すること。
- 関連する部署や担当者に対して、改正内容に関する研修や情報共有を徹底すること。
これらの措置を講じることで、改正後の制度においても円滑な特定技能外国人の受け入れと支援が可能となり、外国人材と受け入れ機関双方にとってより良い環境が実現することが期待される。
付表
- 報告義務の変更点(2025年4月1日以降適用)
| 報告の種類 | 旧規則(2025年3月31日まで) | 新規則(2025年4月1日から) |
| 定期届出 | 四半期に1回 | 年に1回(4月1日~5月31日) |
| 随時届出(受入れ困難) | 特定の事由に該当する場合 | 対象範囲の拡大 |
| 随時届出(基準不適合) | 出入国または労働関係の不正行為 | 特定技能基準省令への不適合 |
| 随時届出(支援困難) | なし | 新設(受け入れ機関・登録支援機関) |
引用文献
- 介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省 …, 4月 4, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
- 特定技能ビザの必要書類を徹底解説!申請の流れや手続きについても紹介!, 4月 4, 2025にアクセス、 https://tokuty.jp/blog/specified_skilled_worker_required_documents/
- 【2025年版】登録支援機関とは?特定技能外国人支援に関する役割 …, 4月 4, 2025にアクセス、 https://linku-s.com/media/tourokushienkikan/
- 2025年4月施行 特定技能制度改正のポイント ~地域共生に向けた …, 4月 4, 2025にアクセス、 https://aktsouseigroup.com/2025%E5%B9%B44%E6%9C%88%E6%96%BD%E8%A1%8C-%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-%EF%BD%9E%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%85%B1/
- 特定技能制度における運用改善について | 出入国在留管理庁, 4月 4, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
- 【最新情報】2025年4月1日からの特定技能制度の運用改善 – 新潟 …, 4月 4, 2025にアクセス、 https://visa-asocia.com/news/1423/
- 特定技能の申請書式の変更点まとめ(2025年4月より) – RakuVisa, 4月 4, 2025にアクセス、 https://rakuvisa.com/Blog/Article/157/ja
- 特定技能制度|2025年4月からの変更点 – OSAHIROブログ, 4月 4, 2025にアクセス、 https://osahiro.blog/archives/1807
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます – 行政書士山本事務所, 4月 4, 2025にアクセス、 https://gyosei-y.com/blog/2025/03/31/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%81%8B%E7%94%A8%E8%A6%81%E9%A0%98%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%95/
- 法務省出入国在留管理庁「特定技能関係の制度変更」について | 全国民営職業紹介事業協会, 4月 4, 2025にアクセス、 https://www.minshokyo.or.jp/news/2025/03/14/1746.html
- 【速報】2025年4月より開始!特定技能の制度変更点を分かりやすく解説 – SMILEVISA, 4月 4, 2025にアクセス、 https://www.smilevisa.jp/owned-media/tokuteiginou-new-system-change-2025/
- 2025年版 外国人雇用&特定技能ニュース【2025年3月28日更新】, 4月 4, 2025にアクセス、 https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/22006





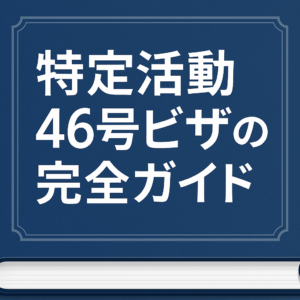
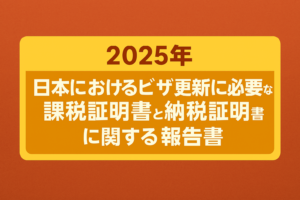
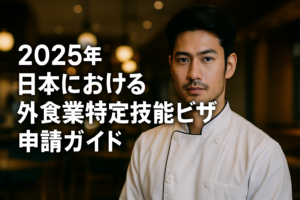
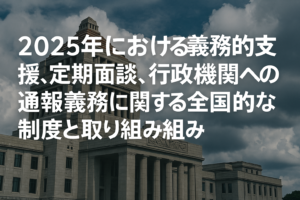

コメント