1. はじめに
日本における人口動態の変化、すなわち出生率の低下と高齢化の進行は、持続可能な労働力の確保と社会統合の促進のために、堅牢な義務的支援システムの必要性を高めています。2025年は、外国人労働者と高齢従業員の両方に影響を与える重要な法的改正が完全に施行される年となります。本報告書は、2025年に日本全国で有効となる義務的支援システムに関する包括的な概要を提供することを目的としており、特にこれらの支援に関する相談および苦情対応メカニズムに焦点を当てます。本報告書では、特定技能外国人および高齢者の雇用に関連する主要な法律および取り組みを分析し、全国レベルのリソースと地域ごとの差異の可能性を特定します。本報告書の対象読者は、労働法を理解し、実施し、労働力に必要な支援を提供する責任を負う事業主、人事管理者、法務専門家、およびその他の関係者です。
2. 2025年における特定技能外国人(特定技能)に対する義務的支援
- 特定技能ビザプログラムの概要: 特定技能ビザプログラムは、特定の分野における労働力不足に対処することを目的としており、これらの労働者に与えられる権利と保護を規定しています。
- 特定技能外国人に対する雇用主の義務(Snippet S1, S8, S49, S50, S51, S52, S61, S64, S67, S82):
- 義務的支援の詳細な内訳:
- 入国前の事前ガイダンスの提供: 雇用契約および日本で行う活動内容に関する情報を提供する必要があります。本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可とされ、在留資格申請前に、当該外国人が理解できる言語で対面またはテレビ電話等で行うことが義務付けられています。これは、外国人労働者が来日する前に、自身の権利や労働条件、日本での生活について正確な情報を理解することを保証するものです。対面またはビデオ通話による説明は、単なる書面による情報提供よりも理解を深め、不安を軽減する効果が期待されます。
- 出入国時の空港等への送迎: 日本への入国時には空港等で迎え、出国時には保安検査場の前まで同行することが義務付けられています。異国の地で初めて空港に降り立つ外国人労働者にとって、このサポートは大きな安心感につながります。また、出国時の保安検査場までの同行は、手続きの不慣れさからくるトラブルを避けるための配慮と言えるでしょう。
- 住宅確保に向けた支援: 保証人の確保など、外国人労働者が住居を確保するための支援を行うことが義務付けられています。日本での住居探しは、言語や文化の違いから外国人にとって困難な場合があります。保証人の確保支援は、賃貸契約を結ぶ上での大きな障壁を取り除く上で不可欠です。
- 生活に必要な契約に関する支援: 銀行口座の開設、携帯電話の契約など、日本で生活するために必要な契約に関する支援を行うことが義務付けられています。これらの契約は、給与の受け取りや日常生活におけるコミュニケーションに不可欠です。雇用主による支援は、これらの手続きを円滑に進める上で重要な役割を果たします。
- 在留中の生活に係るオリエンテーションの実施: 生活一般、行政手続き、外国人対応可能な医療機関、緊急時対応、法的保護について、8時間以上かけてオリエンテーションを実施し、確認書に署名を得る必要があります。これは、外国人労働者が日本での生活に必要な知識を網羅的に習得し、安心して生活を送るための基盤となります。8時間以上の実施と署名による確認は、情報の確実な伝達と理解を促すための措置です。
- 日本語の学習機会の提供: 日本語教室、Eラーニング講座、各種教材の情報提供など、日本語学習の機会を提供することが義務付けられています。言語能力は、職場でのコミュニケーションだけでなく、地域社会への統合においても重要な要素です。学習機会の提供は、外国人労働者の自立を支援する上で不可欠です。
- 相談や苦情への対応: 外国人労働者からの相談や苦情に対して、迅速かつ適切に対応する義務があります。これにより、外国人労働者は安心して働く上で生じる様々な問題や不満を表明し、解決を図ることができます。迅速な対応は、信頼関係の構築にもつながります。
- 日本人との交流促進に関わる支援: 地域社会や職場における日本人との交流を促進するための支援を行うことが義務付けられています。これにより、外国人労働者の孤立を防ぎ、より円滑な社会統合を促すことが期待されます。
- 非自発的離職時における転職支援: 離職時に必要な行政手続きに関する情報提供、次の受入れ機関に関する情報提供、ハローワークや職業紹介事業者の案内、推薦状の作成など、非自発的な離職の場合には転職支援を行うことが義務付けられています。これにより、外国人労働者は不本意な離職後も、速やかに新たな就職先を見つけるためのサポートを受けることができます。
- 外国人及びその監督者と定期的に面談: 3か月に1回以上の頻度で、外国人労働者とその監督者との定期的な面談を実施することが義務付けられています。これにより、外国人労働者の状況を定期的に把握し、問題の早期発見と解決を図ることができます。
- 労働関連法令違反時における行政機関への通報: 労働関連法令に違反する事実があった場合には、行政機関へ通報する義務があります。これは、外国人労働者の権利保護を強化し、労働関連法令の遵守を促すための重要な措置です。
- 義務的支援と任意的支援の区別: 上記の支援は、特定技能1号の外国人に対しては義務とされていますが、特定技能2号の外国人に対しては義務ではありません。この区別は、雇用主が自身の法的義務を理解する上で重要です。
- 不履行の場合の措置: これらの義務的支援を履行しなかった場合には、処罰の対象となる可能性があります。これは、義務的支援の重要性を強調し、雇用主による適切な支援を促すための措置です。
- 支援の外部委託: 雇用主は、これらの支援を登録支援機関に委託することができますが、最終的な責任は雇用主にあります。登録支援機関は専門的な知識や経験を有しており、支援の質を高めることが期待されますが、雇用主も外国人労働者の状況を把握し、責任を果たす必要があります。
- 特定技能外国人向けの全国相談サービス:
- 外国人材在留支援センター(FRESC)(Snippet S7, S10, S69, S70, B1):
- 概要: FRESCは、日本で生活し、活躍する外国人の在留を支援するために、政府の様々な窓口が集約された拠点です。
- 相談窓口: FRESCには、出入国在留管理庁、東京法務局人権擁護部、日本司法支援センター(法テラス)、外務省ビザ情報、東京労働局外国人労働者特別相談・支援室、東京外国人雇用サービスセンターなど、様々な専門機関の相談窓口が設置されています。これにより、外国人居住者は、入国・在留手続きから人権問題、労働問題、法律相談まで、多岐にわたる相談を一つの場所で行うことができます。
- 連絡先: 電話番号は0570-011000、住所は東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階、開館時間は午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)です。
- FRESCのイベント: FRESCでは、外国人留学生や特定技能外国人向けの就職支援セミナーや合同面接会などのイベントも開催されています。これらのイベントは、外国人材の円滑な就職と日本社会への統合を促進する上で重要な役割を果たします。
- 最新情報: 2025年4月1日にFRESCのイベント情報が更新されました。公式ウェブサイトは、最新の情報を得るための重要な情報源です。
- 専用相談窓口(0800-800-7860)(Snippet S6, S44, S45, S46, S47, S48):
- 提供者: この電話番号は、特定技能・登録支援機関手続き相談オフィスやJAC(国際技能協力機構)など、複数の機関で使用されている可能性があります。正確な提供主体については、更なる確認が必要です。複数の機関が同様の電話番号を使用している場合、問い合わせ内容に応じて適切な担当者に繋がる仕組みになっていると考えられます。
- 支援範囲: スニペットの情報に基づくと、この相談窓口は、特定技能制度、ビザ手続き、登録支援機関による支援サービスなどに関する相談に対応しているようです。特定技能外国人やその雇用主にとって、制度に関する疑問や手続きの不明点を解消するための重要な窓口となります。
- 対応言語: スニペットS44では、異なる電話番号ではあるものの、日本語、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語による多言語対応が可能な相談窓口が言及されており、同様のサービスがこの番号でも提供されている可能性があります。
- オンライン相談: スニペットS44では、オンラインツール(Microsoft Teams)を利用した対面相談も受け付けている相談窓口が紹介されており、この番号の相談窓口でも同様のサービスが提供されている可能性があります。
- 外務省ビザ情報: FRESC内には、日本への入国に必要なビザ申請に関する一般的な問い合わせに対応する外務省の窓口があります。
- 東京労働局外国人労働者特別相談・支援室: FRESCには、労働時間、賃金、解雇などの労働問題に直面している外国人労働者向けの相談窓口が設置されています。これは、外国人労働者が安心して働くための重要なセーフティネットとなります。
- 東京外国人雇用サービスセンター: FRESC内には、留学生や高度なスキルを持つ外国人専門家向けの就職支援を行うセンターがあります。
- 日本貿易振興機構(JETRO): JETROは、高度なスキルを持つ外国人専門家の活用を促進するための情報提供を行っています。
- 製造業分野に特化した相談窓口(Snippet S9, S24, S44): 特定技能制度における製造業分野には、多言語対応が可能な専用の相談窓口が設置されています。これは、製造業特有の課題やニーズに対応するためのものです。
- 外食業分野に特化した相談窓口(Snippet S23, S24): 外食業分野で就労する外国人や、受け入れを希望する事業者向けに、農林水産省の補助事業としてJTBが運営する相談窓口があります。
- 建設業オンライン申請サポート(Snippet S11): 直接的な相談窓口ではありませんが、建設分野の特定技能外国人に関するオンライン申請をサポートするポータルサイトが存在します。
- 都道府県レベルの支援(Snippet S24, S27, S68, S69, S71, S72): 秋田県や広島県など、多くの都道府県が外国人向けの相談センターを設置しており、多言語での対応や、仕事や生活に関する様々な相談に対応しています。Snippet S71では、CLAIR(一般財団法人自治体国際化協会)が全国の外国人相談窓口をまとめたポータルサイトを運営していることが示されており、地方自治体レベルでの外国人支援の取り組みが広がっていることがわかります。Snippet S68では、地方自治体がマニュアルの多言語化や相談窓口の設置に対して助成金を提供している事例が紹介されています。Snippet S72では、地方自治体や地域の国際交流協会の相談担当者向けのセミナーが開催されており、相談員の専門性向上への取り組みが見られます。
- 特定技能外国人向けの苦情処理手続き:
- 雇用主の責任: 雇用主は、特定技能外国人からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する義務があります。これには、速やかに話し合いに応じ、必要な助言や指導を行い、適切な行政機関への紹介や同行支援が含まれます。
- 苦情の記録: 全ての相談や苦情は「相談記録書」に記録し、四半期ごとに出入国在留管理庁に提出する必要があります。
- 関係機関への案内: 雇用主は、苦情の内容に応じて、地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係機関を案内し、必要に応じて同行支援を行う必要があります。
- 不当な扱いの禁止: 苦情を申し立てた外国人労働者が、そのことを理由に職場内で不当な扱いを受けないよう、個人情報の保護に努める必要があります。
- 就業時間外の相談対応: 相談対応は、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上、相談しやすい就業時間外にも対応することが求められています。
- 外部支援オプション(Snippet S49, S53, S64):
- 外国人労働者は、地方出入国在留管理局、労働基準監督署、ハローワーク、法務局・地方法務局、警察署、最寄りの市区町村、弁護士会・法テラス、自国の大使館・領事館などの公的機関に直接連絡することも可能です。Snippet S49では、雇用主はこれらの公的機関の連絡先を外国人労働者に知らせておく必要があると明記されています。
- 登録支援機関も、雇用主に代わって相談や苦情に対応することができます。
- 名古屋国際法律事務所のように、外国人労働問題に特化した法律事務所も相談サービスを提供しています。
3. 2025年における高齢者の雇用に関連する義務的支援(高年齢者雇用安定法)
- 65歳までの雇用確保措置の完全義務化(Snippet S2, S3, S4, S16, S17, S20, S22, S59, S76, S78):
- 法律の概要: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)は、高齢者の雇用を促進し、安定させることを目的としています。
- 経過措置の終了: 65歳までの雇用確保措置に関する経過措置は2025年3月末で終了し、2025年4月1日からは完全に義務化されます。これにより、定年年齢を65歳未満としている企業は、希望する従業員全員が65歳まで働けるようにするための措置を講じる必要があります。
- 雇用主の義務: 雇用主は、65歳までの雇用を確保するために、定年年齢を65歳に引き上げる、定年制度を廃止する、または65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入するいずれかの措置を講じる必要があります。
- 70歳までの就業確保の努力義務: 2021年の改正により、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置(定年引上げ、定年制の廃止、継続雇用制度の導入、業務委託契約の締結、社会貢献事業への従事機会の提供)を講じることが企業の努力義務となっています。これは2025年には義務ではありませんが、高齢者の就業促進に向けた政府の方向性を示すものです。
- 再雇用基準への影響: 改正前の法律に基づき再雇用対象者の選別基準を定めていた企業は、2025年までその選別基準を適用することが可能です。しかし、改正前に選別基準を定めていなかった企業については、2013年4月以降、原則として希望者全員の65歳までの雇用が義務付けられています。
- 高齢者向けの全国相談サービス:
- ハローワークの「生涯現役支援窓口」(Snippet S31, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S57):
- 概要: 全国約300か所のハローワークに、概ね60歳以上の求職者を対象とした「生涯現役支援窓口」が設置されています。
- 相談内容: これまでの就労経験や年金の受給状況などを踏まえ、個々のニーズに合わせた職業相談・職業紹介、職場見学・面接会・セミナーの紹介、公共職業訓練の受講あっせんなどが行われています。Snippet S38では、キャリア相談、職業訓練、求人情報の提供など、幅広いサポートが行われていることが示されています。Snippet S36では、シルバー人材センターに関する情報提供や、年金と就労の関係に関する相談も行われていることがわかります。
- 求人開拓支援: 高齢者の採用に意欲的な企業の求人情報を提供し、企業に対しても高齢者向けの求人作成方法などのアドバイスを行っています。
- シルバー人材センターとの連携: シルバー人材センターと連携し、軽易な就業に関する情報も提供しています。
- セミナー例: 生涯設計に関するセミナーなども開催されています。
- ハローワークの一般サービス(Snippet S28, S30, S57): 高齢者は、「生涯現役支援窓口」だけでなく、全国のハローワークで一般的な職業相談、職業紹介、雇用保険に関するサービスも利用できます。
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)(Snippet B3): JEEDは、高齢者を雇用する企業と、就職を希望する高齢者双方に対して、相談・支援サービスを提供しています。「70歳雇用推進プランナー」や「高年齢者雇用アドバイザー」による相談・助言、計画策定支援、研修サービス、企業診断システムなどを提供しています。
- 都道府県レベルの相談(Snippet S30, S32, S73, S74, S75): 山口県のように、都道府県労働局やハローワークが連携して、高齢者の雇用に関する相談窓口を設置している場合があります。愛知県では、「就職支援の出張相談会」として、県内各地の市町村役場などで相談会を実施しています。Snippet S32では、仕事や生活に困っている場合は、地方自治体の相談窓口に相談するよう促しており、高齢者も対象となる可能性があります。Snippet S75では、厚生労働省のウェブサイトで、高齢者の活用を検討している事業者向けの相談窓口が案内されています。
- 高齢者向けの苦情処理手続き:
- 労働基準監督署(Snippet S39, S40, S41, S42, S43, S64): 未払い賃金、不当解雇、その他労働基準法違反に関する問題(定年や再雇用に関する問題を含む)について、労働基準監督署に苦情を申し立てることができます。Snippet S39とS40では、労働基準監督署が対応できる主な事例として、賃金不払い、残業代未払い、最低賃金違反、有給休暇の不取得などを挙げています。Snippet S42では、高齢者の雇用に関するルールも労働基準監督署の管轄であることが示唆されています。
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(Snippet S28, S40, S41, S63): 雇用における差別、ハラスメント(年齢に基づくものを含む)、高年齢者雇用安定法に関する問題などについては、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談することができます。Snippet S40では、これらの部署が男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などに関する問題解決を支援していることが示されています。
- 総合労働相談コーナー(労働基準監督署内)(Snippet S30): 労働基準監督署内には、より広範な労働問題に関する相談を受け付ける「総合労働相談コーナー」が設置されています。
- 行政苦情相談(Snippet S55): ハローワークのサービスを含む、政府のサービスに関する苦情や相談は、「行政苦情110番」または地方の行政相談センターに申し立てることができます。
- 弁護士への相談(Snippet S21): より複雑な法的問題については、労働法を専門とする弁護士に相談することも可能です。Snippet S21では、高齢者雇用に関するトラブルの相談料や、解雇トラブルの際の弁護士費用について言及されています。
4. 2025年におけるその他の潜在的に関連する義務的支援システム
- 雇用主の育児支援義務(育児・介護休業法改正)(Snippet S4, S59, S60, S62, S63, S78, S79, S80, S81):
- 柔軟な働き方の実現: 改正育児・介護休業法により、育児を行う労働者に対する支援が強化され、情報提供や相談体制の整備などが義務付けられます。Snippet S79とS81では、3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に対して、始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与など、5つのうち2つ以上の柔軟な働き方を選択できるように措置することが義務付けられることが示されています(2025年10月から)。
- 柔軟な働き方の提供義務: 2025年10月からは、企業は、始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、保育施設の設置運営などの中から2つ以上を選択し、労働者が利用できるようにする必要があります。
- 子の看護休暇の拡充: 子の看護休暇の対象が小学校3年生までに拡大され、子の行事参加などでも取得可能になります。
- 育児のためのテレワークの努力義務: 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課されます。
- 個別意向確認の義務化: 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務付けられます。
- 相談体制の整備: 育児休業や介護両立支援制度に関する相談窓口の設置が義務付けられます。Snippet S63では、山口労働局が仕事と育児・介護の両立支援制度に関する相談窓口を設置していることが紹介されています。
- 妊婦等に対する相談支援: 妊婦とその配偶者に対する情報提供や相談、経済的支援も制度化されます。
- 介護者支援(介護)(Snippet S59, S60, S62, S63, S81): 育児と同様に、改正法では、家族の介護を行う従業員への支援も強化され、介護休業や介護両立支援制度に関する情報提供や相談体制の整備が義務付けられます。Snippet S60では、介護離職防止のための雇用環境整備として、研修の実施、相談体制の整備などが義務付けられることが示されています。
- 顧客からのハラスメント対策(カスハラ対策)(Snippet S18, S65): 直接的な従業員支援ではありませんが、顧客からのハラスメント防止への注目が高まっており、将来的に法的義務が生じる可能性があり、その際には従業員向けの相談・苦情処理メカニズムの設置が必要となる可能性があります。Snippet S18では、顧客からのハラスメント対策に関するガイドラインが示されており、相談窓口の設置などが推奨されています。Snippet S65では、2025年に顧客からのハラスメント対策が義務化される見込みであると述べられています。
5. 政府省庁および地方自治体の役割
- 厚生労働省:
- 監督と実施: 高齢者の雇用および特定技能外国人プログラムに関連する労働法の策定と執行を担当する主要な政府機関です。
- 情報提供: これらの法律および関連する支援システムに関する広範な情報とリソースをウェブサイトで提供しています。
- 相談サービス: 相談ホットラインを運営し、「生涯現役支援窓口」や「外国人労働者向け相談ダイヤル」などの取り組みを支援しています。Snippet B4は、厚生労働省が「外国人労働者向け相談ダイヤル」を運営していることを確認しています。
- 補助金プログラム: 高齢者の雇用を促進し、外国人労働者を支援する企業に対して補助金を提供しています。
- 法務省/出入国在留管理庁:
- 特定技能外国人プログラムの管理: 特定技能ビザプログラム全体の管理、規制の設定、ビザ申請の処理を担当しています。
- 外国人材在留支援センター(FRESC): 外国人居住者に対する包括的な支援を提供するために、出入国在留管理庁の下に設置されました。
- 執行: 出入国管理法の遵守を監督し、外国人労働者の地位と活動に関連する問題を取り扱います。
- 経済産業省:
- 分野別支援: 製造業など、特定技能外国人プログラムの特定の分野に関連する取り組みに関与しています。Snippet S9は、製造業分野における特定技能外国人材制度に関するポータルサイトを示しています。
- 国土交通省:
- 分野別支援: 建設業や宿泊業など、特定の分野における特定技能外国人プログラムを監督しています。
- 地方自治体:
- 支援の地域差: 全国的な枠組みが存在する一方で、地方自治体は、それぞれの管轄区域内で外国人居住者や高齢者に追加の、または調整された支援サービスを提供している場合があります。
- 相談センター: 多くの都道府県および市町村が、独自の外国人相談センターを運営しています。Snippet S71は、全国の外国人相談窓口のポータルサイトを示しています。
- 高齢者雇用支援: 地方自治体は、高齢者の就職支援プログラムを実施し、相談を提供している場合があります。
- 国との連携: 地方自治体は、ハローワークなどの国の機関と連携して、雇用支援サービスを提供することがよくあります。
6. 2025年の法的改正の影響
- 65歳までの雇用確保措置の完全義務化(2025年4月): これは、定年年齢を65歳未満としている企業に大きな影響を与え、希望する従業員の継続雇用を確保するための措置の実施を義務付けます。
- 育児・介護休業法の改正(2025年4月および10月): これらの改正により、育児および介護を行う従業員を支援するための雇用主の義務が新たに導入され、相談体制の確立や柔軟な働き方の提供などが含まれます。
- 雇用保険制度の変更(2025年4月および10月): これには、高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ(15%から10%へ)、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の創設、教育訓練休暇給付金の創設が含まれます。
- 特定技能外国人に関する報告義務の変更(2025年4月): 受け入れ機関による定期報告の頻度が、3か月に1回から年1回に削減されます。
- 特定技能外国人に関する不当な行為の範囲の拡大(2025年4月): 外国人労働者の意思表示の妨害、不当な転職・退職の制限、相談窓口への報告の妨害などが、新たな不正行為として追加されます。
- 特定技能外国人に関する地方自治体との連携義務(2025年4月): 受け入れ機関は、外国人労働者の居住地の地方自治体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
7. 結論
2025年には、日本において、特に特定技能外国人および高齢従業員を対象とした包括的な義務的支援システムの枠組みが整備されます。FRESCやハローワークの「生涯現役支援窓口」などの全国レベルの相談サービスは、重要なリソースを提供します。苦情処理メカニズムは、主に既存の労働および入国管理当局を通じて処理され、雇用主の責任と文書化の重要性が高まっています。企業は、65歳までの雇用確保措置の完全義務化、育児・介護支援に関する新たな義務、および特定技能外国人に関する変更点を認識する必要があります。最も正確で最新の情報については、厚生労働省、出入国在留管理庁、および関連する地方自治体の公式ウェブサイトを参照することが不可欠です。企業は、2025年に施行される規制を遵守し、必要な支援を効果的に提供し、相談や苦情に適切に対応できるよう、事前に方針と慣行を見直す必要があります。
結論セクションの貴重な表:
| 支援分野 | 組織 | 主な連絡先 |
| 特定技能外国人 | 外国人材在留支援センター(FRESC) | 電話:0570-011000;住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階;ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html |
| 専用相談窓口(可能性としてOffice Lotus/JAC) | 電話:0800-800-7860(正確な範囲と公式な地位についてはさらなる確認が必要) | |
| 地方出入国在留管理局 | 連絡先は地域によって異なります。出入国在留管理庁のウェブサイトからアクセスできます:https://www.moj.go.jp/isa/ | |
| 労働基準監督署 | 連絡先は地域によって異なります。厚生労働省のウェブサイトからアクセスできます:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html | |
| 高齢者の雇用 | ハローワークの「生涯現役支援窓口」 | 連絡先はハローワークによって異なります。お近くのハローワークは、厚生労働省のウェブサイトから検索できます:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) | ウェブサイト(英語):https://www.jeed.or.jp/english/;ウェブサイト(日本語):https://www.jeed.or.jp/ | |
| 労働基準監督署 | 連絡先は地域によって異なります。厚生労働省のウェブサイトからアクセスできます:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html | |
| 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) | 連絡先は都道府県によって異なります。厚生労働省のウェブサイトからアクセスできます:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kintou/madoguchi/index.html |
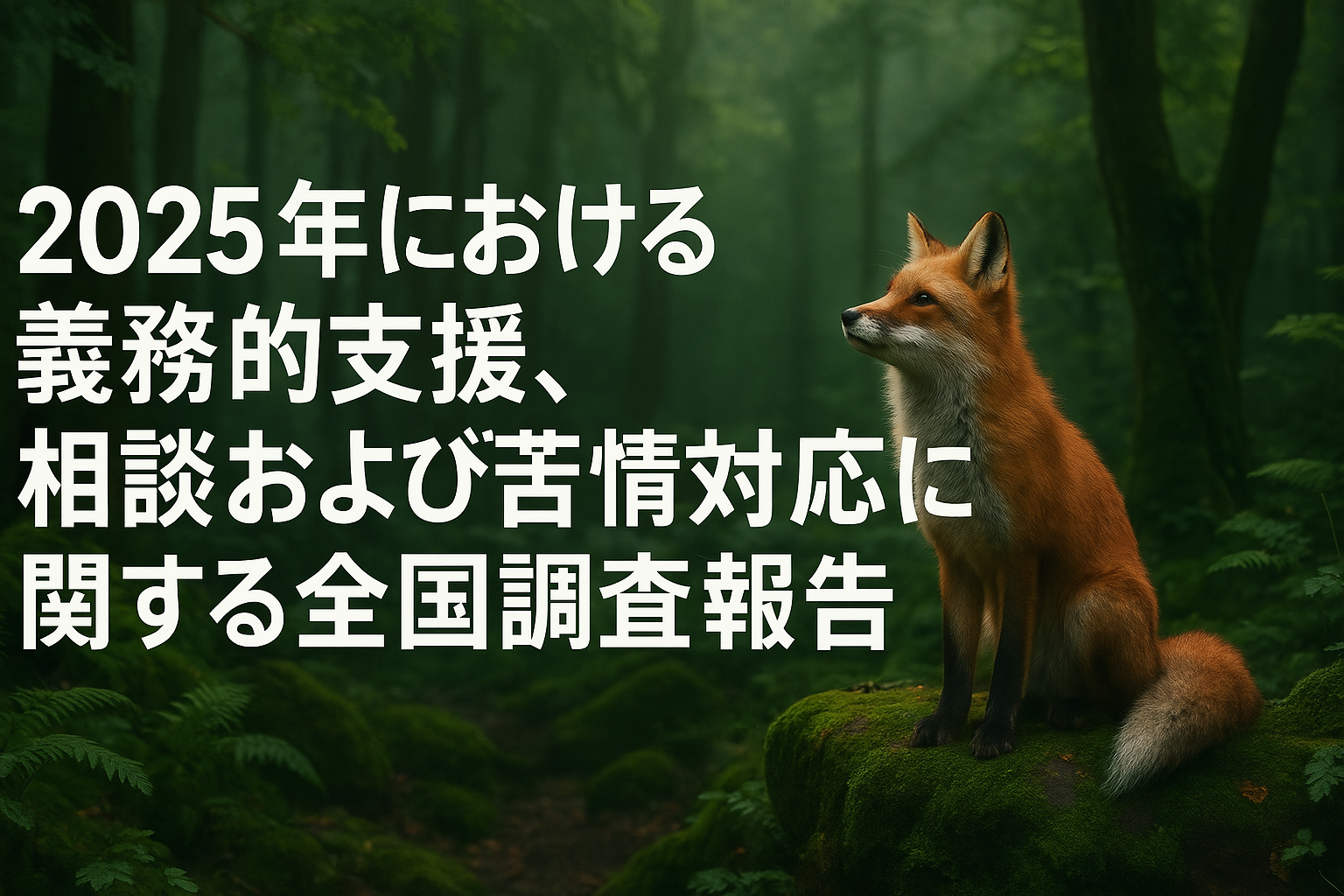
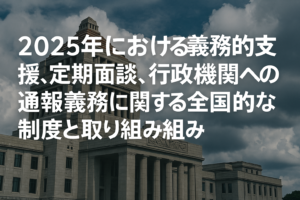


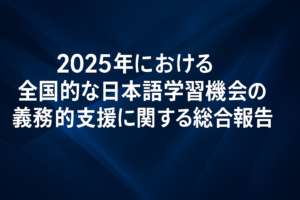
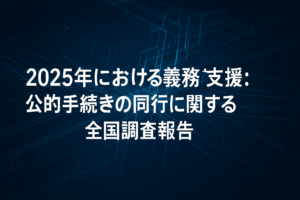
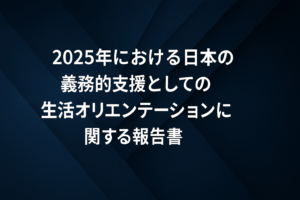

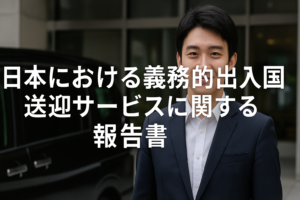
コメント