1. 登録支援機関制度の概要
日本における特定技能ビザは、国内の特定の産業分野における深刻な労働力不足を解消するために創設されました1。このビザには、特定技能1号と特定技能2号の2つのカテゴリーが存在しますが、登録支援機関が主に関与するのは、より幅広い分野を対象とする特定技能1号です3。特定技能1号の外国人労働者は、一定の日本語能力と技能水準を持つことが求められています1。
登録支援機関(登録支援機関)は、この特定技能1号の外国人労働者が日本で安定かつ円滑に就労し生活できるよう、様々な支援を提供する役割を担う機関として、日本政府(出入国在留管理庁)によって認可されています3。受け入れ機関(雇用主)自身がこれらの支援を提供することも可能ですが、多くの場合、特に十分な内部リソースや専門知識を持たない企業にとっては、登録支援機関への委託が一般的です3。登録支援機関として登録されるためには、組織体制、外国人支援の経験、法令遵守状況など、一定の要件を満たす必要があります5。
これらの支援サービスの重要性は、外国人労働者が日本の社会や職場に円滑に適応するために不可欠であるという点にあります2。適切な支援は、外国人労働者の仕事への満足度を高め、離職率を低下させ、受け入れ機関と労働者の双方にとってより良い結果をもたらす可能性があります。特定技能制度の長期的な成功と持続可能性にとって、効果的な支援サービスの提供は重要な要素となります。
2. 法的枠組みと義務
登録支援機関制度は、法務省出入国在留管理庁が主に管轄しており2、労働条件や雇用に関しては厚生労働省も関与しています1。両省庁が連携して制度を運営していることは、外国人労働者の入国と労働の両面を包括的にサポートする体制を示唆しています。
特定技能1号の外国人労働者に対する義務的支援(義務的支援)の提供は、受け入れ機関(自ら支援を行う場合)と登録支援機関(支援を委託された場合)の両方に法的に義務付けられています3。この義務を怠った場合、登録支援機関の登録取り消しや、受け入れ機関が特定技能外国人を受け入れる資格を失うなどの罰則が科される可能性があります3。この法的義務と罰則の存在は、日本政府が外国人労働者への適切な支援を非常に重視していることを示しています。
一方、任意的支援(任意的支援)は、法律で義務付けられているわけではありませんが、外国人労働者の円滑な社会生活と職業生活のために有益であると考えられています3。ただし、任意的支援の内容が支援計画に記載された場合、その支援の提供は義務となります3。この点は、支援計画の策定にあたり、任意的支援の内容を慎重に検討する必要があることを示唆しています。
3. 2025年における義務的支援の詳細分析
2025年において、登録支援機関および受け入れ機関が特定技能1号の外国人労働者に対して提供することが義務付けられている支援は、以下の10項目です4。
| 支援項目 (日本語/英語) | 具体的な要件 | 2025年の変更点/新規規定 |
| 事前ガイダンス (Pre-departure Guidance) | 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無等について、対面またはテレビ電話等で説明を行うこと 4。 | 特になし |
| 出入国する際の送迎 (Pick-up and Drop-off Upon Entry and Departure) | 入国時に空港等から事業所または住居まで送迎し、帰国時には空港の保安検査場まで送迎・同行すること 4。送迎にかかる交通費は受け入れ機関が負担すること 11。一時帰国に対して送迎義務は発生しない 11。 | 登録支援機関が車両を用いて送迎を行う場合、道路運送法に違反しない具体例などが追記される 7。 |
| 住居確保・生活に必要な契約支援 (Securing Housing and Support for Necessary Contracts for Daily Life) | 連帯保証人になる、社宅を提供するなど住居の確保を支援すること。銀行口座開設、携帯電話やライフラインの契約手続きなどを案内・補助すること 4。 | 特になし |
| 生活オリエンテーション (Daily Life Orientation) | 日本での生活に必要なルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などを、外国人が十分に理解できる言語で説明すること 4。8時間以上実施し、質問に回答できる体制を整え、受講確認書に署名を得ること 11。必要に応じて定期面談時に実施することも可能 11。 | 特になし |
| 公的手続等への同行 (Accompanying for Public Procedures, etc.) | 必要に応じて、住居地、社会保障、税などの手続きに同行し、書類作成を補助すること 4。マイナンバーの手続きや自転車の防犯登録なども含まれる 11。 | 特になし |
| 日本語学習の機会の提供 (Providing Opportunities for Japanese Language Study) | 日本語教室の入学案内や日本語学習教材の情報提供など、日本語を学ぶ機会を提供すること 4。自主学習のためのオンライン講座や学習教材の情報提供、必要に応じて利用・入会の手続きのサポートも含む 11。 | 特になし |
| 相談・苦情への対応 (Consultation and Complaint Support) | 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語で対応し、内容に応じた必要な助言、指導等を行うこと 4。即時対応と相談記録書の作成が求められる 11。 | 特になし |
| 日本人との交流促進 (Promoting Interaction with Japanese People) | 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等を行うこと 4。 | 特になし |
| 転職支援(人員整理等の場合) (Employment Change Support in Case of Layoffs, etc.) | 受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合、転職先を探す手伝いや推薦状の作成に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供すること 4。 | 特になし |
| 定期的な面談・行政機関への通報 (Regular Interviews and Reporting to Administrative Authorities) | 外国人及びその監督者と定期的に(3か月に1回以上)面談し、労働基準法等の違反があった場合は行政機関へ通報すること 4。 | 面談対象となる特定技能外国人の同意がある場合、オンライン面談の実施が可能となる。ただし、頻度は3か月に1回以上を維持する必要がある 7。 |
2025年には、義務的支援に関していくつかの変更点と新たな規定が導入されます7。まず、特定技能外国人支援計画の策定において、「地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものであること」が求められるようになります。これは、外国人労働者が地域社会に溶け込み、地域社会の一員として生活できるよう、地域社会の取り組みとの連携を強化するものです。
出入国する際の送迎については、登録支援機関が委託を受けて車両を利用して送迎を行う場合、道路運送法に抵触しないための具体的な事例などが明確化されます。これにより、送迎サービスの提供における法的解釈の曖昧さが解消され、より円滑な支援が期待されます。
また、定期的な面談については、これまで原則として対面での実施が求められていましたが、2025年4月1日以降、面談対象となる特定技能外国人の同意があれば、オンラインでの実施が可能となります。ただし、面談の頻度は引き続き3か月に1回以上を維持する必要があります。この変更は、遠隔地にいる場合や、感染症の流行時などにおいても、柔軟に面談を実施できる利便性をもたらします。
これらの変更点は、特定技能制度の運用状況を踏まえ、外国人労働者への支援体制をより充実させ、効率化を図ることを目的としています。
4. 任意的支援の検討
任意的支援(任意的支援)は、登録支援機関が義務的支援に加えて、特定技能1号の外国人労働者に対して行うことが望ましいとされる支援です3。これらの支援は、外国人労働者の日本での生活の質を高め、よりスムーズな社会統合を促進することを目的としています。任意的支援は、支援計画に記載するかどうかは任意ですが、計画に記載された場合は、義務的支援と同様に実施する義務が生じるため注意が必要です3。
任意的支援の具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます3。
- 事前ガイダンスに関する任意的支援: 日本の気候や適切な服装、本国から持参すべき物、当面必要となる費用の目安、受け入れ機関から支給される物品など、より詳細な生活情報の提供や、事前ガイダンス後も継続的な相談対応を行うことが望まれます3。
- 住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援: 雇用契約終了後や転職時の住居探し、義務的支援に含まれない生活関連契約(保険など)のサポートなどが考えられます3。
- 生活オリエンテーションに関する任意的支援: 国民健康保険や国民年金の手続きなど、外国人自身が行う必要のある行政手続きへの同行や補助が推奨されます3。
- 日本語学習の機会の提供に関する任意的支援: 職員による日本語指導や講習の実施、日本語能力試験の受験支援、資格取得者への優遇措置、日本語学習費用の補助などが挙げられます3。
- 相談・苦情への対応に関する任意的支援: 外国人自身が公的機関に相談・苦情を申し立てるための窓口情報提供、登録支援機関内に専門の相談窓口や連絡先を設置すること、労災手続きに関する家族への情報提供などが考えられます3。
- 日本人との交流促進に関する任意的支援: 地域行事への参加を希望する外国人への勤務時間調整や有給休暇付与の配慮、登録支援機関が主体となって交流イベントを企画・開催することなどが期待されます3。
- 転職支援に関する任意的支援: 義務的支援を超える、より専門的なキャリアカウンセリングや求職活動のサポートなどが考えられます。
- 経済的支援: 特定のニーズに対する経済的な援助を行う場合もありますが、一般的ではありません13。
これらの任意的支援は、義務的支援を補完し、外国人労働者がより快適に日本で生活し、働くための環境を整備する上で重要な役割を果たします。登録支援機関が提供する任意的支援の充実度は、外国人労働者や受け入れ機関にとって、機関選択の重要な要素となる可能性があります。
5. 全国における登録支援機関の現状
2025年3月26日現在、全国で10,000を超える登録支援機関が登録されています6。出入国在留管理庁のウェブサイトでは、これらの登録機関のリストが随時更新されており、その活動状況を把握することができます。これだけの数の登録支援機関が存在することは、日本において特定技能外国人労働者の受け入れと支援が広範囲にわたって行われていることを示しています。
すべての登録支援機関は、法的に定められた10項目の義務的支援を提供する必要がありますが、それぞれの機関の規模、専門分野、経験、財政状況などによって、提供される支援の範囲や質には差異が生じる可能性があります。外国人労働者の受け入れが多い地域や、特定の産業分野に特化した支援を行っている機関では、より専門的で質の高いサービスが提供されていることも考えられます。
受け入れ機関や外国人労働者が登録支援機関を選ぶ際には、以下の要素を考慮することが重要です。まず、出入国在留管理庁の登録リストに掲載されているかを確認し、正規の登録機関であることを確かめる必要があります。次に、機関の外国人支援の実績や経験、外国人労働者が理解できる言語での対応能力などを評価することが重要です。さらに、義務的支援に加えて、どのような任意的支援を提供しているか、その内容や質も比較検討することが望ましいでしょう。
6. 2025年の主要な更新と動向
厚生労働省が2024年10月末時点の外国人雇用状況をまとめた報告によると、日本で働く外国人労働者数は増加傾向にあり12、特定技能制度の重要性が増しています。また、2025年4月1日からは、出入国在留管理庁に提出する各種届出の様式が更新される予定です7。登録支援機関は、四半期ごとの定期届出を行う義務があり7、2024年1月1日からは、この定期面談は原則として対面で実施する必要があります10。これらの動向は、制度が継続的に見直され、運用が改善されていることを示唆しています。
登録支援機関とその支援サービスに関する今後の動向としては、いくつかの可能性が考えられます。まず、特定の産業分野や外国人労働者の国籍に特化した専門性の高い登録支援機関が増加する可能性があります。また、オンラインでの言語学習プラットフォームやデジタルコミュニケーションツールなど、テクノロジーを活用した支援サービスの導入が進むことも予想されます。さらに、支援サービスの質と効果に対する関心が高まり、将来的には登録機関の評価基準がより厳格化される可能性も考えられます。
7. 実践的なガイダンスとベストプラクティス
登録支援機関制度や義務的支援・任意的支援に関する詳細な情報については、出入国在留管理庁や厚生労働省が公表している公式ガイドラインやFAQを参照することが最も重要です。これらの情報は随時更新されるため、常に最新の情報を確認するように努める必要があります。
義務的支援と任意的支援を効果的に実施するためには、外国人労働者との円滑なコミュニケーションと文化的な感受性が不可欠です。それぞれの外国人労働者の日本語能力、文化的背景、個別の状況などを考慮し、ニーズに合わせた支援計画を策定することが推奨されます。登録支援機関、受け入れ機関、外国人労働者の間で緊密なコミュニケーションチャネルを確立し、外国人労働者が理解できる言語で支援を提供することが重要です。また、支援担当者に対して、関連法規、制度、異文化コミュニケーションに関する定期的な研修を実施することも効果的です。
実際に成功している登録支援機関の例としては、地域社会との連携を積極的に行い、交流イベントなどを頻繁に開催することで、外国人労働者の孤立を防ぎ、地域社会への統合を促進している機関が挙げられます。また、日本語学習支援においては、オンライン教材の提供だけでなく、職場での実践的な日本語指導や、資格取得支援などを組み合わせることで、より高い学習効果を上げている例もあります。
8. 支援サービスの戦略的重要性
登録支援機関による適切な支援は、特定技能外国人労働者が日本社会と職場で円滑に適応し、長期的に就労を継続するために不可欠な役割を果たします。十分なサポートは、外国人労働者の仕事への満足度を高め、離職を防ぎ、受け入れ機関にとっても安定した労働力の確保につながります。また、効果的な支援は、受け入れ機関の評判を高め、より多様で包括的な職場環境の構築に貢献します。
義務的支援と任意的支援の充実は、特定技能制度全体の成功にとっても重要な意味を持ちます。外国人労働者が日本での生活や仕事に満足し、良い経験を積むことができれば、日本の労働市場の魅力が高まり、より多くの優秀な外国人材の受け入れにつながる可能性があります。逆に、支援体制が不十分であれば、外国人労働者の不満や早期離職を招き、制度の目的達成を阻害する要因となりかねません。したがって、質の高い支援サービスの提供は、単なる法令遵守にとどまらず、日本の労働力不足解消と国際協力の推進という broader な目標達成に不可欠な戦略的投資と言えるでしょう。
9. 結論と提言
本報告書では、2025年における登録支援機関の義務的支援と任意的支援について、その法的枠組み、具体的な内容、全国的な現状、そして今後の動向について詳細に分析しました。分析の結果、特定技能制度は、日本の労働力不足を補う上で重要な役割を果たしており、その成功には登録支援機関による適切な支援が不可欠であることが改めて確認されました。
この分析を踏まえ、関係者に対して以下の提言を行います。
- 受け入れ機関に向けて: 登録支援機関の選定にあたっては、実績、提供サービスの内容、外国人労働者への対応能力などを慎重に評価し、自社のニーズに最も適した機関を選ぶべきです。また、義務的支援だけでなく、外国人労働者のより良い定着のために、任意的支援の提供も検討することが望ましいです。
- 登録支援機関に向けて: 提供する支援サービスの質と範囲を継続的に改善し、特に任意的支援の充実を図ることで、競争力を高めることができます。また、支援担当者の専門性向上に向けた研修や、最新の法規制に関する知識のアップデートを怠らないようにする必要があります。
- 潜在的な外国人労働者に向けて: 日本での就労にあたっては、自身が受けられる義務的支援の内容を十分に理解し、必要に応じて任意的支援についても確認することが重要です。また、困ったことがあれば、遠慮なく受け入れ機関や登録支援機関に相談するべきです。
- 日本政府に向けて: 登録支援機関の活動状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて制度の見直しや改善を行うべきです。また、全国の登録支援機関のサービス品質の均質化を図るための施策や、ベストプラクティスの共有を促進することも重要です。
これらの提言を実行することで、特定技能制度がより効果的に機能し、日本社会と外国人労働者の双方にとってより良い結果をもたらすことが期待されます。
引用文献
- 育成就労制度の概要, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf
- 【2025】特定技能制度の「登録支援機関」とは?申請要件と選び方をわかりやすく解説, 4月 1, 2025にアクセス、 https://meikoglobal.jp/magazine/registered-support-organization-for-specified-skill-system/
- 【2025年版】登録支援機関とは?特定技能外国人支援に関する役割 …, 4月 1, 2025にアクセス、 https://linku-s.com/media/tourokushienkikan/
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html
- 特定技能で登録支援機関が担う役割や支援の委託が必要なケースを紹介, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.careerlinkfactory.co.jp/blog/specific-skills-rso/
- 登録支援機関(Registered Support Organization) | 出入国在留管理庁, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html
- 特定技能制度における運用改善について | 出入国在留管理庁, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
- 特定技能の定期届出・定期報告・随時届出についてわかりやすく解説! | 外国人採用サポネット, 4月 1, 2025にアクセス、 https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/19276
- 「登録支援機関」の役割とは?義務的支援の内容や監理団体との違いを外国人雇用労務士が解説, 4月 1, 2025にアクセス、 https://japannesia.com/howto/support-organization/
- 特定技能制度 | 出入国在留管理庁 – 法務省, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- 特定技能外国人の義務的支援 必須10項目から支援計画まで徹底解説, 4月 1, 2025にアクセス、 https://nihongocafe.jp/specific-skills-foreigners-mandatory-support/
- 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点) – 厚生労働省, 4月 1, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html
- 【社労士監修】【2025年度版】外国人雇用に関する助成金・補助金一覧!自治体の支援も, 4月 1, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/hr-recruiting/212/

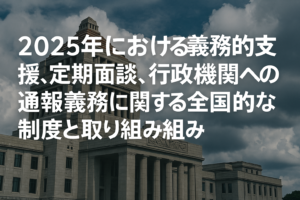


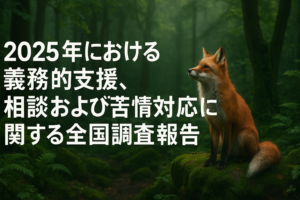
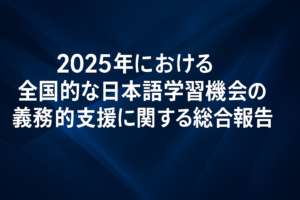
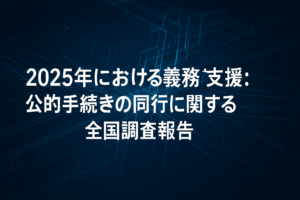
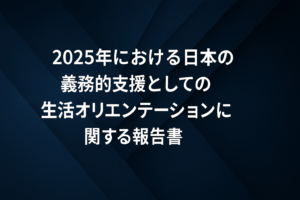

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 2025年における登録支援機関の義務的支援と任意的支援に関する全国調査報告書, 4月 2, 2025にアクセス、 https://blog.kenkyo.ai/2025/04/01/2025%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%99%BB%E9%8C%B… […]
[…] 2025年における登録支援機関の義務的支援と任意的支援に関する全国調査報告書, 4月 3, 2025にアクセス、 https://blog.kenkyo.ai/2025/04/01/2025%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%99%BB%E9%8C%B… […]