「不動産を売却したら、手元にいくら残るんだろう?」
「仲介手数料以外にも、いろいろ費用がかかるって聞くけど、具体的に何にいくら?」
2025年に不動産の売却をお考えのあなたへ。売却代金から差し引かれるのは、不動産会社に支払う仲介手数料だけではありません。実は、それ以外にも様々な諸費用が発生し、これらを正確に把握していないと、「思ったより手残りが少なかった…」と後悔することになりかねません。
一般的に「諸費用は売却価格の4~6%程度」と言われることもありますが、これはあくまで目安。実際には、税金、登記費用、状況によっては測量費や解体費など、物件や状況によって金額は大きく変動します。中には数百万円単位になる費用もあり、事前の把握と資金計画が非常に重要です。
この記事では、2025年の不動産売却において仲介手数料を除き、全国的に発生しうる諸費用の種類、金額の目安、計算方法、そして注意点を徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたの不動産売却で「何に」「いつ」「いくらくらい」費用がかかるのかが明確になり、安心して売却準備を進めるための具体的なステップが見えてきます。損しない、後悔しない不動産売却のために、ぜひ最後までご確認ください。
必ずかかる費用は?税金と登記関連費用
不動産を売却する際、ほぼ確実に発生する費用があります。まずは、これらをしっかり押さえましょう。
1. 印紙税:売買契約書に必要な税金
- 何にかかる?:不動産売買契約書を作成する際に課税される国税です。
- いくら?:契約書に記載される売買価格によって決まります。2027年3月31日までは軽減措置が適用されています。
- 表1:不動産売買契約書の印紙税額(2025年・軽減税率適用)
| 契約金額(売買価格) | 軽減後の税額 |
| :——————————- | :———– |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| (※10万円超~500万円以下も規定あり) | | - 出典:国税庁資料等に基づき簡略化
- 表1:不動産売買契約書の印紙税額(2025年・軽減税率適用)
- いつ払う?:売買契約締結時に、契約書に収入印紙を貼って納付します。通常、売主・買主それぞれが保管する契約書1通分ずつ負担します。
2. 登記費用:権利関係を整理する費用
- 何にかかる?:不動産の権利情報を登記簿に記録(登記)するための費用です。売主が主に関わるのは「抵当権抹消登記」です。
- 構成要素:
- 登録免許税:登記手続き自体にかかる国税。
- 司法書士報酬:手続きを代行する司法書士への報酬。
抵当権抹消登記
- なぜ必要?:住宅ローンなどが残っている場合、完済して抵当権を抹消しないと売却できません。
- いくら?:
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円(土地+建物なら通常2,000円)。
- 司法書士報酬:約1.5万円~1.6万円程度が全国平均ですが、地域や事務所により8千円~3万円超と幅があります。登記簿上の住所変更などが同時に必要な場合は加算されます。
- いつ払う?:通常、決済(引渡し)時に司法書士に支払い、手続きを代行してもらいます。
住所・氏名変更登記(必要な場合)
- なぜ必要?:登記簿上の住所・氏名が現在と異なる場合、所有権移転の前に変更登記が必要です。
- いくら?:登録免許税(不動産1個につき1,000円)+司法書士報酬(約1万円~1.2万円程度)。
司法書士報酬の地域差
司法書士報酬は全国一律ではなく、都市部(特に近畿、中部、関東など)の方が地方(東北、九州など)よりも高くなる傾向があります。あくまで目安と考え、可能であれば事前に見積もりを取りましょう。
3. 住宅ローン繰上返済手数料
- 何にかかる?:売却に伴い住宅ローンを一括返済する際に、金融機関に支払う手数料です。
- いくら?:金融機関や商品によって無料~数万円(一般的に5千円~3万円、時に5万円超)と大きく異なります。インターネット手続きだと安い場合も。
- いつ払う?:通常、決済時に売却代金から返済する際に発生します。
- 注意点:ローン残高がある方は、必ず事前にご自身の金融機関に確認しましょう。
利益が出たら要注意!譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。これは最も高額になる可能性のある費用の一つです。
どんな時にかかる?譲渡所得の計算方法
- 基本:売却価格が「取得費(買ったときの費用)」と「譲渡費用(売るときの費用)」の合計額を上回った場合、その差額(利益)が課税対象です。
- 計算式:
課税譲渡所得金額 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 - 取得費とは?:
- 土地・建物の購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税、改良費など。
- 建物は所有期間中の価値減少分(減価償却費)を差し引きます。
- 重要!:購入時の契約書などで取得費を証明できない場合、売却価格の5%を「概算取得費」とすることもできますが、実際の取得費より低くなり、税金が大幅に高くなる可能性があります。購入時の書類は絶対に保管しましょう!
- 譲渡費用とは?:
- 売却のために直接かかった費用。仲介手数料(本記事では除外)、売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記費用(登録免許税+司法書士報酬)、売却のための測量費、売却のための解体費用などが該当します。
- 注意:通常の修繕費やハウスクリーニング費用は含まれません。
- 特別控除額とは?:一定の要件を満たす場合に、税負担を軽減するために譲渡所得から差し引ける金額(後述)。
税率はどのくらい?所有期間で大きく変わる!
税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。
- 所有期間の判定:売却した年の「1月1日時点」で判断します。
- 短期譲渡所得:所有期間5年以下
- 長期譲渡所得:所有期間5年超
- 注意!「1月1日時点」ルール:例えば2020年5月に購入し2025年11月に売却した場合、実際の所有期間は5年超ですが、2025年1月1日時点では5年以下のため「短期」扱いになります。長期の税率を適用するには2026年1月1日以降の売却が必要です。
- 税率(2025年):
- 表2:譲渡所得税・住民税の税率(復興特別所得税含む)
| 区分 | 合計税率 |
| :————— | :——— |
| 短期譲渡所得 (5年以下) | 39.63% |
| 長期譲渡所得 (5年超) | 20.315%| - 出典:国税庁資料等に基づく
- ご覧の通り、短期の税率は長期のほぼ倍! 可能であれば所有期間5年超での売却が節税の大きなポイントです。
- 表2:譲渡所得税・住民税の税率(復興特別所得税含む)
税金を安くできるかも?主な特例・控除
特にマイホーム(居住用財産)の売却には、税負担を大幅に軽減できる特例があります。適用には要件を満たし、確定申告が必要です。
- マイホームの3,000万円特別控除
- 内容:マイホームを売却した場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。利益が3,000万円以下なら税金はゼロに。
- 主な要件:自分が住んでいた家であること、親子・夫婦間など特別な関係者への売却でないこと、他の特例(住宅ローン控除など)と併用できない場合があること、など。
- ポイント:非常に強力な控除。夫婦共有名義なら、それぞれ適用できれば最大6,000万円控除の可能性も。税金がゼロでも確定申告は必須です。
- 10年超所有の軽減税率(マイホーム)
- 内容:所有期間10年超のマイホームの場合、上記3,000万円控除後の課税譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分について、さらに低い税率(合計14.21%)が適用されます。
- ポイント:3,000万円控除と併用可能。長期所有のマイホーム売却で利益が大きい場合に有利。
- 空き家(相続した家)の3,000万円特別控除
- 内容:相続した被相続人(亡くなった方)の家(空き家)を売却した場合、一定要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
- 主な要件:耐震基準を満たすか家屋を取り壊すこと、相続開始から一定期間内の売却であること、など詳細な要件あり。
- ポイント:相続した空き家の売却を検討する際に必ず確認したい特例。
いつ、どうやって払う?確定申告
- 時期:譲渡所得が発生した場合、売却した年の翌年2月16日~3月15日に確定申告が必要です。
- 申告:特例を適用して税金がゼロになる場合でも、必ず確定申告をしなければ控除は受けられません。
- 納付:所得税(+復興特別所得税)は申告期限(通常3月15日)までに納付。住民税は後日送られてくる通知書に基づき、通常6月以降に納付します。
ケースバイケース!状況によってかかる費用
上記の費用以外にも、物件の状況や売主の判断によって、以下のような費用が発生することがあります。
1. 土地の境界を確定する「測量費」
- どんなとき?:主に土地や古い一戸建てで、隣地との境界がはっきりしない場合。トラブル防止のため、売主には境界を明示する義務があります。隣地所有者や役所との立会いが必要な「確定測量」が一般的。
- いくら?:土地の状況によりますが、数十万円(例:30万円~100万円以上)かかることが一般的。官民境界の確定が必要だと高額・長期化しやすい。
- いつ?:売却活動開始前。確定に数ヶ月~半年以上かかることも。
- ポイント:高額かつ時間のかかる可能性がある重要費用。特に土地売却では必須となるケースが多い。早期に必要性を確認し、見積もり取得を。
2. 古い家を取り壊す「解体費用」
- どんなとき?:土地上の古い建物の価値が低い、または買主が更地を希望する場合に、建物を取り壊して更地として売却するため。
- いくら?:建物の大きさ、構造(木造か鉄骨かRCか)、立地、廃棄物の量などで大きく変動。一般的な木造一戸建て(30~40坪)で100万円~300万円程度が目安。RC造はさらに高額。塀や庭木の撤去費用も別途かかる場合あり。
- いつ?:更地で売るなら売却活動開始前。
- ポイント:非常に高額になる可能性がある費用。解体費用を売却価格に上乗せできるとは限らないため、「古家付き土地」として売る方が有利な場合も。不動産会社とよく相談して判断を。
3. 見た目を良くする費用(ハウスクリーニング等)
- どんなとき?:内覧時の印象を良くし、早期・高値売却を目指すため。
- いくら?:
- ハウスクリーニング:数万円~10万円程度(広さ・汚れ具合による)。水回りだけでも効果的(各1~2万円程度)。
- 軽微な修繕:壁紙の部分補修、ドアノブ交換など。費用は内容次第。大規模リフォームは費用回収が難しく非推奨なことが多い。
- 不要品処分:量や種類による。
- ポイント:必須ではないが、少ない投資で効果が期待できる場合も。費用対効果を考えて実施を検討。
4. 引っ越し費用
- どんなとき?:売主が住んでいた物件を売却する場合。
- いくら?:荷物量、距離、時期(繁忙期は高額)により数万円~数十万円以上。
- ポイント:売却全体の資金計画に必ず含めるべき費用。繁忙期(2~4月)は特に高額になるので注意。
5. その他(インスペクション、地中埋設物など)
- 建物状況調査(インスペクション):専門家による建物診断。買主の安心のため、または情報開示のために実施。5万円程度~。
- 土壌汚染調査:工場跡地などで必要になる可能性。調査・対策には高額(数十万円~)な費用がかかることも。
- 地下埋設物撤去:解体時などに予期せぬ障害物(古い基礎、浄化槽など)が見つかることも。撤去に高額(時に100万円超)な費用がかかるリスクあり。
- 書類取得費用:住民票、印鑑証明書などの発行手数料(1通数百円)。
物件タイプ別!費用の違いと注意点
売却する物件の種類によって、かかりやすい費用や注意点が異なります。
一戸建て
- 測量費が発生しやすい。
- 古い場合は解体費用の検討が必要になることも。
- 建物の状態が価格に影響しやすく、修繕費用がかさむ可能性。
- 土地関連リスク(地下埋設物など)がマンションより高い。
マンション
- 管理費・修繕積立金の精算(日割り等)が必要。
- 火災保険料や住宅ローン保証料の返金を受けられる可能性あり(要手続き)。
- 通常、測量費・解体費用は不要。
土地
- 測量費がほぼ必須となるケースが多い。
- 古家があれば解体費用。
- 土壌汚染や地下埋設物、インフラ整備状況のリスク確認が重要。
- 土地自体の売却は消費税非課税だが、関連サービス(測量、解体、仲介手数料等)には消費税がかかる。
全国共通?地域による違いは?
- 全国共通ルール:印紙税、登録免許税、譲渡所得税・住民税などの税金。
- 地域差あり:司法書士報酬、測量費、解体費用、ハウスクリーニング費用など、専門家や業者に支払うサービス費用。一般的に都市部の方が地方よりも高くなる傾向があります。
まとめ:後悔しない!2025年 不動産売却の費用計画 完全ガイド
2025年の不動産売却では、仲介手数料以外にも多くの諸費用がかかります。印紙税や登記費用といった必須コストから、状況に応じて発生する高額な測量費、解体費、そして利益が出た場合の譲渡所得税まで様々です。
これらの費用を事前にしっかり把握し、資金計画に織り込むことが、売却を成功させ、手元に残るお金を最大化するための鍵となります。
成功のための重要ポイント:
- 早期に調査・予算化を!:どんな費用がかかりそうか、早めにリストアップし、概算額を把握しましょう。
- 正確な計算と見積もり取得を!:特に譲渡所得税は、取得費の証明と控除の活用が節税の鍵。変動が大きい費用(司法書士報酬、測量費、解体費など)は必ず見積もりを取りましょう。
- 書類は宝物!大切に保管を!:購入時の売買契約書や領収書は、取得費を証明する重要な証拠です。
- 専門家を味方に!:不動産会社はもちろん、登記は司法書士、税金は税理士など、必要に応じて専門家の力を借りましょう。
不動産売却は人生における大きなイベントの一つです。この記事を参考に、諸費用に関する知識を深め、周到な資金計画を立てることで、2025年の不動産市場において、あなたが納得できる売却を実現されることを願っています。
【免責事項】
※この記事は、一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務アドバイスを提供するものではありません。
※税制や各種料金は変更される可能性があります。最新かつ正確な情報は、必ず国税庁、関連省庁、各自治体、金融機関、専門家等にご確認ください。
※具体的な売却計画や費用計算については、必ず不動産会社、司法書士、税理士等の専門家にご相談ください。



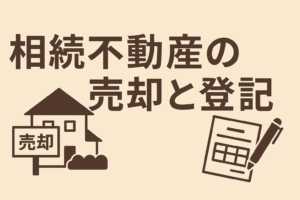

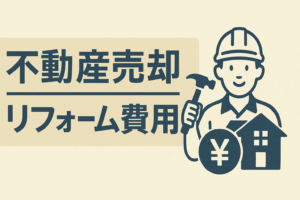


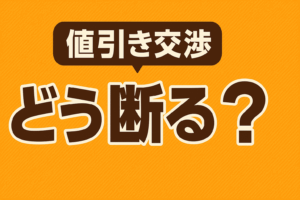
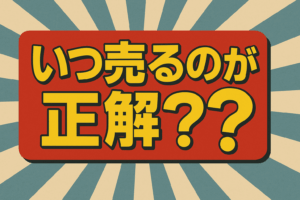
コメント